- 2025年9月11日
- 2025年9月16日
インフルエンザ予防接種の効果と接種時期 | 松戸市の内科医が詳しく解説

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。まだまだ暑い日が続きますが、少し季節を先取りして今回はインフルエンザの話です。
毎年秋から冬にかけて流行するインフルエンザ。「今年も予防接種を受けた方がいいのかな?」「いつ頃受ければいいの?」「副反応は大丈夫?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。インフルエンザは単なる風邪とは異なり、高熱や全身の倦怠感など重篤な症状を引き起こすことがあり、特に高齢者や持病をお持ちの方では重症化のリスクが高まります。予防接種は、このようなリスクを大幅に軽減できる効果的な予防手段です。本記事では、松戸市で内科クリニックを開院する医師として、インフルエンザ予防接種について皆様が知っておくべき重要な情報を、分かりやすく詳しく解説いたします。
目次

インフルエンザとは?基礎知識を理解しましょう
インフルエンザウイルスの特徴
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性の呼吸器感染症です。このウイルスは主にA型、B型、C型の3つの型に分類され、このうちA型とB型が毎年の季節性インフルエンザの原因となります。
特にA型インフルエンザウイルスは変異しやすい性質を持っており、毎年少しずつ性質を変えながら流行します。これが、毎年新しいワクチンが必要となる理由です。
感染経路について
インフルエンザの感染は主に以下の経路で起こります。
飛沫感染:感染者のくしゃみや咳によって飛び散ったウイルスを含む飛沫を、他の人が吸い込むことで感染します。電車内や職場、学校などの人が密集する場所では特に注意が必要です。
接触感染:ウイルスが付着したドアノブ、手すり、スマートフォンなどを触った手で口や鼻を触ることで感染します。日常生活の中で最も起こりやすい感染経路の一つです。
潜伏期間と感染力
インフルエンザウイルスに感染してから症状が現れるまでの潜伏期間は、通常1〜3日程度です。感染力が最も強いのは発症前日から発症後3日目頃までとされており、この期間は特に他の人への感染リスクが高くなります。

インフルエンザの症状と日常生活への影響
典型的な症状
インフルエンザの症状は風邪とは大きく異なり、より急激で強い症状が特徴です。
全身症状
- 38℃以上の高熱(しばしば39℃を超える)
- 激しい頭痛
- 全身の筋肉痛や関節痛
- 強い倦怠感(だるさ)
- 悪寒
呼吸器症状
- 咳(乾いた咳から始まることが多い)
- のどの痛み
- 鼻水や鼻づまり
風邪との違い
一般的な風邪と比べて、インフルエンザは症状の現れ方が急激で強い傾向があります。風邪では微熱程度のことが多いのに対し、インフルエンザでは突然の高熱で始まることが多く、「昨日まで元気だったのに、朝起きたら動けないほど具合が悪い」といった状況になることも珍しくありません。
日常生活への影響
インフルエンザにかかると、通常5日間は仕事や学校を休むことが必要になることが多いです。学校においては、「発症後5日を経過」し、かつ「解熱した後2日」となっています (学校保健安全法)。仕事においては、特に決まりはないので勤務先と相談ということになります。
これは単に体調不良というだけでなく、他の人への感染を防ぐ意味でも重要です。
また、完全に回復するまでには2週間程度かかることもあり、特に高齢者や持病をお持ちの方では、さらに長期間にわたって体調に影響が残ることがあります。
重症化のリスク
以下の方々は、インフルエンザが重症化しやすいとされています。
- 65歳以上の高齢者
- 妊娠中の女性
- 慢性呼吸器疾患(喘息など)をお持ちの方
- 心疾患をお持ちの方
- 糖尿病などの代謝性疾患をお持ちの方
- 免疫機能が低下している方
これらの方々にとって、予防接種は特に重要な意味を持ちます。
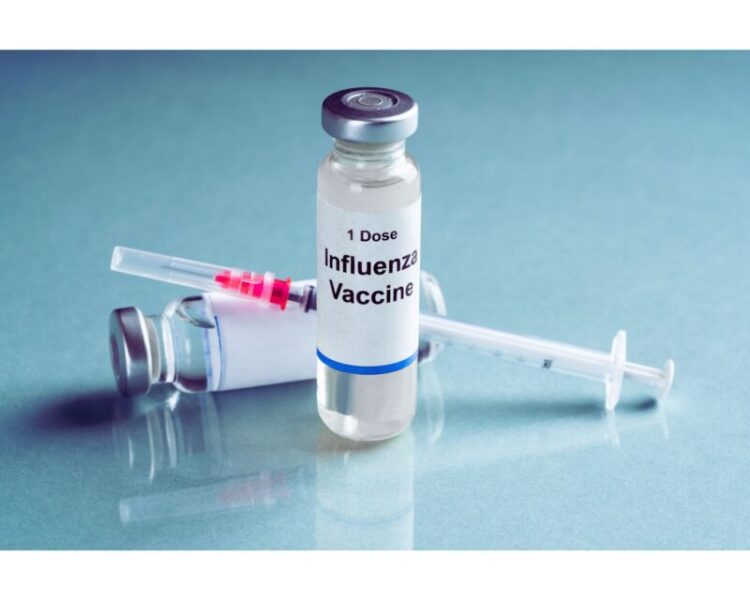
インフルエンザ予防接種の効果と仕組み
ワクチンの仕組み
インフルエンザワクチンは「不活化ワクチン」と呼ばれるタイプで、ウイルスの感染力を失わせた成分を体内に入れることで、免疫システムにウイルスを認識させ、抗体を作らせる仕組みです。
実際のウイルスではないため、ワクチン接種によってインフルエンザになることはありません。
予防効果について
適切な時期に接種されたインフルエンザワクチンの有効性は、年齢や流行するウイルス株によって変動しますが、一般的に以下のような効果が期待できます。
発症予防効果:健康な成人では約60〜70%、高齢者では約30〜50%程度の発症予防効果があるとされています。
重症化予防効果:仮に感染した場合でも、症状の重篤化を防ぐ効果が認められており、入院リスクを大幅に軽減することができます。
効果の持続期間
ワクチン接種による免疫効果は、接種後約2週間で現れ始め、その後約5ヶ月間持続するとされています。これが毎年の接種が推奨される理由の一つです。
集団免疫効果
個人の予防だけでなく、多くの人がワクチン接種を受けることで、地域全体での感染拡大を抑制する「集団免疫効果」も期待できます。これは、感染しやすい方々を間接的に守ることにもつながります。
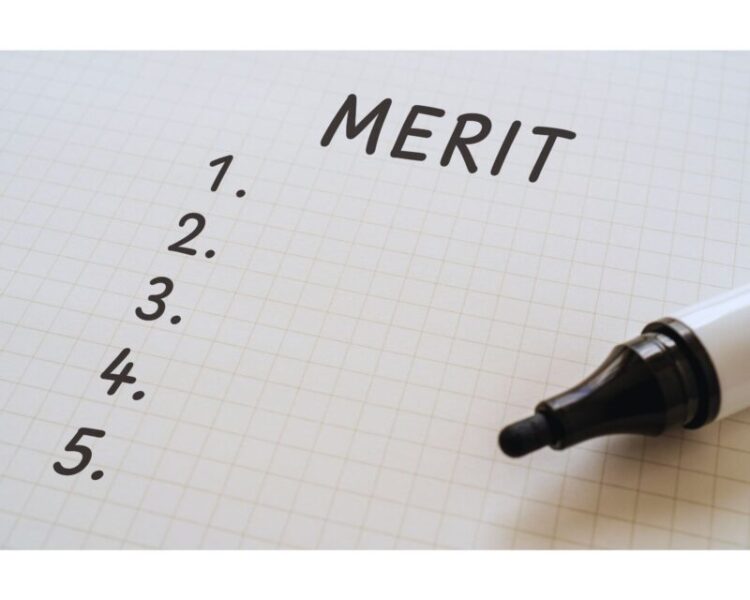
最適な接種時期と接種方法
接種時期の重要性
インフルエンザワクチンの接種時期は、効果を最大限に発揮するために非常に重要です。
推奨される接種時期:日本では例年10月〜12月初旬にかけてが接種の推奨時期とされています。これは以下の理由によります。
- ワクチン効果が現れるまで約2週間必要
- インフルエンザの流行は通常12月下旬から3月頃まで
- 効果の持続期間を考慮した最適なタイミング
接種回数について
13歳以上の方:原則として1回接種が推奨されています。ワクチンの添付文書には「13歳以上のものは1回または2回注射」と記載されていますが、以前の研究から、インフルエンザワクチンの1回接種で、2回接種と同等の抗体価の上昇が得られたとの報告があります。
13歳未満のお子様:2〜4週間の間隔をあけて2回接種することが推奨されています。これは、お子様の免疫システムがまだ発達途中であることを考慮した措置です。
- 6か月以上3歳未満の方 1回0.25mL 2回接種
- 3歳以上13歳未満の方 1回0.5mL 2回接種
接種できない方・注意が必要な方
以下の方は接種前に必ず医師にご相談ください。
接種できない方
- 重篤な急性疾患にかかっている方 (発熱など)
- インフルエンザワクチンの成分に対して重篤なアレルギー反応を起こしたことのある方
- その他、医師が接種不適当と判断した方
注意が必要な方 (以下添付文書からの抜粋ですが、下記の方はむしろ接種した方が良い方も含まれると思うので、主治医と相談してください。)
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方および全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
- 過去にけいれんの既往のある方
- 過去に免疫不全の診断がなされている方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する方
- インフルエンザワクチンの成分または鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーを呈するおそれのある方
副反応について
インフルエンザワクチンの副反応は一般的に軽微で、以下のようなものが報告されています。
局所反応(接種部位)10-20%
- 赤み、腫れ、痛み
- 通常2〜3日で自然に改善します
全身反応 5-10%
- 微熱
- 軽度の頭痛や倦怠感
- 通常1〜2日で改善します
重篤な副反応は極めて稀ですが、接種後に異常を感じた場合は速やかに医療機関にご相談ください。

よくある質問(Q&A)
Q1: 毎年接種する必要があるのはなぜですか?
A1: インフルエンザウイルスは毎年変異するため、前年のワクチンでは十分な効果が期待できない場合があります。また、ワクチンによる免疫効果は約5ヶ月間で徐々に減弱するため、毎年の接種が推奨されています。世界保健機関(WHO)が毎年流行予測を行い、それに基づいて新しいワクチンが製造されています。
Q2: 接種後にインフルエンザになることはありますか?
A2: インフルエンザワクチンは不活化ワクチンのため、接種によってインフルエンザになることはありません。ただし、以下の場合にインフルエンザを発症する可能性があります。
- 接種前にすでに感染していた場合
- 免疫が十分にできる前(接種後2週間以内)に感染した場合
- ワクチンに含まれていない型のウイルスに感染した場合
Q3: 卵アレルギーがあっても接種できますか?
A3: 軽度の卵アレルギーの場合、多くの方が接種可能です。現在のインフルエンザワクチンに含まれる卵タンパクの量は極めて微量です。ただし、重篤な卵アレルギーをお持ちの方は、必ず事前に医師にご相談ください。インフルエンザに罹った場合のリスクと卵アレルギーの程度によりバランスを考慮し相談いたします。
Q4: 妊娠中でも接種できますか?
A4: 妊娠中の方もインフルエンザワクチンの接種が可能で、むしろ推奨されています。妊娠中はインフルエンザが重症化しやすく、また生まれてくる赤ちゃんを感染から守る効果も期待できます。ただし、接種前には必ず担当の産婦人科医師にご相談ください。
Q5: 他のワクチンとの同時接種は可能ですか?
A5: インフルエンザワクチンは他のワクチンとの同時接種が可能です。(新型コロナウイルスワクチンとの同時接種も可能です。)
Q6: 接種後に注意すべきことはありますか?
A6: 接種後は以下の点にご注意ください。
- 接種当日は激しい運動や長時間の入浴は避ける
- 接種部位を強くこすらない
- アルコールの過度な摂取は控える
- 接種後30分程度は医療機関で様子を見ることが推奨されます
- 異常を感じた場合は速やかに医療機関にご連絡ください
Q7: 高齢者は特に注意すべき点はありますか?
A7: 高齢者の方は以下の点で特に注意が必要です。
- インフルエンザが重症化しやすいため、予防接種は特に重要
- 免疫反応が若い方より弱い可能性があるため、より一層の感染予防対策が必要
- 持病をお持ちの場合は、かかりつけ医との相談の上で接種スケジュールを決定
- 接種後の副反応の観察もより慎重に行うことが推奨されます

まとめ
インフルエンザ予防接種は、個人の健康を守るだけでなく、家族や地域社会全体の健康維持にも貢献する重要な予防手段です。
重要なポイント
- 適切な接種時期: 10月〜12月初旬の接種が効果的
- 継続的な接種: 毎年の接種により安定した予防効果を維持
- 重症化予防: 感染リスクの高い方にとって特に重要
- 安全性: 副反応は一般的に軽微で、重篤な副反応は極めて稀
当クリニックでは、患者様一人ひとりの健康状態や生活環境を考慮し、最適な予防接種プランをご提案いたします。インフルエンザシーズンを健康に過ごすために、ぜひお気軽にご相談ください。また、予防接種と併せて、手洗い・うがい、適切なマスクの着用、十分な睡眠と栄養摂取など、日常的な感染予防対策も継続していくことが大切です。
ご不明な点やご心配なことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。皆様の健康維持のお手伝いをさせていただきます。
参考文献・情報源
執筆者プロフィール
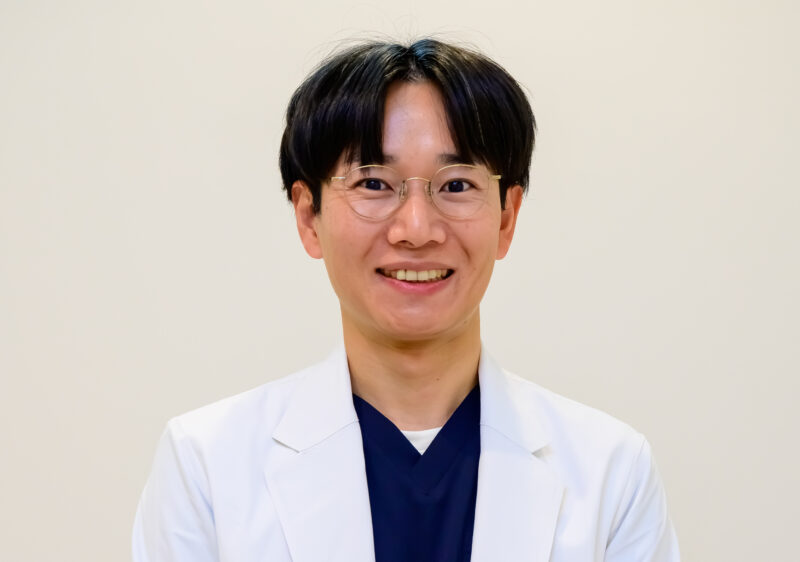
田邉弦
丹野内科・循環器・糖尿病内科 院長
- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医
- 日本循環器学会 循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会 認定医
- 日本内科学会 JMECCインストラクター
- 日本救急医学会 ICLSインストラクター
- 認知症サポート医
