- 2025年9月22日
女性のいびき:原因から対処法まで内科医が詳しく解説

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。今回は女性のいびきに関してのブログです。「恥ずかしくて人に相談できない」「女性なのにいびきをかくなんて…」そんな悩みを抱えていらっしゃる女性は少なくありません。いびきは男性の方が多いのは事実ですが、実は女性のいびきも珍しいことではありません。松戸市で内科クリニックを開業している私のもとにも、いびきに関するご相談を多くいただいております。本記事では、女性のいびきの原因や対処法について、医学的根拠に基づいて詳しく解説いたします。
目次

女性のいびきの基礎知識
いびきのメカニズム
いびきは、睡眠中に気道が狭くなることで生じる現象です。呼吸によって空気が気道を通る際、狭くなった部分で振動が起こり、あの特徴的な音が発生します。
これは楽器の原理と似ており、管楽器が細い管で音を出すように、気道が狭くなることで音が生まれるのです。
女性のいびきの特徴
一般的に、女性のいびきには以下のような特徴があります。
- 音が比較的小さい:男性と比べて気道の構造上、大きな音になりにくい傾向があります
- 断続的:継続的ではなく、断続的に起こることが多いです
- 年齢による変化:ホルモンバランスの変化により、閉経後の時期に現れやすくなります
統計データから見る女性のいびき
ある会社の調査によると、いびきに悩む女性の割合は約40%と報告されています。これは意外に多い数値で、年々増加傾向にあります。また、いびきに悩む人ほど、平均睡眠時間が短い傾向もあるとのことでした。

女性特有のいびきの原因
ホルモンバランスの影響
女性のいびきの最も特徴的な原因は、ホルモンバランスの変化です。
妊娠中のいびき
妊娠中は以下の理由でいびきが生じやすくなります。
- プロゲステロンの増加による鼻粘膜の腫れ
- 体重増加による気道への圧迫
- 睡眠姿勢の変化
実際に、妊娠前にはいびきをかかなかった方の約30%が、妊娠中にいびきを経験するという報告があります。
更年期のいびき
更年期においては、エストロゲンの減少が大きな要因となります。
- 筋肉の弾力性低下による気道の緩み
- 体重増加傾向
- 睡眠の質の変化
閉経後の注意点
特に閉経後の女性では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症リスクが大幅に増加することが知られています。これは、エストロゲンが気道を支える筋肉の機能維持に重要な役割を果たしているためです。
重要なのは、SASによる症状(不眠、日中の眠気、抑うつ症状、集中力低下など)が、更年期障害でよく見られる症状と非常によく似ていることです。そのため、更年期症状として見過ごされがちで、適切な診断と治療が遅れる可能性があります。
その他の主な原因
鼻の問題
- アレルギー性鼻炎
- 鼻中隔湾曲症
- 慢性副鼻腔炎
体型の変化
- 首回りの脂肪蓄積
- 舌や軟口蓋の肥大
- 顎の形状
生活習慣
- 飲酒
- 喫煙
- 睡眠薬の服用
- 睡眠不足

いびきが及ぼす健康への影響
睡眠の質への影響
いびきは、ご本人だけでなくパートナーの睡眠の質にも影響を与えます。
本人への影響
- 睡眠の断片化(何度も目が覚める)
- 深い眠りに入れない
- 日中の疲労感・眠気
- 集中力の低下
パートナーへの影響
- 睡眠不足による健康への悪影響
- 関係性のストレス
- 別々の部屋で寝る必要性
睡眠時無呼吸症候群のリスク
特に注意が必要なのは、いびきが睡眠時無呼吸症候群の症状である場合です。この病気は以下のような深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。
- 高血圧
- 心臓病
- 脳梗塞
- 糖尿病
- 認知機能の低下
- うつ病
女性の場合、更年期以降に睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まる傾向があります。特に閉経後の女性では発症率が男性に近づくとされており、注意が必要です。
睡眠時無呼吸の症状や合併症・治療に関しては以前のブログをご覧ください。
更年期症状との見分け方
閉経後の女性では、睡眠時無呼吸症候群による症状(不眠、日中の眠気、イライラ、抑うつ症状、記憶力低下など)が、更年期障害の症状と非常によく似ているため、見過ごされやすいという問題があります。
以下のような場合は、更年期症状だけでなく睡眠時無呼吸症候群の可能性も考慮することが大切です。
- ホルモン補充療法を行っても症状が改善しない
- パートナーから「呼吸が止まっている」と指摘される
- 朝起きたときの頭痛や口の渇きが強い
- 日中の眠気が運転や仕事に支障をきたすレベル

日常生活でできる予防法と対処法
睡眠環境の改善
適切な寝姿勢
- 横向き寝を心がける
- 枕の高さを調整する(首が自然なカーブを描く高さ)
- 抱き枕を使用して横向き寝を維持する
寝室環境の整備
- 適度な湿度(50-60%)を保つ
- 清潔な環境を維持し、アレルゲンを減らす
- 適切な室温を保つ
生活習慣の改善
体重管理
適正体重の維持は、いびき改善において非常に重要です。BMI(体格指数)25以上の方は、3-5kgの減量でもいびきの改善が期待できます。
食事の工夫
- 就寝3時間前以降の食事は控える
- アルコールの摂取量を減らす(特に就寝前)
- 水分摂取を適切に行う
運動習慣
- 定期的な有酸素運動
- 首や喉周りの筋肉を鍛える体操
- ヨガや深呼吸による筋肉のリラックス
具体的なエクササイズ
舌の体操
- 舌を大きく前に出す(5秒キープ)
- 舌先で鼻を触るように上に向ける(5秒キープ)
- 舌先で顎を触るように下に向ける(5秒キープ)
- これを5回繰り返す
喉の筋力アップ
- 大きく口を開けて「あ」の口の形で5秒キープ
- 口角を上げて「い」の口の形で5秒キープ
- 口をすぼめて「う」の口の形で5秒キープ
- 各5回ずつ行う

医療機関を受診する目安
以下の症状がある場合は、早めに医療機関での相談をお勧めします。
受診推奨症状
- 呼吸が止まる(10秒以上)
- 激しいいびきで家族が心配するほど
- 日中に強い眠気で運転や仕事に支障がある
- 朝起きたときの頭痛が続く
その他睡眠時無呼吸と関連する可能性のある症状
- 体重の増減に関わらずいびきが悪化
- 鼻づまりが慢性的に続いている
- 夜間頻尿が気になる
- 更年期治療を受けているが症状が改善しない(閉経後の女性)
閉経後の女性への特別な注意:50歳以降の女性で、更年期症状と思われる不眠、日中の眠気、抑うつ症状などがある場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性も考慮し、総合的な評価を受けることをお勧めします。
受診時の準備
医療機関を受診される際は、以下の情報をまとめておくと診断に役立ちます。
- いびきの頻度と音の大きさ
- 睡眠時間と質
- 日中の症状(眠気、疲労感など)
- 服用中の薬物
- アレルギーの有無
- 体重の変化
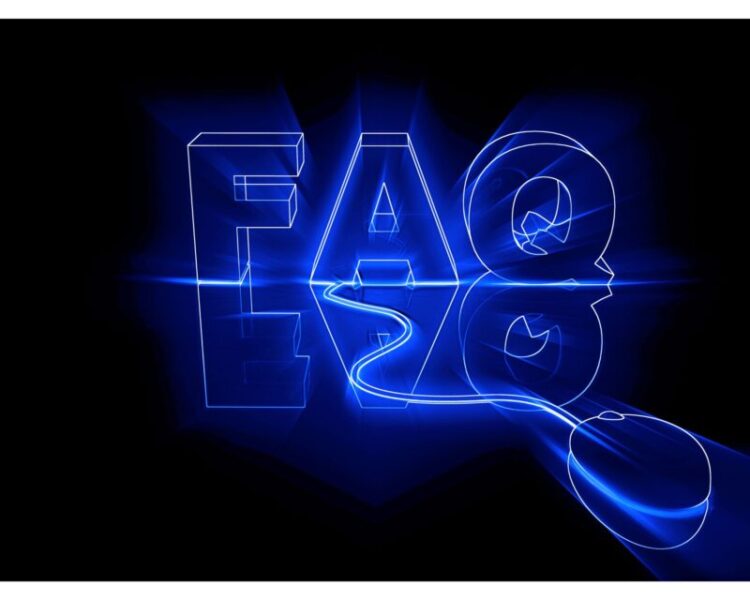
よくあるご質問(Q&A)
Q1: 女性でもいびきをかくのは普通ですか?
A: はい、女性でもいびきをかくのは決して珍しいことではありません。前述の通り、約40%の女性が習慣的にいびきを経験しており、年齢とともにその割合は増加します。恥ずかしがる必要はありませんので、気になる症状があれば遠慮なくご相談ください。
Q2: 妊娠中のいびきは赤ちゃんに影響しますか?
A: 軽度のいびきであれば、通常は赤ちゃんへの直接的な影響は少ないとされています。ただし、睡眠時無呼吸症候群を伴う場合は、母体の酸素不足が懸念されるため、かかりつけの産婦人科医との相談が推奨されます。
Q3: 市販のいびき対策グッズは効果がありますか?
A: 鼻腔拡張テープや口呼吸防止テープなど、一部の市販品には効果を実感される方もいらっしゃいます。ただし、根本的な原因によって効果は異なるため、継続的な症状がある場合は医療機関での診断をお勧めします。
Q4: いびきは完全に治すことができますか?
A: 原因によって治療法や改善度は異なります。生活習慣の改善で大きく改善する場合もあれば、骨格的な問題で困難な場合もあります。まずは原因を特定することが重要です。
Q5: 更年期の症状と思っていたものが、実は睡眠時無呼吸症候群だったということはありますか?
A: はい、閉経後の女性では睡眠時無呼吸症候群の発症率が増加し、その症状(不眠、日中の眠気、抑うつ症状、集中力低下など)が更年期症状と非常によく似ているため、見分けが困難な場合があります。ホルモン補充療法などの更年期治療を行っても症状が改善しない場合や、いびきを伴う場合は、睡眠時無呼吸症候群の検査をお勧めします。早期発見・治療により、生活の質の大幅な改善が期待できます。

まとめ
女性のいびきは、決して恥ずかしいことでも珍しいことでもありません。ホルモンバランスの変化や生活習慣、体型の変化など、様々な要因が関与する症状です。
重要なポイント
- 理解と受容:まずは、いびきが起こる理由を理解し、自分を責めないことが大切です
- 生活習慣の見直し:睡眠環境の改善、適正体重の維持、規則正しい生活リズムが基本となります
- 早期の相談:症状が長期間続く場合や、日常生活に影響がある場合は、早めの医療相談が推奨されます
- 継続的な取り組み:改善には時間がかかることもありますが、諦めずに継続することが大切です
私たちは、患者様が安心してご相談いただけるよう、丁寧に診療にあたっております。いびきでお悩みの際は、一人で抱え込まずに、お気軽に当院にご相談ください。良質な睡眠は、健康的な毎日を送るための基盤です。適切な対策により、快適な睡眠を取り戻し、生活の質の向上につなげていきましょう。
参考文献・情報源
執筆者プロフィール

田邉弦
丹野内科・循環器・糖尿病内科 院長
- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医
- 日本循環器学会 循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会 認定医
- 日本内科学会 JMECCインストラクター
- 日本救急医学会 ICLSインストラクター
- 認知症サポート医
