- 2025年10月17日
女性の貧血|その疲れやすさ、もしかして貧血かも?症状・原因・対処法を専門医が解説

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。「最近疲れやすい」「立ちくらみが増えた」「なんとなく体がだるい」このような症状に心当たりはありませんか?
実は日本人女性の約5人に1人が貧血、またはその予備軍と言われています。特に月経(生理)のある世代の女性では、貧血は決して珍しい病気ではありません。しかし、「よくあることだから」と見過ごしてしまうと、日常生活の質が大きく低下してしまう可能性があります。
この記事では、内科専門医として多くの貧血患者様を診てきた経験から、女性の貧血について詳しく解説いたします。貧血の基礎知識から症状、対処法まで、わかりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
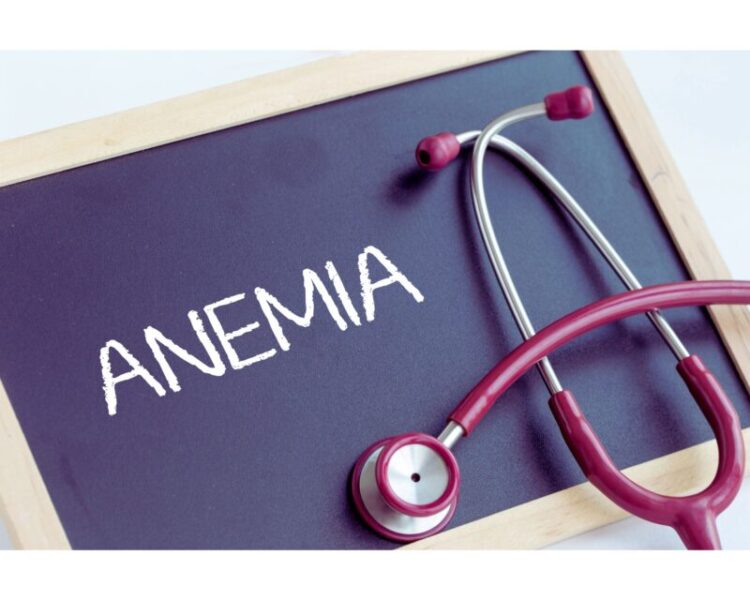
1. 女性に貧血が多い理由
貧血とは何か
貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビン(酸素を運ぶたんぱく質)が正常よりも少なくなった状態を指します。一般的に、ヘモグロビン値が成人女性で12g/dL未満の場合、貧血と診断されます。
立ちくらみやめまいのことをよく脳貧血と言ったりしますが、この用語は今回お話しする医学的な貧血とは関係なく、実際に血液検査上で貧血がある(ヘモグロビンが少ない)とは限りません。
赤血球は全身に酸素を届ける重要な役割を担っています。そのため、貧血になると体の隅々まで十分な酸素が行き渡らなくなり、さまざまな症状が現れるのです。
なぜ女性に多いのか
女性に貧血が多い理由は、主に以下の3つが挙げられます。
月経による鉄分の損失
月経のある女性は、毎月定期的に出血があります。経血には鉄分が含まれているため、月経のたびに体内の鉄分が失われていきます。特に月経量が多い方は、それだけ多くの鉄分を失うことになります。
妊娠・出産による鉄分の需要増加
妊娠中は、お母さん自身の血液量が増えるだけでなく、赤ちゃんの成長のためにも多くの鉄分が必要になります。出産時の出血でも鉄分が失われるため、妊娠・出産は女性の鉄分バランスに大きな影響を与えます。
ダイエットや偏食による鉄分摂取不足
美容や健康への関心から食事制限をされる方も多いですが、極端なダイエットは鉄分をはじめとする栄養素の不足を招きやすくなります。また、忙しい生活の中で食事が不規則になったり、偏った食生活になったりすることも、鉄分不足の原因となります。

2. 貧血の症状チェックリスト
貧血の症状は、ゆっくりと進行することが多いため、ご自身では気づきにくい場合があります。以下のような症状に心当たりがある方は、貧血の可能性が考えられます。
全身症状
- 疲れやすい、倦怠感が続く
- 息切れや動悸がする(階段を上るのがつらい)
- めまいや立ちくらみがする
- 集中力が続かない、記憶力の低下を感じる
- 頭痛や頭が重い感じがする
外見の変化
- 顔色が悪い、青白いと言われる
- 唇や爪の色が薄い
- 下まぶたの内側(結膜)が白っぽい
- 爪が薄くなったり、スプーン状に反り返ったりする
- 髪が抜けやすくなった
その他の症状
- 氷をバリバリ食べたくなる(氷食症)
- 食べ物や飲み物を飲み込みづらい
- 舌が荒れる、口角炎ができやすい
- 脚がむずむずして眠れない(むずむず脚症候群)
これらの症状が複数当てはまる場合は、一度医療機関での検査をお勧めいたします。
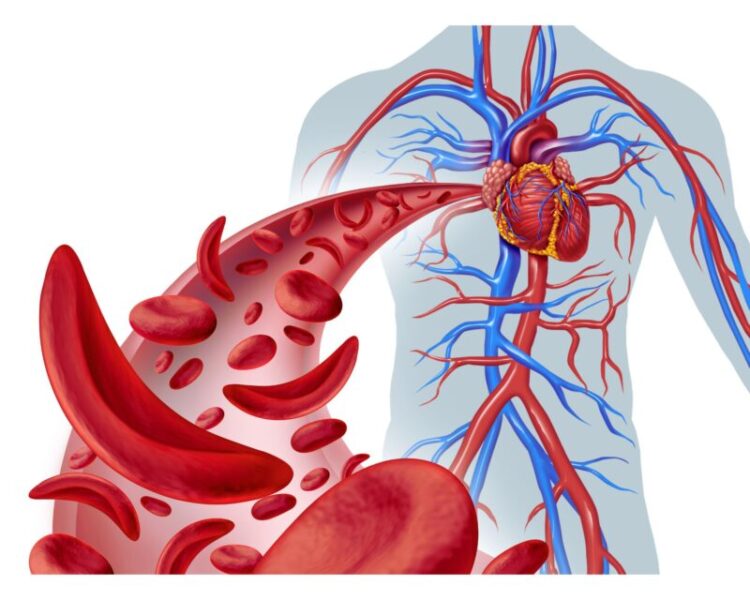
3. 貧血が女性の体に及ぼす影響
貧血を放置すると、日常生活にさまざまな支障が出る可能性があります。
仕事や学業への影響
集中力の低下や記憶力の減退により、仕事や勉強の効率が落ちてしまうことがあります。また、疲れやすさから休憩の回数が増えたり、通常の業務でも疲労感が強く残ったりすることがあります。
妊娠への影響
妊娠中の貧血は、お母さんだけでなく赤ちゃんにも影響を及ぼす可能性があります。早産や低出生体重児のリスクが高まるという報告もあるため、妊娠を考えている方や妊娠中の方は、特に貧血対策が重要です。
心臓への負担
貧血が長期間続くと、心臓は少ない酸素を補うために、より多くの血液を送り出そうとします。その結果、心臓に負担がかかり、動悸や息切れがひどくなることがあります。
免疫力の低下
鉄分は免疫機能にも関わっているため、貧血により免疫力が低下し、風邪をひきやすくなったり、感染症にかかりやすくなったりすることがあります。
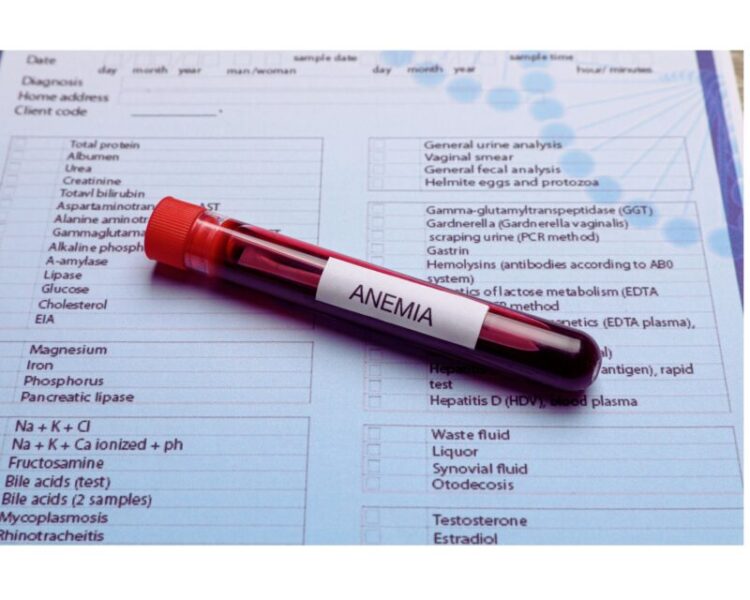
4. 貧血の検査と診断
血液検査
貧血の診断には、血液検査が必要です。主に以下の項目を確認します。
ヘモグロビン値(Hb)
正常値は女性で12〜16g/dL程度とされています。12g/dL未満の場合、貧血と診断されることが一般的です。
赤血球数(RBC)
赤血球の数を測定します。
ヘマトクリット値(Ht)
血液中の赤血球の割合を示す値です。
MCV(平均赤血球容積)
赤血球一個あたりの大きさを示します。鉄欠乏性貧血では、この値が低くなる傾向があります。
血清鉄、フェリチン
体内の鉄分の貯蔵量を示す指標です。フェリチンは「かくれ貧血」の発見にも役立ちます。
かくれ貧血とは
ヘモグロビン値は正常範囲でも、体内の鉄の貯蔵量(フェリチン)が少ない状態を「かくれ貧血」と呼びます。この段階で対策を始めることで、本格的な貧血への進行を防ぐことができます。

5. 貧血の治療法
貧血と診断された場合、原因に応じた治療が行われます。
鉄剤の服用
女性の貧血の多くは鉄欠乏性貧血であるため、鉄剤の服用が基本的な治療となります。鉄剤には錠剤やシロップなど、さまざまな形態があります。
鉄剤を服用する際の注意点として、以下のようなものがあります。
- 胃腸症状(吐き気、便秘、下痢など)が出ることがある
- 効果が現れるまでに数週間から数ヶ月かかる
注射による鉄分補給
経口の鉄剤では効果が不十分な場合や、胃腸症状が強くて飲めない場合は、静脈注射で鉄分を補給することもあります。(当院は静脈注射の鉄剤は取り扱っていないので、他院に紹介させていただきます。)
原因疾患の治療
貧血の背景に子宮筋腫や月経過多、胃潰瘍などの病気が隠れていることが多いので、原因検索や治療も並行して行う必要があります。

6. 日常生活でできる貧血予防
鉄分を多く含む食品を意識的に摂る
鉄分には、体に吸収されやすい「ヘム鉄」と、吸収されにくい「非ヘム鉄」があります。
ヘム鉄を多く含む食品
- 赤身の肉(牛肉、豚肉など)
- レバー
- カツオ、マグロなどの魚
- あさり、しじみなどの貝類
非ヘム鉄を多く含む食品
- ほうれん草、小松菜などの緑黄色野菜
- 大豆製品(納豆、豆腐など)
- ひじきなどの海藻類
非ヘム鉄は、ビタミンCやたんぱく質と一緒に摂ることで吸収率が高まります。例えば、ほうれん草のお浸しに鰹節をかけたり、食後に果物を食べたりするのが効果的です。
バランスの良い食事を心がける
鉄分だけでなく、赤血球の形成に必要なビタミンB12や葉酸、たんぱく質なども重要です。偏った食事ではなく、バランスよくさまざまな食材を摂るよう心がけましょう。
極端なダイエットは避ける
急激な体重減少を目指す極端なダイエットは、鉄分をはじめとする栄養素の不足を招きます。健康的な体重管理を意識することが大切です。
定期的な健康診断を受ける
貧血は自覚症状がないまま進行することもあります。年に一度は健康診断を受け、血液検査で自分の状態を把握することをお勧めいたします。
月経過多の場合は婦人科を受診
月経量が多い、月経期間が長い、レバー状の塊が多く出るなどの症状がある場合は、子宮筋腫などの可能性も考えられます。婦人科での診察も検討してみてください。
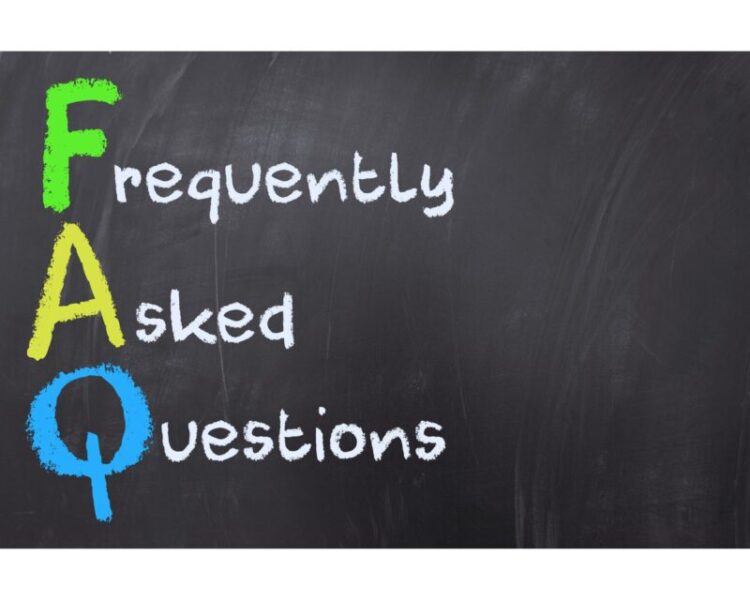
7. よくある質問(Q&A)
Q1: 貧血とは具体的にどのような状態ですか?
A: 貧血は、血液中の赤血球やヘモグロビンが正常より少なくなった状態です。赤血球には酸素を運ぶ役割があるため、貧血になると全身に十分な酸素が届かず、疲れやすさやめまいなどの症状が現れます。
Q2: 鉄分のサプリメントを飲めば治りますか?
A: 市販のサプリメントでも一定の効果は期待できますが、まずは医療機関での検査をお勧めいたします。貧血の原因によっては、別の病気が隠れている場合もあるためです。また、医療機関で処方される鉄剤の方が鉄分の含有量が多く、効果的な治療が期待できます。
Q3: 貧血は遺伝しますか?
A: 一般的な鉄欠乏性貧血は遺伝しませんが、一部の貧血(サラセミア、鎌状赤血球症など)は遺伝性のものもあります。日本人に多いのは鉄欠乏性貧血で、こちらは慢性出血による影響が大きいとされています。
Q4: 妊娠を希望していますが、貧血があります。どうすればよいですか?
A: 妊娠前から貧血を改善しておくことが推奨されます。妊娠中は鉄分の需要が大幅に増えるため、妊娠前の段階で十分な鉄分を蓄えておくことが理想的です。まずは内科や婦人科で相談されることをお勧めいたします。
Q5: 鉄剤を飲むと便が黒くなりましたが、大丈夫ですか?
A: 鉄剤の服用により便が黒くなることは、よく見られる現象で特に心配はいりません。これは鉄分が腸内で変化したためです。ただし、便が黒くなる原因には胃や腸からの出血もあるため、一度医師に相談してください。
Q6: どのくらいの期間で改善しますか?
A: 個人差はありますが、鉄剤を服用し始めて2〜4週間程度で自覚症状の改善を感じる方が多いです。ただし、体内の鉄分を十分に貯蔵するためには、半年程度継続的な治療が必要とされています。症状が改善しても、医師の指示に従って服用を続けることが大切です。
Q7: コーヒーやお茶を飲んではいけませんか?
A: コーヒーやお茶に含まれるタンニンは、鉄分の吸収を妨げる可能性があります。鉄剤を服用する際や、鉄分の多い食事を摂る際は、前後1時間程度は控えることが推奨されます。ただし、日常的に全く飲んではいけないというわけではありません。
Q8: 運動をしても大丈夫ですか?
A: 軽度の貧血であれば、適度な運動は問題ありません。ただし、ヘモグロビン値が著しく低い場合や、めまいや息切れが強い場合は、激しい運動は控えた方が良いでしょう。運動の内容については、主治医と相談しながら決めることをお勧めいたします。
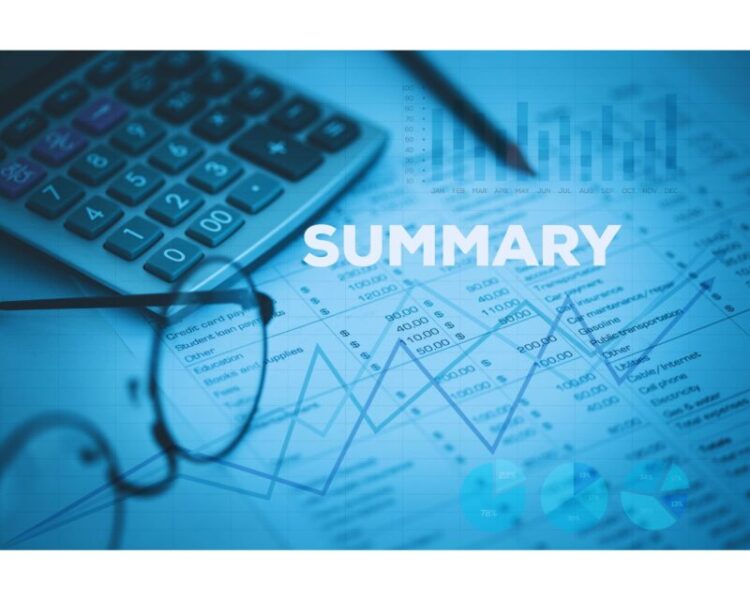
8. まとめ
女性の貧血は、月経や妊娠・出産、食生活など、さまざまな要因が関わっています。「よくあることだから」と軽く考えず、気になる症状がある場合は早めに医療機関を受診することが大切です。
貧血の多くは、適切な治療と生活習慣の改善により改善が期待できます。鉄分を意識した食事、バランスの良い栄養摂取、そして定期的な健康診断を行いましょう。
当クリニックでは、貧血に関する検査や治療も行っております。少しでも気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。一人ひとりの患者様に寄り添いながら、適切な診療を提供してまいります。
執筆者プロフィール

田邉弦
丹野内科・循環器・糖尿病内科 院長
- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医
- 日本循環器学会 循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会 認定医
- 日本内科学会 JMECCインストラクター
- 日本救急医学会 ICLSインストラクター
- 認知症サポート医
インタビュー記事はこちらからご覧ください。
