- 2025年3月27日
風邪が新型コロナと同じ5類感染症に?何が変わるの?そもそも風邪とは?
こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。徐々に暖かくなって本格的に花粉症がひどくなってきました。花粉症に関しては以前のブログ記事「今年は花粉の飛散量3倍!?効果的な花粉症対策、治療は?」をご覧ください。今回は一般内科疾患の代表である風邪についてのお話です。
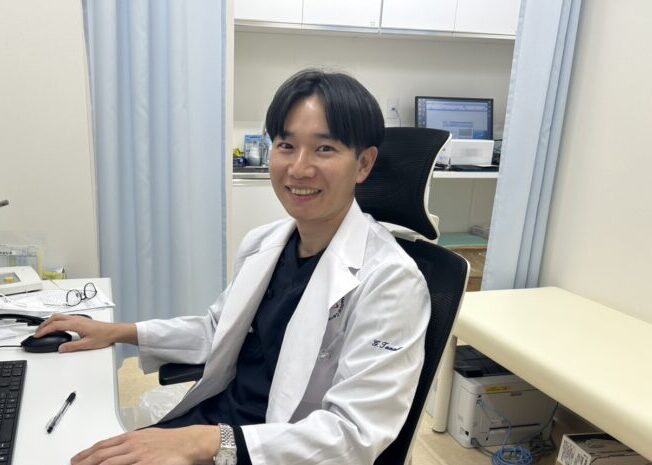
2025年4月から風邪が新型コロナウイルス感染症と同じ5類感染症に分類されることになりました。多くの方が「5類感染症って何?」「かかると出勤停止になるの?」と疑問をお持ちではないでしょうか。この記事では、制度の変更点と風邪について詳しく解説していきます。
目次

感染症法とは?
「感染症法」は正式には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」といいます。この法律は、私たち国民の健康を守るために、感染症の発生や蔓延を防ぐことを目的としています。
具体的には、「この病気は早く見つけて対応する必要がある」という感染症を、下記のように危険度に応じて分類しています.
- 1類感染症:エボラ出血熱などの重症度が極めて高い感染症
- 2類感染症:結核などの重症度が高い感染症
- 3類感染症:コレラなど、食中毒のように食品や水を介して広がる感染症
- 4類感染症:A型肝炎、狂犬病など人や動物の間で広がる感染症
- 5類感染症:危険度はさほど高くないが、発生状況を把握したい感染症(インフルエンザや新型コロナ)
このように分類することで、それぞれの感染症に応じた適切な対応ができるようになっています。また医師には、これらの感染症を診断した場合、保健所への届出が義務付けられています。感染症の発生状況を把握し、適切な対策を講じることで、地域の皆様の健康を守るためのものです。
2025年4月から風邪も5類感染症へ
2025年4月から急性呼吸器感染症(いわゆる風邪)もインフルエンザや新型コロナウイルス感染症と同様に5類感染症に分類されることになりました。
変更の背景
5類に分類されると診断した医療機関(指定された定点医療機関)が発生状況を国に報告することになります。新型コロナウイルスの世界的流行の教訓を生かし、今後未知のウイルスの流行が起こった場合にいち早くその動向を把握し、対応することを目的としているようです。
具体的な変更点
以上のような背景があり5類に変更されるということですが、患者さんの対応は今までも変わりなく、出席・出勤停止期間などに具体的な定めはなく、医療費負担も今まで通りとなっています。
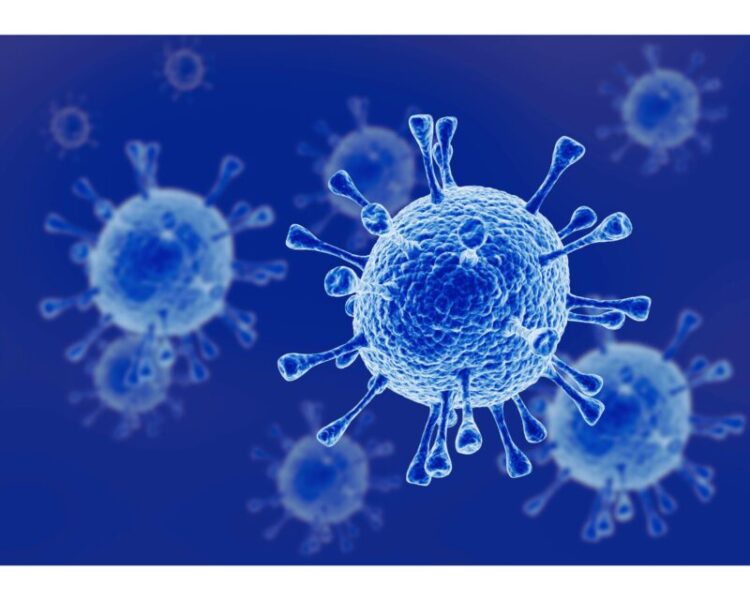
そもそも風邪とは?
次は風邪について解説します。風邪はよく聞く言葉だと思いますが、具体的によくわかっていない方も多いのではないでしょうか?
風邪の定義と原因
風邪は、様々なウイルスによって引き起こされる上気道(鼻、のどなど)感染症の総称です。原因ウイルスは200種類以上とも言われており、現在の医療レベルでは原因ウイルスを特定するのは困難です。
有名な原因ウイルスには、以下のようなものがあります。
- ライノウイルス
- コロナウイルス(新型コロナウイルス以外)
- RSウイルス
- アデノウイルス
- エンテロウイルス
特徴的な症状
1. 初期症状
- のどの痛み
- くしゃみ
- 鼻水
- 軽い倦怠感
2. 進行期の症状
- 咳
- 痰
- 発熱
- 頭痛
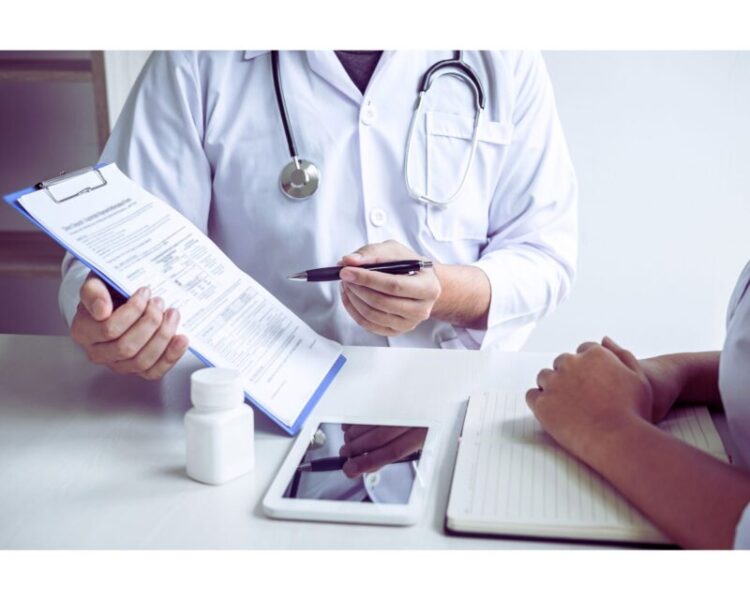
風邪の診断と治療
診断方法
1. 問診
- 症状の経過
- 周囲の感染状況
- 基礎疾患の有無
2. 身体診察
- のどの観察
- 聴診
- リンパ節の触診
基本的に風邪(ウイルス感染症)の場合は咳、鼻汁、咽頭痛の3つの症状が揃うことが多いとされています。問診・身体診察を行い、その他の細菌性疾患(肺炎や副鼻腔炎、溶連菌性扁桃炎)の可能性が低い時に風邪と診断します。
治療
基本的に風邪に抗生物質は必要ありません
その理由は、風邪はウイルスが原因だからです。抗生物質は細菌にのみ効果があり、ウイルスには全く効果がありません。抗ウイルス薬はインフルエンザや新型コロナウイルスに対しては開発されていますが、その他のほとんどのウイルスに抗ウイルス薬はありません。よって以下のような対症療法を行い自分の免疫力を整えることが重要になります。特に十分な休息、睡眠は軽視されがちですがとても重要です。
1. 対症療法
- 解熱鎮痛薬
- 咳止め
- 鼻づまり改善薬
- のど痛み緩和薬
2. 生活上の注意
- 十分な休息(睡眠)
- 水分補給(脱水を防ぐ)
- 適切な栄養摂取
それでは抗生物質を風邪に対して安易に内服するとどうなるでしょうか?不必要な抗生物質の使用は以下のような悪影響があります。
- 耐性菌の発生
- 腸内細菌叢の乱れ→下痢などの副作用
- アレルギー反応
耐性菌と言われてもピンとこないかもしれませんが、耐性菌とは「抗生物質が効かなくなった細菌」のことです。たとえば、風邪をひいて抗生物質を服用してしまうと、多くの細菌は死滅します。しかし、中には抗生物質の攻撃を効きづらい細菌がいます。この生き残った細菌は、抗生物質への「耐性」を持っているため、同じ薬を使っても効果がなくなってしまいます。さらに、この耐性菌が増殖すると、より多くの耐性菌が体内で広がることになります。抗生物質の不適切な使用が耐性菌の主要な原因と言われています。抗生物質の不適切な使用が続くと体内で耐性菌が誘導され本当に抗生物質が必要な状況で抗生物質が効かないということになりかねません。
ただし、初期は風邪と診断されてもその後細菌感染が合併し、抗生物質が必要となることがあります。以下のような場合細菌性感染症の合併が疑われ注意が必要です。
- 高熱(38度以上)が4日以上続く
- 膿性の痰が増える
- のどに膿がついている
- 中耳炎や副鼻腔炎のような症状がある
特に注意が必要な方
- 高齢の方
- 糖尿病などの基礎疾患がある方
- 免疫力が低下している方
抗生物質が必要かどうかは、以下の検査や所見を総合的に判断します。
- 全身状態
- 症状の経過
- 血液検査(白血球数、CRPなど)
- 聴診での肺の音、胸部レントゲンでの肺炎の有無
大切なのは抗生物質が必要かどうかを我々医師が適切に判断することです。心配な症状がある場合は、ご自身での判断はせず、当院を受診してください。当院では、患者さんの症状を丁寧に診察し、必要な場合にのみ抗生物質を処方する方針としています。

予防と対策
以上のように風邪はウイルスが原因で特効薬のような治療法はありませんので、予防が重要になります。
日常的な予防法
1. 基本的な感染対策
- こまめな手洗い
- マスクの適切な着用
- 十分な睡眠
- バランスの良い食事
2. 環境整備
- 適切な湿度管理
- 定期的な換気
- 清潔な環境維持
免疫力を高める生活習慣
- 規則正しい生活リズム
- ストレス管理
- 適度な運動
- 十分な休養
受診の目安
すぐに受診すべき症状
1. 重症化を示唆する症状
- 38度以上の高熱が続く
- 呼吸困難
- 強い倦怠感
- 食事や水分が摂れない
2. 注意が必要な方
- 高齢者
- 基礎疾患がある方
- 乳幼児
経過観察でよい場合
- 軽い症状のみ
- 全身状態が良好
- 水分・食事が摂れる
- 改善傾向がある
家族への感染予防
- 個室での療養
- マスクの着用
- 共用部分の消毒
- 十分な換気

まとめ
風邪が5類感染症への変更になりましたが、当クリニックの診療や患者様一人ひとりには特に変わりはありません。
当院では、以下のような対応を心がけています。
- 丁寧な問診と診察
- 必要に応じて抗原検査や採血などの検査
- 症状に応じた適切な治療
- 予防に関するアドバイス
- 必要時の迅速な対応
- 重症化予防のための早期介入
当院では37.5以上の発熱がある方は隔離対応をしております。個室が埋まっている場合はお待たせしてしまうこともあるため、事前予約をお勧めしています。ご予約は、お電話またはウェブサイトから受け付けております。ご来院お待ちしております。
