- 2025年4月3日
発熱と頭痛の原因は?風邪や重病の見分け方と対処法
こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。新年度となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?今回は、誰しも一度は経験したことがあるであろう発熱と頭痛に関するお話です。

発熱と頭痛は多くの方が経験する症状です。単なる風邪かもしれませんが、時には重大な病気の兆候である可能性もあります。この記事では、発熱と頭痛が同時に起こる原因や、風邪とより深刻な疾患の見分け方、適切な対処法について詳しく解説します。
目次
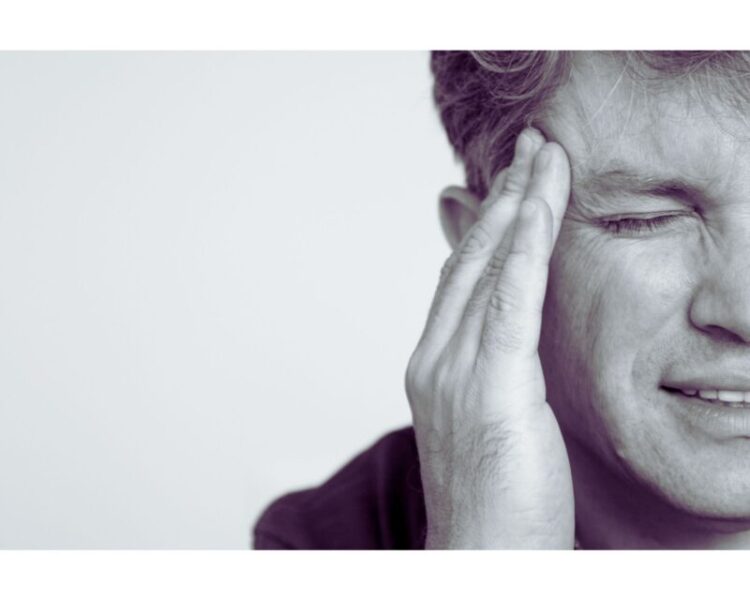
発熱と頭痛が同時に現れるよくある原因
発熱と頭痛が同時に現れるケースは非常に多く、その原因もさまざまです。風邪やインフルエンザなどの一般的な感染症から、より重篤な疾患まで幅広く考えられます。
風邪(急性上気道炎・咽頭炎)
風邪は最も一般的な原因の一つです。通常、軽度から中程度の発熱(37.5℃〜38.5℃程度)と頭痛を伴います。風邪の場合、これらの症状に加えて、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、咳などの上気道症状を伴うことが特徴です。
風邪の多くはウイルス感染によるもので、特異的な治療はありません。通常3〜7日程度で自然に回復します。十分な休息と水分摂取が重要です。
風邪に関しては以前のブログ「風邪が新型コロナと同じ5類感染症に?何が変わるの?そもそも風邪とは?」に書いておりますので、是非ご覧ください。
インフルエンザ
インフルエンザは風邪より症状が重く、突然の高熱(38.5℃以上)と強い頭痛が特徴です。全身の倦怠感や筋肉痛も伴うことが多く、発症が急激である点が風邪との大きな違いです。ただワクチン接種の有無でも症状は異なり、基本的に抗原検査を行わないと正確な判断はできません。
インフルエンザは季節性があり、主に冬季に流行します。発症から48時間以内に抗ウイルス薬(タミフル、イナビル、ゾフルーザなど)の投与が効果的です。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
COVID-19の症状は個人差が大きいですが、発熱と頭痛に加えて、咳、息切れ、味覚・嗅覚障害、全身の倦怠感などが現れることがあります。最近の変異株では、上気道症状がより顕著になっている傾向があります。
感染が疑われる場合は、自己判断せずご相談ください。

注意が必要な原因
髄膜炎・脳炎
髄膜炎・脳炎は脳や脊髄を覆う髄膜の炎症であり、高熱と激しい頭痛に加え、首の硬直(首を前に曲げると痛みがある)、光過敏、吐き気・嘔吐などの症状があります。悪化すると意識障害、けいれん、言語障害、行動の変化などの神経症状を伴うことがあります。ウイルス性と細菌性とありますが、細菌性髄膜炎は進行が速く、早急な治療が必要です。
肺炎
肺炎はその名の通り、肺の感染症で、発熱と頭痛に加えて、激しい咳・痰、呼吸困難や息切れ、胸痛、酸素飽和度の低下などがあります。特に高齢者や乳幼児、基礎疾患のある方は重症化しやすいため注意が必要です。ウイルス性の可能性もありますが、細菌性のことが多く抗生物質による治療が必要です。
尿路感染症・腎盂腎炎
尿路感染症は、膀胱や腎臓など尿路の感染症です。発熱と頭痛に加えて、頻尿や排尿時の痛み、下腹部や腰背部の痛み、尿が濁るなどの症状があります。特に女性は男性よりも尿路感染症にかかりやすく、腎盂腎炎などの重篤な合併症に進展するリスクがあるため、早期の治療が重要です。抗生物質による治療が必要です。
副鼻腔炎
副鼻腔炎(蓄膿症)は、副鼻腔の感染や炎症によって起こります。原因はウイルス性のことが多いですが、細菌が2次感染して起こることもあります。発熱と共に、額や頬、目の周りの痛み、鼻づまり、黄緑色の鼻水などの症状が特徴です。

風邪と重病の見分け方
発熱と頭痛があるとき、それが単なる風邪なのか、より深刻な病気のサインなのかを見分けることは非常に重要です。以下のポイントに注目しましょう。
警告サイン:すぐに医療機関を受診すべき症状
以下の症状がある場合は、重篤な疾患の可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください
- 39℃以上の高熱が続く
- 激しい頭痛、特に今までに経験したことのないような痛み
- 首の硬直(首を前に曲げると痛みがある)
- 意識障害や混乱
- けいれん
- 光や音に対する過敏反応
- 呼吸苦
- 持続する嘔吐
年齢層別の注意点
小児の場合
小児は体温調節機能が未熟なため、成人よりも発熱しやすい傾向があります。一方で、重篤な感染症にかかるリスクも高いため、以下の場合は特に注意が必要です。
- 3ヶ月未満の乳児で38℃以上の発熱
- 元気がなく、ぐったりしている
- 水分摂取が極端に減少している
- 泣き方が普段と異なる、または泣き止まない
- 呼吸が速い、または呼吸に問題がある
高齢者の場合
高齢者は免疫機能の低下により、重篤な感染症のリスクが高まります。特に基礎疾患のある方はさらに要注意です。また、症状が典型的でない場合もあり、次のような変化に注意が必要です。
- 普段と異なる混乱や意識レベルの変化
- 転倒
- 食欲低下
- 日常生活動作の急激な低下
基礎疾患がある場合
糖尿病、心疾患、慢性呼吸器疾患、免疫不全などの基礎疾患がある方は、感染症により症状が重症化するリスクが高いため、早めの受診をお勧めします。

発熱と頭痛への対処法
自宅でできるケア
風邪や軽度の感染症による発熱と頭痛には、以下の対処法が効果的です。
1. 適切な休息
十分な睡眠と休息は、体の回復力を高め、免疫機能を強化します。発熱時は特に、体力を温存するために安静にしましょう。
2. 水分補給
発熱により体内の水分が失われやすくなるため、こまめな水分補給が重要です。水、お茶、スープなどを積極的に摂りましょう。特に発汗や嘔吐がある場合は、電解質バランスも考慮したスポーツドリンク(スポーツドリンクは糖分を多く含むので、肥満や糖尿病の方は注意が必要)も有効です。
3. 解熱鎮痛薬の適切な使用
市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)は、発熱や頭痛の一時的な緩和に役立ちます。ただし、用法・用量を守り、長期間の連続使用は避けてください。特に以下の点に注意が必要です。
- 複数の解熱鎮痛薬を同時に服用しない
- 持病がある場合や他の薬を服用中の場合は、事前に医師に相談する
4. 冷却法
額や首筋に冷たいタオルを当てると、頭痛や熱感を和らげる効果があります。ただし、強い悪寒がある場合は避けましょう。
医療機関を受診すべきタイミング
以下の場合は、自己判断せず医療機関を受診してください。
- 38.0℃以上の高熱が2日以上続く
- 解熱剤を使用しても熱が下がらない
- 頭痛が徐々に悪化する
- 発疹が現れる
- 呼吸が困難になる
- 嘔吐が続く
- 脱水症状がある(口の渇き、尿量の減少、めまいなど)
- 首が硬くなる
- 意識がもうろうとする

発熱と頭痛の予防法
日常生活での対策
1. 手洗いとマスク
感染症予防の基本は手洗いとマスクです。特に公共の場所から帰宅後や食事前には、石鹸で30秒以上かけて丁寧に手を洗いましょう。また、流行時期には適切なマスクの着用も効果的です。
2. バランスの良い食事と適度な運動
免疫力を高めるためには、ビタミンやミネラルを豊富に含むバランスの良い食事と、適度な運動が重要です。特にビタミンC、ビタミンD、亜鉛などの栄養素は免疫機能の維持に役立ちます。
3. 十分な睡眠
質の良い睡眠は免疫力を高め、感染症への抵抗力を強化します。成人の場合、7〜8時間の睡眠が理想的です。
4. ストレス管理
慢性的なストレスは免疫機能を低下させるため、適切なストレス管理が重要です。瞑想、深呼吸、趣味の時間など、自分に合ったリラックス法を見つけましょう。
5. ワクチン接種
インフルエンザや肺炎球菌などのワクチン接種も、重要な予防策の一つです。特に高齢者や基礎疾患のある方、小さなお子さんがいるご家庭ではワクチン接種をお勧めします。
RSウイルスワクチンについては以前のブログ「高齢者に対するRSウイルスワクチンの有効性。RSウイルスは子供の感染症!?」をご覧ください。
まとめ
発熱と頭痛は多くの疾患に共通する症状ですが、その原因や重症度はさまざまです。軽度の風邪から生命を脅かす感染症まで、幅広い可能性があります。
多くの場合、十分な休息、水分補給、適切な解熱鎮痛薬の使用などの自己ケアで改善しますが、高熱の持続や激しい頭痛、首の硬直などの警告サインがある場合は、迅速に医療機関を受診することが重要です。
特に小さなお子さんや高齢者、基礎疾患をお持ちの方は、症状が重症化するリスクが高いため、早めの受診をお勧めします。
予防においては、手洗い・マスク着用などの基本的な感染対策と、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理などの健康的な生活習慣が重要です。
当院での診療について
当院では、発熱外来を終日設置しており、発熱や頭痛をはじめとする様々な症状に対応しております。お気軽に当院までお問い合わせください。丁寧な診察と適切な治療を心がけております。
