- 2025年11月11日
肥満症とは?糖尿病専門医が解説する原因・診断基準・治療法【松戸市の内科クリニック】

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉優希です。今回は最近話題の肥満症についてのお話です。
「最近、体重が増えて気になる」「健康診断でメタボと言われた」そんなお悩みはありませんか?肥満症は、単なる「太っている状態」とは異なり、医学的な治療が必要な疾患です。日本では成人の約3人に1人が肥満傾向にあり、糖尿病や高血圧などの生活習慣病と深く関係しています。
この記事では、糖尿病専門医の立場から、肥満症の基礎知識から具体的な対策まで、わかりやすく解説いたします。ご自身やご家族の健康管理にお役立てください。
目次

1. 肥満症とは何か?基礎知識を理解しよう
肥満症の医学的定義
肥満症とは、「脂肪組織が過剰に蓄積した状態で、健康障害を伴うか、その リスクが高い場合」を指す疾患です。
日本肥満学会によれば、BMI(体格指数)が25以上で、かつ以下のいずれかに該当する場合に肥満症と診断されます。
- すでに肥満に関連する健康障害がある
- 内臓脂肪が過剰に蓄積している
つまり、単に体重が重いだけでなく、健康に悪影響を及ぼしている、または及ぼす可能性が高い状態が肥満症なのです。
BMI(体格指数)とは
BMIは、体重と身長から算出される肥満度を示す指標です。
計算式:BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)
例えば、身長160cm、体重65kgの方の場合: 65 ÷ 1.6 ÷ 1.6 = 25.4
日本肥満学会では、BMI25以上を「肥満」と分類しています。
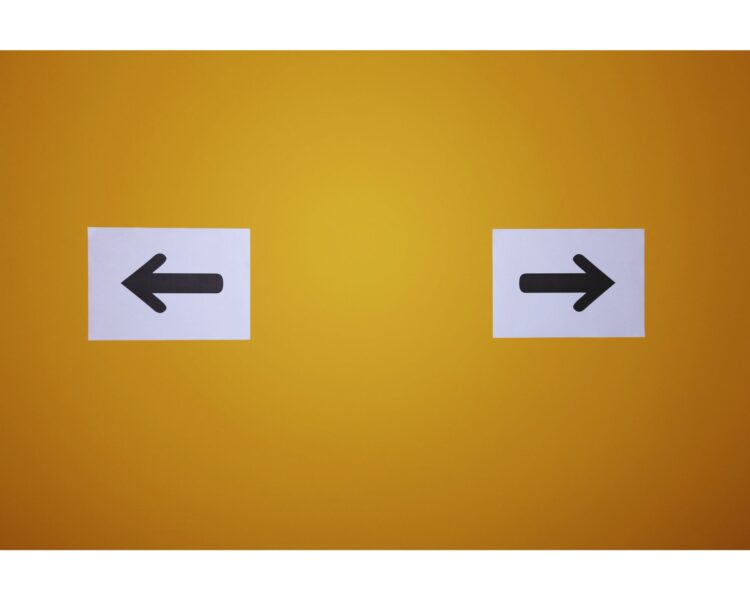
2. 肥満と肥満症の違い
ここが重要なポイントです。「肥満」と「肥満症」は似ているようで異なります。
肥満
BMIが25以上の状態を指します。これ自体は病気ではなく、身体の状態を示す指標です。健康障害がなければ、必ずしも治療が必要とは限りません。
肥満症
肥満に加えて、以下のような健康障害を伴う、または伴うリスクが高い状態です。
- 2型糖尿病
- 脂質異常症(高脂血症)
- 高血圧
- 高尿酸血症・痛風
- 冠動脈疾患(心筋梗塞、狭心症)
- 脳梗塞
- 脂肪肝
- 睡眠時無呼吸症候群
- 変形性関節症
- 月経異常、不妊
これらの健康障害がある場合、積極的な治療が推奨されます。
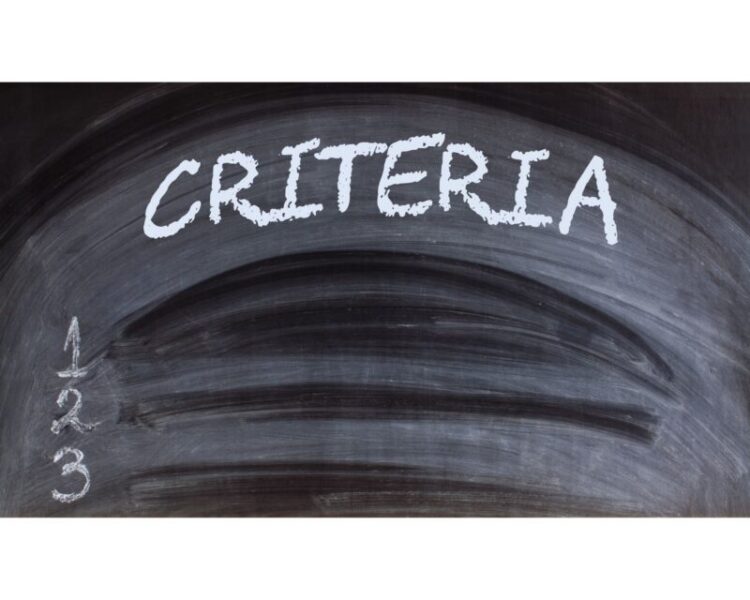
3. 肥満症の診断基準
BMIによる分類
日本肥満学会の基準では以下のように分類されています。
- BMI 18.5未満:低体重
- BMI 18.5〜25未満:普通体重
- BMI 25〜30未満:肥満(1度)
- BMI 30〜35未満:肥満(2度)
- BMI 35〜40未満:肥満(3度)
- BMI 40以上:肥満(4度)
内臓脂肪型肥満の判定
内臓脂肪の蓄積は、CTスキャンやウエスト周囲径で評価されます。
ウエスト周囲径の基準:
- 男性:85cm以上
- 女性:90cm以上
この基準を超えると、内臓脂肪型肥満の可能性が高いと判断されます。(この基準はメタボリックシンドロームの基準としてなじみ深いと思います。)
内臓脂肪が蓄積すると、メタボリックシンドローム(代謝症候群)のリスクが高まり、糖尿病や心血管疾患の発症リスクが増加します。

4. 肥満症が引き起こす健康リスク
糖尿病との深い関係
私が専門とする糖尿病領域では、肥満症は最も重要なリスク因子の一つです。
内臓脂肪が蓄積すると、インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」という状態が生じます。その結果、血糖値が上昇し、2型糖尿病を発症しやすくなります。
実際、2型糖尿病患者さんの約6〜7割が肥満を合併しているというデータがあります。
心血管疾患のリスク
肥満症は、心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化性疾患のリスクを高めます。
具体的には
- 高血圧:血管に負担がかかり、脳卒中や心臓病のリスクが上昇
- 脂質異常症:LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の増加
- 血栓:血液が固まりやすくなり、血管が詰まるリスクが増加
その他の健康リスク
- 睡眠時無呼吸症候群:首周りの脂肪で気道が狭くなり、睡眠中に呼吸が止まる
- 変形性膝関節症:膝への負担増加で痛みや変形が生じる
- 脂肪肝:肝臓に脂肪が蓄積し、肝硬変や肝がんへ進行する可能性
- 不妊・月経異常:ホルモンバランスの乱れ
- がんリスク:大腸がん、乳がん、子宮体がんなどのリスク増加
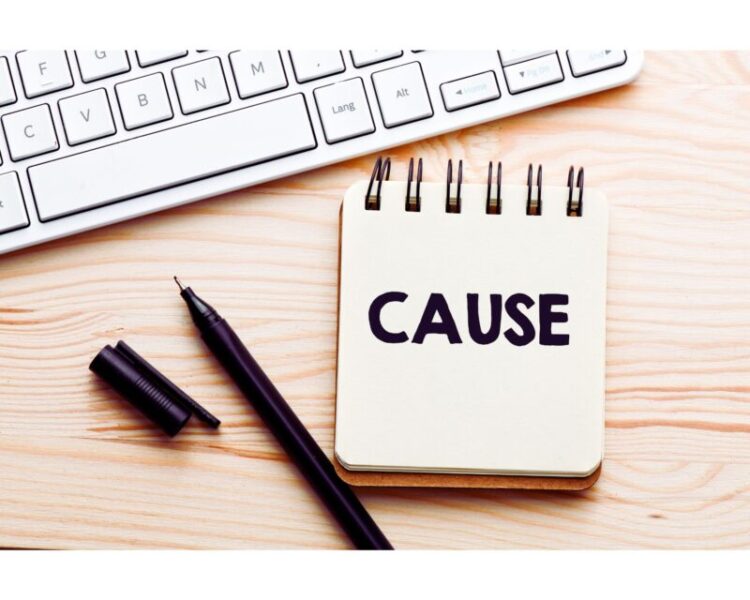
5. 肥満症の原因
エネルギーバランスの乱れ
肥満症の基本的な原因は、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回る状態が続くことです。
よくある生活パターン
- 夜遅い時間の食事
- 早食い、ながら食い
- 間食や甘い飲料の過剰摂取
- 運動不足、デスクワーク中心の生活
- ストレスによる過食
遺伝的要因
肥満には遺伝的な要素もあります。両親が肥満の場合、子どもが肥満になる確率は約70〜80%とも言われています。
ただし、遺伝的要因があっても、生活習慣の改善で肥満を予防・改善することは十分可能です。
加齢による代謝の低下
年齢を重ねると、基礎代謝が低下し、若い頃と同じ食事量でも太りやすくなります。
40代以降は特に、食事内容や運動習慣の見直しが重要になります。
疾患や薬剤による影響
一部の疾患(甲状腺機能低下症、クッシング症候群など)や、薬剤(ステロイド、一部の精神科薬など)が肥満の原因となることもあります。
急激な体重増加がある場合は、医療機関でご相談されることをお勧めします。

6. 肥満症の治療と予防法
食事療法の基本
肥満症治療の基本は、適切なカロリー制限です。
推奨される目標
- 3〜6ヶ月で現体重の3〜5%減少
- 急激な減量は避け、月に1〜2kg程度のペースが理想的
具体的な食事のポイント
- 主食の量を調整する
- ご飯は茶碗1杯(150g程度)を目安に
- 麺類は1人前の8割程度に
- 野菜を先に食べる(ベジファースト)
- 食物繊維が血糖値の急上昇を防ぐ
- 満腹感を得やすい
- たんぱく質をしっかり摂る
- 魚、鶏肉、大豆製品など
- 筋肉量の維持に重要
- 間食・甘い飲料を控える
- ジュース、缶コーヒーは高カロリーなので控える
- 飲み物は水、お茶、ブラックコーヒーを中心に
- ゆっくりよく噛んで食べる
- 一口30回を目標に
- 食事時間は20分以上かけて

運動療法の実践
食事療法と並行して、運動習慣をつけることが推奨されます。
有酸素運動
- ウォーキング:1日30分以上、週5日
- 水泳、サイクリングなども効果的
- 「少し息が上がる程度」の運動強度が目安
日常生活での工夫
- エレベーターではなく階段を使う
- 一駅手前で降りて歩く
- 家事を積極的に行う
- 立って作業する時間を増やす
行動療法
生活習慣を見直し、太りにくい行動パターンを身につけることも重要です。
具体的な方法
- 体重や食事内容を記録する(レコーディング)
- 食事の時間を決め、規則正しく食べる
- ストレス解消法を見つける(運動、趣味など)
- 十分な睡眠をとる(7〜8時間が推奨)
薬物療法
生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合、医師の判断で薬物療法が検討されることがあります。
日本で承認されている抗肥満薬もありますが、あくまで食事・運動療法の補助的な位置づけです。使用には医師の診察が必要で、定期的な経過観察が求められます。
当院での肥満自費診療に関しては「【松戸市】肥満症に対するマンジャロ治療|医学的根拠に基づいた自費診療」をご覧ください。
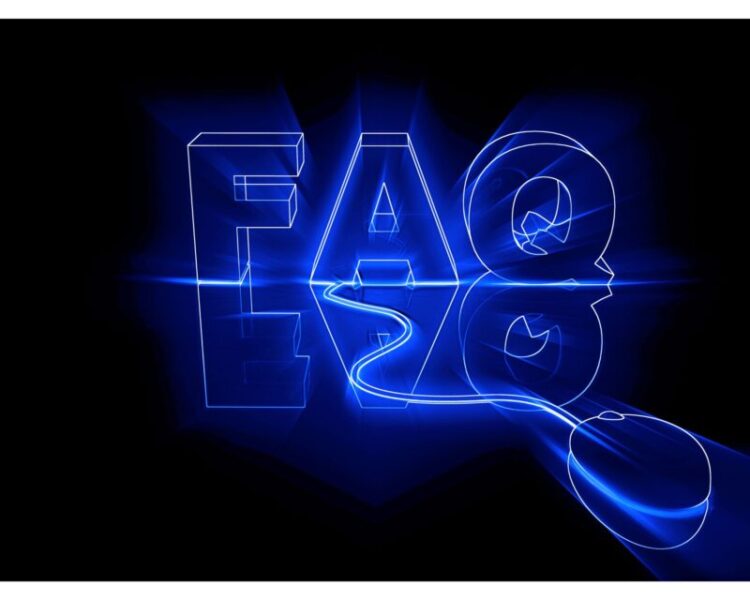
7. よくある質問(Q&A)
Q1. BMIは正常範囲なのに、お腹だけ出ています。これも肥満症ですか?
A. BMIが正常範囲でも、内臓脂肪が過剰に蓄積している「隠れ肥満」の可能性があります。ウエスト周囲径が基準値を超えている場合、内臓脂肪型肥満と診断されることがあります。健康診断で腹囲測定やCT検査などを受けることをお勧めします。
Q2. 肥満症の治療は、どのくらいの期間が必要ですか?
A. 肥満症の治療は、短期間で終わるものではなく、継続的な生活習慣の改善が必要です。まずは3〜6ヶ月で体重の3〜5%減少を目標にし、その後も適正体重を維持していくことが大切です。焦らず、無理のないペースで取り組むことが成功のカギです。
Q3. 糖質制限ダイエットは効果がありますか?
A. 糖質制限には一定の減量効果が報告されていますが、極端な制限は健康リスクも伴います。特に糖尿病の方は、低血糖などのリスクがあるため、必ず医師に相談してから始めてください。バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせることが、長期的には最も効果的です。
糖質制限に関しては以前のブログ「糖尿病の食事療法について。糖尿病に糖質制限は有効なの?」をご覧ください。
Q4. 家族に肥満が多いので、自分も諦めています…
A. 確かに遺伝的要因はありますが、生活習慣の改善で十分に予防・改善が可能です。家族全体で健康的な食生活や運動習慣を取り入れることで、お互いに励まし合いながら続けられるというメリットもあります。諦めずに、できることから始めてみましょう。
Q5. 一度痩せてもリバウンドしてしまいます。どうすればいいですか?
A. リバウンドは、急激な減量や無理な食事制限が原因であることが多いです。月に1〜2kg程度のゆるやかな減量を目指し、生活習慣全体を見直すことが重要です。また、目標体重に達した後も、維持するための習慣を続けることが大切です。

8. まとめ
肥満症は、単なる見た目の問題ではなく、糖尿病や心血管疾患など、様々な健康リスクを伴う疾患です。
この記事の重要ポイント
- 肥満症は「BMI25以上+健康障害または内臓脂肪蓄積」で診断される
- 糖尿病、高血圧、脂質異常症などの合併症リスクが高い
- 治療の基本は「食事療法」と「運動療法」
- 3〜6ヶ月で体重の3〜5%減少を目標に
- 急激な減量ではなく、継続可能な生活習慣の改善が重要
肥満症の改善は、決して一人で抱え込む必要はありません。当院では、一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立て、継続的なサポートを行っています。「最近体重が増えた」「健康診断で指摘された」「家族に肥満症の人がいる」など、少しでも気になることがあれば、当院にご相談ください。早期に対策を始めることで、将来の重大な疾患を予防できる可能性が高まります。
参考文献・引用元
執筆者プロフィール

丹野内科・循環器・糖尿病内科 副院長 田邉 優希
- 日本糖尿病学会 糖尿病専門医
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本医師会 認定産業医
