- 2025年11月20日
【内科医が解説】FODMAP食とは?お腹の不調を改善する食事療法の基礎知識

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉優希です。今回は先日の腸活のブログとも関わってくるお腹に良い食事療法の話です。
「食後にお腹が張る」「下痢と便秘を繰り返す」「特定の食べ物を食べるとお腹が痛くなる」このような症状にお悩みではありませんか?検査をしても異常が見つからないのに、お腹の不調が続く場合、過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。実は、日本人の約10〜15%がこの症状を抱えていると言われています。
そんな方々の症状改善に効果が期待されているのが「FODMAP食(低FODMAP食事療法)」です。オーストラリアの研究者によって開発されたこの食事療法は、国際的にも注目を集めており、過敏性腸症候群の症状緩和に有効とされています。
内科専門医として、日々の診療の中で「何を食べればいいのか分からない」「お腹のことを気にして外食ができない」といったご相談を多くいただきます。この記事では、FODMAP食の基礎知識から実践方法まで、医学的根拠に基づいて分かりやすく解説いたします。
目次
- FODMAP食とは?基礎知識を理解しよう
- どんな症状に効果が期待できるのか
- FODMAPを多く含む食品・少ない食品
- 低FODMAP食事療法の実践方法
- FODMAP食に関するよくある質問(Q&A)
- まとめ:医師の指導のもとで適切に実践を
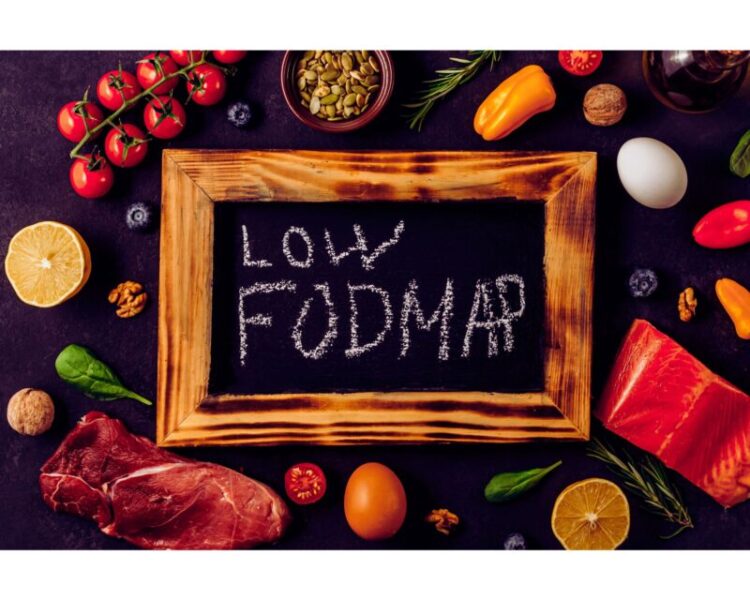
FODMAP食とは?基礎知識を理解しよう
FODMAPの意味
FODMAPとは、以下の英語の頭文字を取った言葉です。
- Fermentable(発酵性の)
- Oligosaccharides(オリゴ糖)
- Disaccharides(二糖類)
- Monosaccharides(単糖類)
- And
- Polyols(ポリオール:糖アルコール)
これらは、小腸で吸収されにくい特定の糖質の総称です。「発酵性の糖質」とも呼ばれ、腸内で発酵しやすい性質を持っています。
FODMAPが症状を引き起こすメカニズム
FODMAPを多く含む食品を摂取すると、腸の中で以下のような現象が起こります。
小腸での吸収が不十分:FODMAPは分子が小さく、小腸で完全に吸収されないまま大腸に到達します。
浸透圧の上昇:吸収されなかった糖質が腸管内に水分を引き込み、腸内の水分量が増加します。これが下痢の原因となることがあります。
腸内細菌による急速な発酵:大腸に到達したFODMAPは、腸内細菌によって急速に発酵され、ガスを大量に産生します。このガスが腹部膨満感やお腹の張り、痛みの原因となります。
健康な方であれば、これらの現象はあまり気にならないかもしれません。しかし、過敏性腸症候群など腸が敏感な方の場合、少量のFODMAPでも強い症状を引き起こすことがあるのです。
低FODMAP食事療法とは
低FODMAP食事療法は、FODMAPを多く含む食品を一時的に制限し、症状の改善を図る食事療法です。ただし、永続的にFODMAPを制限し続けるのではなく、段階的に再導入して、自分に合った食生活を見つけることが目的です。
この食事療法は、単なる食事制限ではありません。症状と食べ物の関係を理解し、長期的な生活の質(QOL)の向上を目指すアプローチなのです。
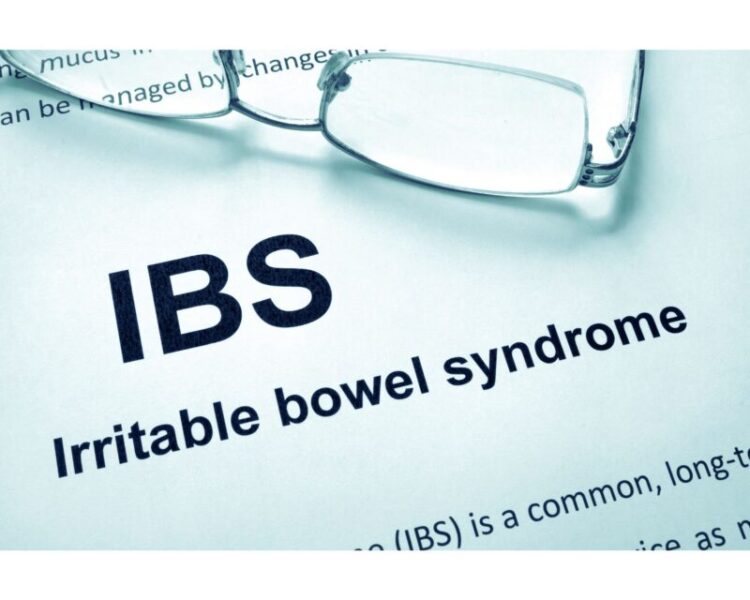
どんな症状に効果が期待できるのか
過敏性腸症候群(IBS)との関係
低FODMAP食事療法は、特に過敏性腸症候群の方に効果が期待されています。
過敏性腸症候群は、検査では異常が見つからないにもかかわらず、慢性的な腹痛や便通異常が続く疾患です。ストレスや食事、腸の動きの異常など、複数の要因が関係していると考えられています。
国際的な研究では、過敏性腸症候群の患者さんの約70〜75%が低FODMAP食事療法によって症状の改善を実感したという報告があります。
改善が期待できる具体的な症状
以下のような症状がある方は、低FODMAP食事療法が有効な可能性があります。
消化器症状
- 食後の腹部膨満感(お腹が張る感じ)
- ガスが溜まりやすい
- 腹痛や腹部の不快感
- 下痢と便秘の繰り返し
- 頻繁な腹鳴(お腹がゴロゴロ鳴る)
生活への影響
たとえば、「会議の前に必ずお腹が痛くなる」「電車に乗るとトイレが心配で不安になる」「外食を楽しめない」といった日常生活への支障が軽減される可能性があります。
効果が期待できない場合
すべての消化器症状に効果があるわけではありません。以下のような場合は、他の原因が考えられますので、必ず医療機関を受診してください。
- 急激な体重減少
- 血便が出る
- 激しい腹痛
- 発熱を伴う症状
- 夜間に症状で目が覚める
これらの症状がある場合は、炎症性腸疾患 (例えば潰瘍性大腸炎) など他の疾患の可能性がありますので、低FODMAP食を試す前に、まず適切な診断を受けることが重要です。

FODMAPを多く含む食品・少ない食品
高FODMAP食品(制限が推奨される食品)
低FODMAP食事療法の実践期間中は、以下の食品を控えることが推奨されます。
穀類・パン類
- 小麦を多く使った製品(パン、パスタ、うどん)
- ライ麦パン
- 一部のシリアル
野菜類
- 玉ねぎ、ニンニク
- アスパラガス、カリフラワー
- キャベツ、ブロッコリーの茎部分
- きのこ類
果物類
- リンゴ、梨
- スイカ、桃
- マンゴー、さくらんぼ
- ドライフルーツ全般
乳製品
- 牛乳、ヨーグルト(通常のもの)
- アイスクリーム
- カッテージチーズ、リコッタチーズ
豆類・ナッツ類
- 大豆、インゲン豆
- ひよこ豆、レンズ豆
- カシューナッツ、ピスタチオ
調味料・甘味料
- ハチミツ、アガベシロップ
- 果糖ぶどう糖液糖を含む製品
- 人工甘味料(ソルビトール、マンニトール、キシリトールなど)
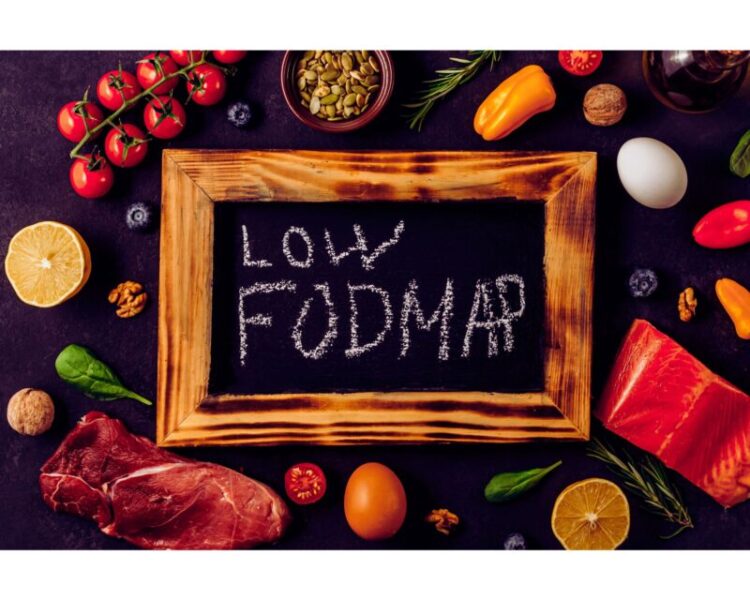
低FODMAP食品(摂取可能な食品)
以下の食品は、低FODMAP食事療法中でも安心して召し上がれます。
穀類・パン類
- 米、米粉製品
- グルテンフリーのパンや麺
- オートミール(少量)
- そば、春雨
野菜類
- ほうれん草、レタス
- にんじん、ズッキーニ
- トマト、きゅうり
- なす、ピーマン
- じゃがいも、かぼちゃ
果物類
- バナナ(熟したもの)
- オレンジ、みかん
- ぶどう、キウイフルーツ
- いちご、ブルーベリー
タンパク質源
- 肉類全般(牛肉、豚肉、鶏肉)
- 魚介類全般
- 卵
- 豆腐(硬めのもの)
乳製品
- ラクトースフリー牛乳
- ハードチーズ(チェダー、パルメザンなど)
- アーモンドミルク、豆乳(少量)
調味料・油脂類
- 醤油、味噌(少量)
- 砂糖、メープルシロップ(少量)
- オリーブオイル、ごま油
- 塩、コショウ、酢

低FODMAP食事療法の実践方法
3つのステップで進める
低FODMAP食事療法は、以下の3段階で進めることが推奨されています。
ステップ1:制限期(2〜6週間)
最初の段階では、高FODMAP食品を厳格に制限します。
- 期間:通常2〜6週間程度
- 目的:症状が改善するかを確認する
- 方法:高FODMAP食品を可能な限り避け、低FODMAP食品を中心に食事を組み立てる
この期間は、自分の症状とFODMAPの関係を確認する重要な時期です。食事日記をつけて、食べたものと症状の変化を記録することをおすすめします。
ステップ2:再導入期(6〜8週間)
症状が改善したら、制限していた食品を少しずつ、系統的に再導入していきます。
- 各食品グループを3日間ずつ試す
- 少量から始めて徐々に量を増やす
- 症状が出た場合は、その食品を記録して次のグループに移る
たとえば、「玉ねぎを少量(スライス2〜3枚)から試し、症状が出なければ中量、多量と増やしていく」という具合です。
ステップ3:維持期(継続)
再導入期を経て、自分に合った食品と量が分かったら、その知識をもとに長期的な食生活を確立します。
- 症状を引き起こさない食品は通常通り摂取
- 症状を引き起こす食品は必要に応じて制限
- 定期的に体調を確認しながら調整

実践時の具体的なポイント
食事の組み立て方
朝食の例:
- ご飯またはグルテンフリーパン
- 卵料理(目玉焼き、オムレツなど)
- ほうれん草やトマトのソテー
- バナナ
昼食の例:
- 鶏肉のグリル
- サラダ(レタス、きゅうり、にんじん)
- 米またはじゃがいも
- オレンジ
夕食の例:
- 焼き魚またはステーキ
- 煮物(にんじん、大根など)
- ご飯
- 味噌汁(豆腐入り)
外食時の工夫
- 和食レストランを選ぶ(魚や肉の定食など)
- 調味料やソースは別添えにしてもらう
- ニンニクや玉ねぎを使わないようリクエストする
- 事前に低FODMAP対応のメニューがあるか確認する
栄養バランスへの配慮
低FODMAP食事療法を実践する際は、栄養バランスにも注意が必要です。
不足しやすい栄養素
- 食物繊維:低FODMAP野菜や果物で補う
- カルシウム:ハードチーズやラクトースフリー製品を活用
- 炭水化物:米、じゃがいも、グルテンフリー製品で確保
特に長期間実践する場合は、栄養士や医師と相談しながら進めることをおすすめします。

FODMAP食に関するよくある質問(Q&A)
Q1: 低FODMAP食事療法は自己判断で始めても良いですか?
A: 必ず医師の診断を受けてから始めることをおすすめします。お腹の症状には様々な原因があり、中には重大な疾患が隠れている場合もあります。まずは適切な検査を受け、過敏性腸症候群などの診断を受けた上で、医師や管理栄養士の指導のもとで実践してください。
Q2: どのくらいの期間続ければ効果が分かりますか?
A: 個人差がありますが、制限期を2〜4週間続けることで、多くの方が症状の変化を感じられます。2週間経過しても全く変化がない場合は、他の原因が考えられますので、医師に相談してください。また、症状が改善したからといって、制限を続けることが目的ではありません。必ず再導入期に進み、自分に合った食生活を見つけることが大切です。
Q3: 永久に高FODMAP食品を食べられないのですか?
A: いいえ、そうではありません。低FODMAP食事療法の目的は、永久的な食事制限ではなく、自分にとって問題のある食品を見極めることです。再導入期を経て、多くの方が一部の高FODMAP食品を適量であれば問題なく摂取できることが分かります。完全な制限が必要なのは、制限期の数週間だけです。
Q4: 外食や旅行の時はどうすればいいですか?
A: 事前の準備と工夫で対応できます。外食では和食レストランを選ぶ、調味料を控えめにしてもらう、可能であれば食材について確認するなどの方法があります。完璧を目指す必要はなく、できる範囲で対応することが長続きのコツです。
Q5: 低FODMAP食事療法中に避けるべき調味料はありますか?
A: ニンニクや玉ねぎを多く使った調味料、ハチミツ、一部の人工甘味料は制限期には避けることが推奨されます。代わりに、ニンニクの風味を出したい場合はガーリックオイル(ニンニクを取り除いたもの)、玉ねぎの代わりに長ネギの緑色部分を使うなどの工夫ができます。基本的な調味料である醤油、味噌、塩、コショウ、酢などは問題なく使用できます。
Q6: 子どもや高齢者でも実践できますか?
A: 可能ですが、より慎重な対応が必要です。成長期の子どもや高齢者では、栄養バランスの維持が特に重要になります。必ず医師や管理栄養士の指導のもとで実践し、定期的に栄養状態をチェックすることをおすすめします。また、高齢者の場合は、食事の準備や記録が負担にならないよう、ご家族のサポートがあるとより安心です。

まとめ:医師の指導のもとで適切に実践を
低FODMAP食事療法は、過敏性腸症候群などのお腹の症状改善に効果が期待できる科学的根拠のある食事療法です。しかし、自己判断で始めるのではなく、適切な医療機関での診断と指導のもとで実践することが重要です。
低FODMAP食事療法の重要ポイント
- 必ず医師の診断を受けてから開始する
- 3つのステップ(制限期・再導入期・維持期)を正しく実践する
- 永続的な制限ではなく、自分に合った食生活を見つけることが目的
- 栄養バランスに配慮しながら進める
- 食事日記をつけて、食べ物と症状の関係を把握する
実践時の心構え
完璧を目指す必要はありません。特に再導入期以降は、「この食品は絶対に食べられない」と考えるのではなく、「この食品は少量なら大丈夫」「この食品は特別な日だけにしよう」といった柔軟な考え方が、長期的な生活の質の向上につながります。
医療機関の受診が必要なサイン
低FODMAP食事療法を試しても症状が改善しない場合や、以下のような症状がある場合は、必ず医療機関を受診してください。
- 制限期を適切に実践しても全く効果が見られない
- 症状が悪化する
- 体重が減少する
- 血便や激しい腹痛がある
- 発熱を伴う
腸活との組み合わせ
低FODMAP食事療法は、腸内環境を整える「腸活」と並行して行うことで、より効果的な場合があります。腸内環境の改善については、以前のブログ「【内科医が解説】腸活とは?今日から始められる腸内環境改善の方法」をご覧ください。
お腹の不調でお悩みの方は、一人で悩まず、まずは医療機関にご相談ください。当クリニックでは、患者様お一人おひとりの症状や生活スタイルに合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。
執筆者プロフィール

丹野内科・循環器・糖尿病内科 副院長 田邉 優希
- 日本糖尿病学会 糖尿病専門医
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本医師会 認定産業医
