- 2025年3月17日
健康診断でよく指摘される中性脂肪!下げるには?コレステロールとの違いは?
こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病の田邉弦です。今回はコレステロールとともに健康診断で指摘されることの多い脂質異常である中性脂肪のお話です。総論的な話なので、少し長くなってしまいましたが是非ご覧ください。
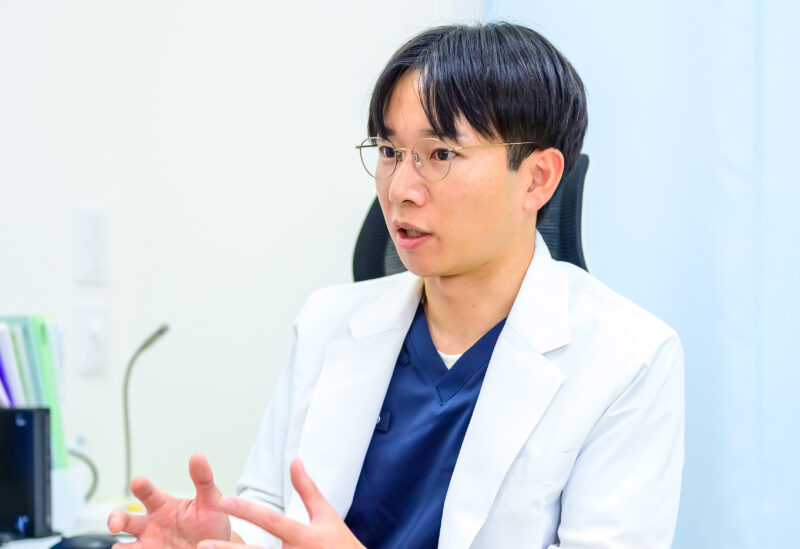
外来をやっていると中性脂肪の高い数値に悩まされている方は少なくありません。健康診断で「中性脂肪が高い」と指摘されても、具体的に何が問題なのか、どうすれば改善できるのか分からない方も多いと思います。本記事では、中性脂肪についての基礎知識から効果的な対策まで、わかりやすく解説します。
目次
- 中性脂肪とは?基本的な知識
- 中性脂肪とコレステロールの違い
- 中性脂肪が高くなる原因
- 中性脂肪が高いとどうなる?健康リスク
- 中性脂肪を下げる効果的な方法
- 薬物療法の適応と種類
- 健康診断での中性脂肪の見方
- Q&A:中性脂肪に関するよくある質問
- 中性脂肪管理のための日常生活のコツ
- まとめ

中性脂肪とは?基本的な知識
中性脂肪とは、体内に存在する脂質の一種です。トリグリセリドとも言われ、TGと略されることもあります。私たちが食事から摂取したエネルギーのうち、すぐに使われなかった余剰分が中性脂肪として体内に蓄えられます。つまり、中性脂肪は「エネルギーの貯蔵庫」としての役割を果たしているのです。
中性脂肪の役割
中性脂肪の主な役割は以下の通りです。
- エネルギー源としての機能:必要時にエネルギーとして利用される
- 体温維持:皮下脂肪として体を保温する
- 内臓保護:衝撃から内臓を守るクッションの役割
中性脂肪自体は、私たちの生命活動に欠かせない成分です。しかし、過剰に蓄積されると様々な健康リスクを引き起こす可能性があります。
中性脂肪の正常値とは
健康診断で確認される空腹時の中性脂肪の基準値は以下の通りです。
- 正常値:30〜149mg/dL
- 高中性脂肪血症の診断基準:空腹時 150mg/dL以上、非空腹時 175mg/dL以上
空腹時の中性脂肪値が150mg/dL未満であれば正常範囲内とされています。ただし、食後は中性脂肪値が上昇するため、非空腹時の採血では175mg/dLが基準値となっています。正確な測定のために健康診断では10時間程度の絶食後に採血を行うことが多いです。
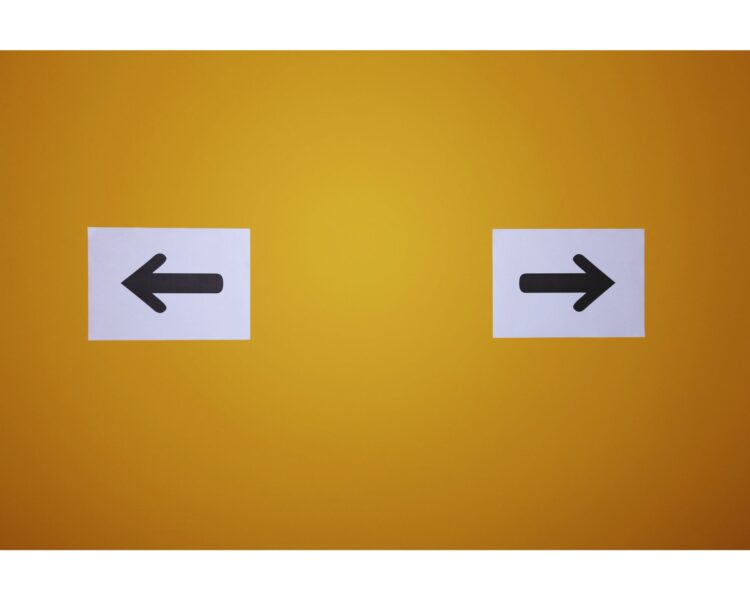
中性脂肪とコレステロールの違い
中性脂肪とコレステロールは、どちらも血液中の脂質ですが、その性質や役割は大きく異なります。
構造と機能の違い
中性脂肪
- 脂肪酸とグリセロールから構成される
- 主にエネルギー源としての役割
- 余剰カロリーが中性脂肪として蓄積される
コレステロール
- ステロイド骨格を持つ脂質
- 細胞膜の構成成分やホルモン合成の原料
- 体内で生成される(約7割が肝臓で生成、残りは食事から摂取)
健康への影響の違い
中性脂肪もコレステロールも高すぎると健康リスクとなりますが、その影響の仕方には若干の違いがあります。コレステロールの方が動脈硬化疾患に直接的な影響が大きいので、基本的にコレステロールも中性脂肪もどちらも高い場合は、コレステロールを優先して管理目標値を目指す。その上で中性脂肪も高いようなら治療を検討するという流れになっています。
管理目標値については以前のブログ『高コレステロール血症のゴールデンスタンダード!スタチンとは?』をご覧ください。
中性脂肪が高いと増加するリスク
- 急性膵炎
- メタボリックシンドローム
- 脂肪肝
- 動脈硬化 (間接的)
コレステロールが高いと増加するリスク
- 動脈硬化
- 心筋梗塞
- 脳卒中
数値の読み取り方の違い
健康診断では以下の項目が測定されます。
中性脂肪
- 単一の指標として測定
コレステロール
- LDLコレステロール(悪玉)
- HDLコレステロール(善玉)
- 総コレステロール
コレステロールの場合、単に「高い・低い」だけでなく、善玉と悪玉のバランスも重要となります。

中性脂肪が高くなる原因
中性脂肪値が上昇する要因は多岐にわたります。主な原因を以下に解説します。
食生活の問題
中性脂肪値上昇に最も影響するのは食習慣です。
- 過剰なカロリー摂取:必要以上のカロリーは中性脂肪として蓄積されます
- 糖質の過剰摂取:特に精製された糖質や炭水化物(白米、パン、麺類など)
- アルコールの過剰摂取:アルコールは肝臓での中性脂肪の分解を阻害します
- 不規則な食事時間:特に夜遅い食事は中性脂肪値を上昇させやすいです
生活習慣の問題
食生活以外にも、以下のような生活習慣が中性脂肪値に影響します。
- 運動不足:適度な運動は中性脂肪を消費するため、運動不足は蓄積の原因に
- 睡眠不足や質の悪い睡眠:ホルモンバランスの乱れを招き、脂質代謝に悪影響
- ストレス:過度なストレスはコルチゾールなどのホルモン分泌に影響し、中性脂肪を上昇させる
遺伝的要因
家族性高中性脂肪血症など、遺伝的要因で中性脂肪が高くなるケースもあります。両親や兄弟に高中性脂肪血症の方がいる場合、自分も注意が必要です。
疾患や薬剤の影響
以下のような病気や薬剤の影響で中性脂肪値が上昇することもあります。
- 糖尿病
- 甲状腺機能低下症
- 腎疾患
- ステロイド剤
- 経口避妊薬
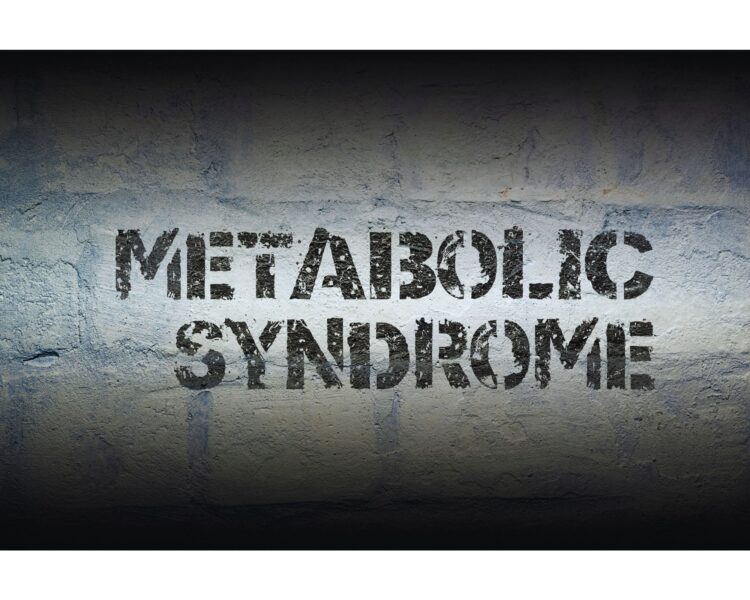
中性脂肪が高いとどうなる?健康リスク
中性脂肪値が継続的に高い状態は、様々な健康問題につながる可能性があります。
短期的なリスク
急性膵炎: 中性脂肪が500 mg/dL以上になると、急性膵炎を発症するリスクが急激に高まります。急性膵炎は激しい腹痛を伴い、重症化すると命に関わることもある深刻な疾患です。
長期的なリスク
1. 動脈硬化性疾患
高い中性脂肪値は、HDLコレステロール(善玉)を減少させ、小型LDLコレステロール(特に悪い悪玉)を増加させることで動脈硬化を促進し、以下のリスクを高めます。
- 心筋梗塞
- 脳卒中
- 末梢動脈疾患
2. メタボリックシンドローム
中性脂肪高値は、糖尿病、高血圧とともにメタボリックシンドロームの診断基準の一つです。メタボリックシンドロームはリスクが重なることにより、動脈硬化の急速な促進因子となります。
3. 脂肪肝
中性脂肪が肝臓に蓄積すると、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)を引き起こします。進行すると肝炎や肝硬変につながる可能性があります。

中性脂肪を下げる効果的な方法
中性脂肪値を下げるためには、日々の生活習慣の改善が最も重要です。以下に効果的な対策を紹介します。
食事療法
1. 糖質の摂取を見直す
- 精製された糖質(白米、白パン、菓子類)を適量にする
- 食物繊維が豊富な全粒穀物に切り替える
- 砂糖や果糖を含む飲料の摂取を控える
2. 適切な脂質を選ぶ
- トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングなど)を避ける
- オメガ3脂肪酸(青魚、アマニ油など)を積極的に摂る
- 良質な油(オリーブオイルなど)を適量使用する
3. 食事の取り方
- 食物繊維を先に摂る
- よく噛んでゆっくり食べる
- 規則正しい食事時間を守る
- 夕食は就寝の3時間前までに済ませる
運動療法
1. 有酸素運動
- ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を週に150分以上行う
- 毎日30分の早歩きでも効果的
- 継続することが最も重要
2. 筋力トレーニング
- 筋肉量を増やすことで基礎代謝が上がり、中性脂肪の消費が促進される
- 週に2回以上、主要な筋群を鍛えるトレーニングを行う
生活習慣の改善
1. アルコール摂取を適量に
- 日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本程度に制限
- 休肝日を設ける
2. 十分な睡眠
- 毎日6〜8時間の質の良い睡眠を心がける
- 就寝・起床時間を一定に保つ
3. ストレス管理
- 瞑想やヨガなどでリラックスする時間を持つ
- 趣味や楽しみを見つける
薬物療法の適応と種類
生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合、薬物療法を検討します。コレステロールが高い場合はほとんどスタチン一択でした、中性脂肪が高い場合は下記のような薬の選択肢があります。
薬物療法の適応
以下のような場合に薬物療法が検討されます。
- 中性脂肪値が500mg/dL以上と著しく高い場合(急性膵炎予防のため)
- 生活習慣改善を3〜6ヶ月行っても十分な効果が得られない場合
- 動脈硬化性疾患の既往や高リスク因子を複数持つ場合
主な治療薬
1. フィブラート系薬剤
- 中性脂肪を特異的に低下させる
- 効果は30〜50%程度
- 肝機能や腎機能障害に注意が必要
2. EPA製剤
- 魚油由来の高純度EPA
- 中性脂肪低下効果に加え、抗血栓作用も期待できる
- 副作用が比較的少ない
3. スタチン系薬剤
- 主にLDLコレステロールを下げる薬だが、中性脂肪も10〜20%程度低下させる
- コレステロールと中性脂肪が共に高い場合に使用
4. その他の薬剤
- ニコチン酸誘導体
- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬
健康診断での中性脂肪値の見方
健康診断で中性脂肪値を適切に解釈するためのポイントを解説します。
検査前の注意点
中性脂肪値は食事の影響を強く受けるため、
- 検査前10時間以上の絶食が理想的
- 前日の過度の飲酒や脂の多い食事は避ける
経時的変化の重要性
単回の検査値だけでなく、経時的な変化も重要です。
- 1回だけの高値なら一時的な要因かもしれない
- 継続的に高値が続く場合は対策が必要
- 年々上昇傾向にある場合も注意が必要
他の検査値との関連
中性脂肪値だけでなく、以下の値も合わせて評価することが重要です。
- HDLコレステロール(善玉):逆相関することが多い
- 空腹時血糖値:インスリン抵抗性を反映
- HbA1c:糖代謝の指標
- AST・ALT:肝機能の指標

Q&A:中性脂肪に関するよくある質問
患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1: 中性脂肪を下げるのに効果的な食品はありますか?
A: 以下の食品が効果的です。
- 青魚(サバ、サンマ、イワシなど)に含まれるEPA・DHA
- 食物繊維が豊富な野菜、海藻、きのこ類
- 大豆製品(納豆、豆腐など)
- オリーブオイルなどの良質な油
- ナッツ類(適量)
Q2: 中性脂肪とHDL(善玉)コレステロールはなぜ逆相関するのですか?
A: 中性脂肪が高い状態では、HDLコレステロールの生成が抑制され、分解も促進されるため、HDL値が低下します。また、運動不足や肥満といった生活習慣は中性脂肪を上げると同時にHDLを下げる作用があります。このため、中性脂肪を下げる生活習慣の改善は、HDLコレステロールの上昇にも効果的です。
Q3: 薬を飲まずに改善できますか?
A: 中性脂肪値が300mg/dL未満の場合は、食事療法や運動療法などの非薬物療法を3〜6ヶ月間しっかり実践することで改善が期待できます。しかし、遺伝的要因が強い場合や、値が著しく高い場合(500mg/dL以上)は薬物療法が必要なことが多いのも事実です。
Q4: 運動はどのくらいの強度で行えばよいですか?
A: 中性脂肪を下げるには有酸素運動が効果的です。「少し息が上がるけれど会話はできる」程度の中強度の運動を、1回30分以上、週に150分以上行うことが理想的です。ただし、まったく運動習慣がない方は、まず5〜10分の軽いウォーキングから始めて、徐々に時間を延ばしていくことをお勧めします。継続することが何よりも重要です。
中性脂肪管理のための日常生活のコツ
中性脂肪値を適切に管理するためには、一時的な対策ではなく、持続可能な生活習慣の改善が重要です。以下に実践しやすいコツをまとめました。
食事のコツ
1. 炭水化物との向き合い方
- 「炭水化物抜き」は長続きしないので、量を減らす工夫を
- 白米なら1杯を2/3杯に
- 主食より先に野菜やタンパク質から食べる
2. 食事の取り方
- よく噛んで食べる(一口30回を目標に)
- 食事は20分以上かけてゆっくりと
- 腹八分目を心がける
3. 外食のコツ
- サラダや野菜の小鉢を先に注文
- 麺類の場合、スープは残す
- アルコールと高カロリーな食事の「二重負荷」を避ける
運動習慣を続けるコツ
1. 日常生活に取り入れる (通勤や家事の際にも)
- エレベーターではなく階段を使う
- 一駅分歩く
- 筋トレは「ながら」でも効果的(テレビを見ながらスクワットなど)
2. モチベーション維持法
- 仲間、家族と一緒に運動する
- 運動の記録をつける
- 目標を小さく区切って達成感を味わう
検査値を改善するための生活リズム
1. 睡眠の質を高める
- 就寝前のスマートフォンを避ける
- 寝室は快適な温度と暗さに保つ
- 休日も起床時間はあまりずらさない
2. ストレス管理
- 深呼吸や瞑想を取り入れる
- 自分なりのリラックス方法を見つける
- 趣味や楽しみの時間を確保する

まとめ
中性脂肪の管理は、単に数値を下げるだけでなく、健康的な生活を送るための指標として捉えることが大切です。
重要なポイント
- 中性脂肪は「余剰エネルギーの貯蔵庫」: 摂取カロリーと消費カロリーのバランスが鍵
- コレステロールとは異なる特性と対策: それぞれの特性を理解して総合的に管理
- 数値改善には時間がかかることを理解する: 一時的な対策ではなく、継続的な生活習慣の改善が重要
- 個人差を考慮: 自分に合った対策を見つけることが成功の秘訣
- 定期的な検査で変化をチェック: 数値の変化を確認して対策を調整
当院では、中性脂肪をはじめとする脂質異常症の患者さんに対して、以下のようなサポートを行っています。
- 血液検査と生活習慣の評価
- 一人ひとりの生活スタイルに合わせた改善プランの提案
- 必要に応じた薬物療法と定期的なモニタリング
- 合併症の早期発見・治療のための総合的な管理
健康診断で中性脂肪高値を指摘された方は、まずは一度ご相談ください。お電話または当ホームページからご予約いただけます。
