- 2025年5月5日
- 2025年5月7日
止まらない咳の原因と対処法 ~症状別の対応と受診の目安~

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。「咳が止まらない。」と言ってクリニックを受診される方は多くいます。特に睡眠が取れないような激しい咳もあり、困っていらっしゃる方も多いです。本記事では、内科医の視点から、咳の原因や対処法、受診の目安について詳しく解説します。日常的な対処から医療機関を受診すべき状況まで、幅広くご紹介しますので、つらい咳でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
目次
- 咳のメカニズム – なぜ咳は出るのか
- 止まらない咳の主な原因
- 咳の種類と特徴
- 咳が続く期間による分類と注意点
- セルフケア – 自宅でできる咳の対処法
- 病院を受診すべき咳の症状
- 咳に関するよくある質問
- まとめ – 咳との上手な付き合い方

咳のメカニズム – なぜ咳は出るのか
咳は、私たちの体を守るための大切な防御反応(反射)です。気道に入った異物や刺激物を排出し、肺や気道を保護する働きがあります。
咳が出るメカニズムは、次のような流れになっています。
- 気道の感覚神経が刺激を感知
- その信号が脳に伝わる
- 脳から「咳をするように」という指令が出る
- 胸の筋肉や横隔膜が収縮して空気を勢いよく排出
このように、咳そのものは体を守るための反応ですが、長く続く場合や強い咳はQOL (生活の質)を下げ、体力を消耗させる原因になります。
止まらない咳の主な原因
咳が止まらない状態には、様々な原因が考えられます。主なものをご紹介します。
感染症による咳
- 風邪(急性上気道炎):最も一般的な原因で、のどの痛みや鼻水、発熱を伴うことが多いです。
- インフルエンザ:高熱と全身症状を伴う激しい咳が特徴です。
- 気管支炎:気管支の粘膜が炎症を起こし、痰を伴う咳が1〜2週間続きます。
- 肺炎:発熱や息切れを伴う咳で、高齢者では症状が典型的でない場合もあります。
- 百日咳:特徴的な「ヒューッ」という音を伴う咳が数週間続きます。
風邪に関しては以前のブログ「風邪が新型コロナと同じ5類感染症に?何が変わるの?そもそも風邪とは?」をご覧ください。
アレルギーや慢性疾患による咳
- 気管支喘息・咳喘息:特に夜間や早朝に悪化する咳や、運動後に生じる咳が特徴です。
- アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎:後鼻漏(鼻からのどに流れる分泌物)による刺激で咳が出ます。
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD):長年の喫煙などが原因で、徐々に悪化する咳や息切れが見られます。
- 胃食道逆流症(GERD):胃酸が食道に逆流し、のどを刺激することで咳が生じます。
環境要因による咳
- 乾燥:特に冬場は室内の乾燥によって気道粘膜が刺激されやすくなります。
- 大気汚染:PM2.5や黄砂、化学物質などによる刺激で咳が出ることがあります。
- タバコ:喫煙や受動喫煙は持続的な咳の原因になります。
薬剤性の咳
- ACE阻害薬 (降圧薬):高血圧の治療に使われる薬の一部で、空咳の副作用が出ることがあります。

咳の種類と特徴
咳には様々な種類があり、その特徴から原因を推測できることがあります。
乾いた咳(空咳)
痰を伴わない乾いた咳です。以下のような特徴があります。
- のどのイガイガ感を伴うことが多い
- 風邪の初期や、アレルギー性疾患、気管支喘息などに見られる
- 夜間に悪化することが多い
湿った咳(痰を伴う咳)
痰を伴う咳には、以下のような特徴があります。
- 気管支炎や肺炎などの感染症に多く見られる
- 痰の色や性状が診断の手がかりになる
- 白色・透明な痰:初期の気管支炎、アレルギー性疾患
- 黄色や緑色の痰:ウイルスや細菌感染の可能性
- 血痰(血液の混じった痰):肺癌や結核の可能性
咳の発生タイミングによる特徴
咳が出るタイミングも、原因を探る手がかりになります。
- 朝に多い咳:COPD、気管支拡張症などが考えられます。夜間に溜まった分泌物を排出するため、起床時に咳が増えます。
- 夜に悪化する咳:喘息、胃食道逆流症、副鼻腔炎による後鼻漏などが多いです。横になることで症状が悪化します。
- 食事中や食後の咳:誤嚥(食べ物や飲み物が気管に入ること)や胃食道逆流症が疑われます。
咳が続く期間による分類と注意点
咳は続く期間によって分類され、その対応も異なります。
急性咳嗽(3週間未満)
風邪やインフルエンザなどの急性感染症による咳が多く、通常は自然に改善します。しかし、以下のような場合は注意が必要です。
- 発熱(37.5℃以上)が4日以上続く
- 息苦しさを感じる
- 胸痛がある
- 血痰が出る
このような症状がある場合は、肺炎になっている可能性があるため、早めに医療機関を受診しましょう。
遷延性咳嗽(3〜8週間)、慢性咳嗽(8週間以上)
急性上気道炎や急性気管支炎後などに咳が残る感染後咳嗽や気管支炎後咳嗽が一番多いケースです。その他に、以下のような慢性疾患が潜んでいる可能性があります。
- 結核
- 百日咳
- 気管支喘息・咳喘息
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 胃食道逆流症
- 副鼻腔気管支症候群・慢性副鼻腔炎
- 薬剤性の咳
3週間以上咳が続く場合は、特に結核を否定するために胸部レントゲン検査が推奨されます。
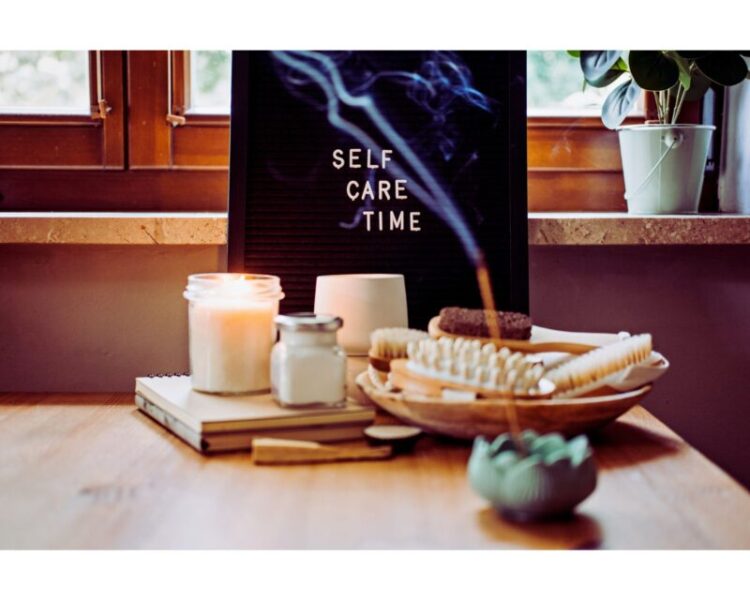
セルフケア – 自宅でできる咳の対処法
咳がつらいときに、自宅でできる対処法をご紹介します。ただし、これらはあくまで対症療法であり、原因に応じた適切な治療が必要な場合もあります。
水分摂取と加湿
- 十分な水分を摂ることで、気道の粘膜を潤し、痰を出しやすくします。
- 部屋の湿度を50〜60%程度に保つことが理想的です。
- 特に寝室の加湿は夜間の咳の緩和に効果的です。
のどの保護
- マスクの着用:外気の刺激や乾燥からのどを守ります。
- のど飴やハチミツ:のどの粘膜を保護し、刺激を和らげます。
- 温かい飲み物:のどの痛みを和らげ、血行を促進します。
姿勢と休息
- 半座位(上半身を少し起こした姿勢)で寝ると、夜間の咳が軽減することがあります。
- 十分な休息をとり、体力を回復させることも大切です。
入浴
- 温かい湯船につかることで、気道の緊張がほぐれ、痰が出やすくなります。
食事の工夫
- 刺激物(辛いもの、酸っぱいもの)は避ける。
- 就寝前の食事や飲酒を控える(特に胃食道逆流が疑われる場合)。

病院を受診すべき咳の症状
以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
肺炎を疑う症状
- 呼吸困難や息苦しさがある
- 高熱(38.5℃以上)が続く
- 胸痛を伴う
- 食事がとれない
その他の受診の目安
- 3週間以上咳が続く
- 夜間の咳で睡眠が妨げられる
- 痰の量が多い、または色や性状が変化した
- 高齢者や持病(喘息、心疾患など)がある方の咳の悪化
咳に関するよくある質問
Q1: 咳止め薬は飲んだ方がいいですか?
A1: 咳には体内の異物を排出する防御機能があるため、むやみに咳を抑えることは推奨されません。特に痰を伴う咳の場合、咳止め薬の使用は痰の排出を妨げる可能性があります。医師の診察を受けて、適切な薬を処方してもらうことをお勧めします。
Q2: 咳が止まらなくて眠れません。どうしたらいいですか?
A2: 夜間の咳対策としては、
- 上半身を少し高くして寝る
- 寝室の加湿を十分に行う
- 就寝前の水分摂取(ただし寝る直前の大量の水分は避ける)
夜の咳が強い場合、喘息などの病気が隠れている場合があります。症状が続く場合は医療機関を受診し、原因に応じた治療を受けることをお勧めします。
Q3: 季節の変わり目に咳が出やすいのはなぜですか?
A3: 気温や湿度の急激な変化が気道に刺激を与えることや、季節特有のアレルゲン(花粉など)の影響が考えられます。また、季節の変わり目はウイルス感染症も流行しやすい時期です。マスク着用や適切な湿度管理などの予防策が有効です。

まとめ – 咳との上手な付き合い方
咳は体を守るための大切な反応ですが、長く続くと生活の質を低下させ、体力も消耗します。以下のポイントを整理します。
- 咳の特徴を観察する:いつ、どのような咳が出るか、痰の性状はどうかなど観察しましょう。→咳の特徴は診察時にも大きなヒントになります。
- 適切なセルフケア:水分摂取、加湿、休息など基本的なケアを行いましょう。
- 受診の目安を知る:特に危険なサインを見逃さないよう、受診すべき症状を把握しておきましょう。
- 原因に応じた対策:咳の原因は様々です。診断を受け、自分の咳の原因に合った対策を行うことが大切です。
- 予防を心がける:手洗い・うがい、適切な湿度管理、禁煙などの基本的な予防策も重要です。
咳が続く場合や、息苦しさ、血痰などの症状がある場合は、自己判断せずに是非当院にご相談ください。患者さん一人ひとりの症状に応じて適切な検査を行い原因に応じた治療を行います。当ホームページより予約できます。お気軽にご相談ください。
