- 2025年7月10日
【内科医が解説】熱中症の症状を見逃さないために知っておきたい基礎知識と対処法

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。夏の暑い日が続くと、気になるのが「熱中症」ですね。ここ数年の夏は異常に熱く、多くの方が熱中症で体調を崩され、救急搬送が必要になるケースもあります。私も総合病院で働いていたころは農作業やゴルフ中に倒れ、救急搬送されてくる方を多く目にしていました。実際に消防庁の統計によると、熱中症による救急搬送者数は年間約9万人を超えていますが、適切な知識と対処により多くの場合は予防や早期対応が可能と考えられます。松戸市で内科クリニックを開業している私のもとにも、「これって熱中症でしょうか?」「どんな症状に注意すればいいの?」といったご相談を多くいただきます。本記事では、内科医の視点から、最新のガイドラインに基づく熱中症の症状について詳しく解説します。
目次

熱中症とは何か?最新の基礎知識を理解しましょう
熱中症の定義と診断基準
熱中症とは、「暑熱環境に居る、あるいは居た後」に発症する体調不良の総称です。高温多湿な環境に長時間いることで、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなることで起こります。
2024年の熱中症ガイドラインでは、熱中症の診断基準がより明確になりました。単に暑い環境にいただけでなく、「暑熱環境に居る、あるいは居た後」という条件が重要なポイントとなっています。
熱中症が起こりやすい条件
熱中症は以下のような条件が重なると発生しやすくなります
環境的要因
- 気温が28度以上、特に35度を超える猛暑日
- 湿度が70%以上の高湿度環境
- 風が弱く、日差しが強い状況
- エアコンが効いていない室内
個人的要因
- 水分補給を怠りがちな方
- 睡眠不足や体調不良の状態
- 高齢者や乳幼児
- 糖尿病、高血圧などの基礎疾患をお持ちの方
- 肥満の方
- 暑さに慣れていない方
最新の熱中症重症度分類
2024年のガイドラインでは、熱中症の重症度が以下の4段階に分類されています
- I度(軽度):現場での対応が可能
- II度(中等度):医療機関での診察が必要
- III度(重度):入院治療が必要
- IV度(最重度):生命に関わる緊急事態
この分類により、より適切な対応が可能になりました。
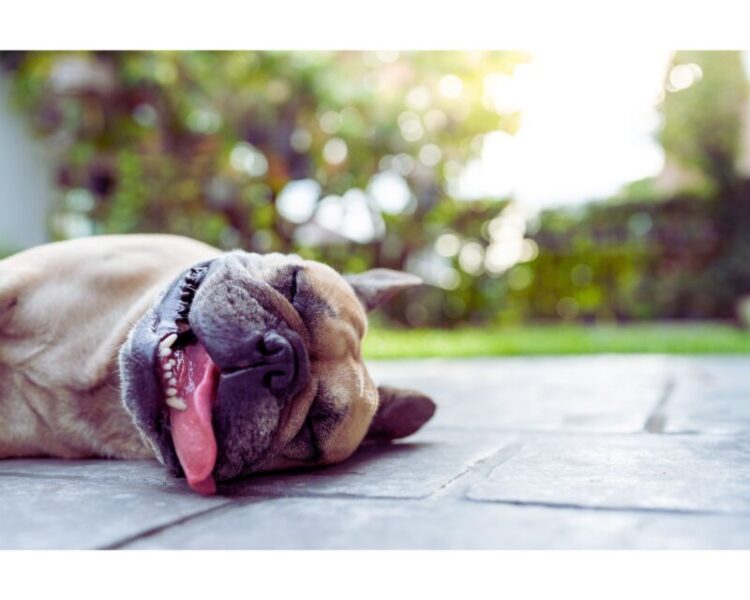
熱中症の症状:最新の4段階分類を詳しく解説
再診のガイドラインでは熱中症の症状が4段階に分類されています。分類自体は少し専門的な話になりますので読み飛ばしていただければと思いますが、熱中症の症状の多彩さがわかると思います。
I度(軽度)の症状
主な症状
- めまい、失神(立ちくらみ)
- 生あくび
- 大量の発汗
- 筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)
- 意識障害は認めない
具体的な症状の例:例えば、炎天下でガーデニングをしていて「急に立ち上がったらくらっとした」「ふくらはぎがつった」「なんだか生あくびが出る」といった症状です。
対処法
- 涼しい場所での休息(Passive Cooling)
- 効果が不十分な場合は、Active Cooling(様々な方法で熱中症患者の体を冷却すること)
- 経口での水分・電解質補給
通常は現場での対応が可能とされていますが、症状が改善しない場合は医療機関への相談が推奨されます。
II度(中等度)の症状
主な症状
- 頭痛
- 嘔吐
- 倦怠感、虚脱感
- 集中力や判断力の低下(JCS1:見当識障害がある程度)
具体的な症状の例:「午後から頭がガンガン痛くて、気持ち悪くて仕事に集中できない」「なんとなくぼーっとして、いつもできることができない」「人の名前や今日の日付がすぐに思い出せない」といった状態です。
対処法
- 医療機関での診察が必要
- Passive Cooling(効果が不十分な場合はActive Cooling)
- 十分な水分・電解質補給(経口摂取困難時は点滴)
この段階では、必ず医療機関を受診することが重要です。
III度(重度)の症状
III度は以下の3つの症状のうち、いずれかを含む場合に診断されます
1. 中枢神経症状
- 意識障害(JCS2:刺激に対する反応が鈍い)
- 小脳症状(ふらつき、協調運動障害)
- 痙攣発作
2. 肝・腎機能障害
- 入院経過観察が必要な程度の肝機能障害
- 入院加療が必要な程度の腎機能障害
3. 血液凝固異常
- 急性DIC(播種性血管内凝固)の診断基準を満たす状態
対処法
- 入院治療が必要
- Active Coolingを含めた集学的治療を考慮
IV度(最重度)の症状
2024年のガイドラインで新たに追加された最重症群です。
診断基準
- 深部体温40.0℃以上
- かつGCS≦8
具体的な状態
- 深昏睡状態
- 非常に高い体温
- 生命に直結する危険な状態
対処法
- 直ちにActive Coolingを含めた集学的治療
- 救急搬送が必要
- 集中治療管理
このような症状が見られた場合は、迷わず救急車を呼ぶことが必要です。
Active CoolingとPassive Coolingの違い
最新のガイドラインでは、冷却方法も明確に分類されています
Active Cooling
- 冷水浴(冷水につかる)
- 蒸散冷却(体に水をかけて扇風機で風を当てる)
- 局所冷却(氷嚢などを用いて局所冷却)
- 胃・膀胱洗浄(冷水を用いた胃・膀胱洗浄)
- 体外式膜型人工肺(ECMOを利用する)
Passive Cooling
- 涼しい環境での休息
重症度に応じて適切な冷却方法を選択することが重要です。

熱中症が体に与える影響とメカニズム
体温調節システムの破綻
正常な状態では、私たちの体は視床下部という脳の一部が「体温調節の司令塔」として機能しています。気温が上がると以下の反応が起こります。
- 汗腺から汗を分泌して気化熱で体を冷やす
- 皮膚の血管を拡張して熱を放出する
- 呼吸を早くして熱を逃がす
しかし、高温多湿の環境が続くと、この調節システムが限界を超えてしまいます。
脱水と電解質バランスの崩れ
大量の汗をかくことで、体内の水分だけでなく、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの電解質も失われます。これらの電解質は
- 筋肉の収縮をコントロール
- 神経の伝達を調整
- 体液のバランスを維持
これらの重要な働きをしているため、バランスが崩れると様々な症状が現れます。
各臓器への影響
脳への影響:脱水により脳への血流が減少し、めまいや意識障害が起こります。重度になると脳浮腫(脳のむくみ)や脳機能障害を起こすことがあります。
心臓への影響:脱水→血液量の減少により心臓に負担がかかり、頻脈や血圧低下が生じます。
肝臓への影響:高体温により肝細胞の障害が起こり、肝機能異常が見られることがあります。
腎臓への影響:脱水により腎機能が低下し、急性腎不全を起こすリスクがあります。
血液凝固系への影響:重度の熱中症では、DIC(播種性血管内凝固)という血液の凝固異常が起こることがあります。

熱中症の予防法と対処法
効果的な予防法
水分補給のコツ
- のどが渇く前に定期的に水分を取る
- 1時間に200~250ml程度を目安に
- 運動時や発汗が多い時は、塩分も一緒に補給
- アルコールやカフェインは利尿作用があるため避ける
服装と環境の工夫
- 通気性が良く、色の薄い服装を選ぶ
- 帽子や日傘で直射日光を避ける
- 室内では適切にエアコンを使用(設定温度28度以下)
- 扇風機との併用で体感温度を下げる
生活習慣の見直し
- 十分な睡眠をとる
- バランスの良い食事を心がける
- 暑さに慣れるため、段階的に活動量を調整(暑熱順化)
症状が現れた時の対処法
軽度(I度)の症状の場合
- 涼しい場所への移動
- エアコンの効いた室内
- 木陰などの涼しい場所
- 水分・塩分の補給
- 経口補水液やスポーツドリンク
- 水に塩を少量加えたもの(0.1~0.2%濃度)
- 体を冷やす
- 首、脇の下、太ももの付け根を冷やす
- 濡れタオルで体を拭く
中等度(II度)以上の症状の場合
- 医療機関での診察が必要
- 意識がはっきりしない場合は、誤嚥の可能性あり水分補給を避ける
重度(III度・IV度)の症状の場合
- 直ちに救急車を呼ぶ
- 到着まで可能な限り体を冷やす
- 意識がない場合は気道確保に注意する(横向きが望ましい。)
医療機関を受診すべき症状
以下の症状がある場合は、迷わず医療機関を受診することが推奨されます
緊急性の高い症状(救急車を呼ぶべき症状)
- 意識がもうろうとしている、または意識がない
- 体温が40度以上
- 水分を自力で摂取できない
- 嘔吐が続いている
- けいれんを起こしている
- 呼びかけに反応しない
- 真っ直ぐ歩けない
やや緊急性のある症状(医療機関受診が必要)
- 頭痛が強い
- 吐き気が持続している
- 体温が38度以上
- めまいやふらつきが改善しない
- 集中力や判断力の低下が見られる
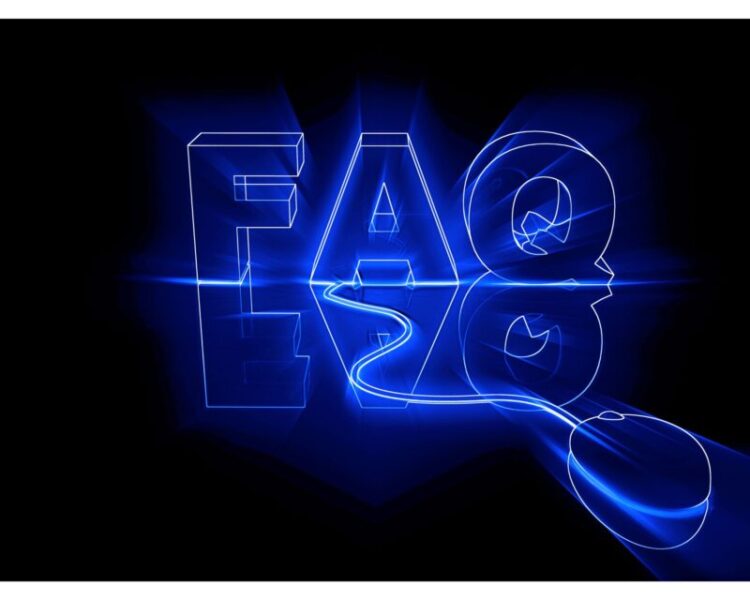
よくある質問(Q&A)
Q1. 熱中症の症状はどのくらいで治りますか?
A: 重症度により異なります
- I度:適切な処置により数時間程度で改善が期待できます
- II度:医療機関での治療により数時間~1日程度
- III度・IV度:入院治療が必要で、完全回復には数日から数週間を要することがあります
完全な回復には、軽度でも数日かかることが一般的ですので、症状が改善しても無理はしないことが大切です。
Q2. 室内にいても熱中症になりますか?
A: はい、室内でも熱中症は起こります。実際に、熱中症患者の約4割は住宅内で発症しています。特に以下の場合注意が必要です。
- エアコンを使用していない室内
- 風通しの悪い室内
- 西日が当たる室内
- 高齢者や乳幼児
Q3. 高齢者は熱中症になりやすいのですか?
A: はい、高齢者は熱中症のリスクが高いです。理由としては、
- 体温調節機能の低下
- のどの渇きを感じにくくなる
- 腎機能の低下により水分調節が困難
- 暑さに対する感覚の鈍化
- 基礎疾患の影響
周囲の方の見守りと、定期的な水分補給の声かけが重要です。高齢者ほど暑さを感じづらく、もったいないなどの理由からエアコンをつけたがらないため、注意が必要です。
Q4. 子どもの熱中症の症状に特徴はありますか?
A: 子どもの場合、以下の点に注意が必要です
- 体温調節機能が未熟
- 症状を正確に訴えられない場合がある
- 機嫌が悪くなる、ぐずりが続く
- 食欲低下、活動量の減少
- 体重に対する体表面積が大きく、熱による影響を受けやすい
大人よりも症状の変化が早いため、こまめな観察が大切です。
Q5. 熱中症になった後、注意することはありますか?
A: 症状が改善した後も、以下の点にご注意ください。
- しばらくは激しい運動や長時間の外出を控える
- こまめな水分補給を継続する
- 体調の変化に注意を払う
- 数日間は無理をしない
- 一度熱中症になると再発しやすい傾向
完全回復まで十分な時間をかけることが重要です。

まとめ
2024年の最新ガイドラインに基づく熱中症の症状について解説いたしました。新たに追加されたIV度の概念により、より適切な対応が可能になりました。
重要なポイント
- 最新の4段階分類(I度~IV度)に基づく症状の理解
- 軽度の症状(めまい、筋肉のけいれん、生あくび)を見逃さない
- II度以上では医療機関での診察が必要
- III度・IV度では入院治療や救急対応が必要
- Active CoolingとPassive Coolingの使い分け
予防の重要性
- のどが渇く前の水分補給
- 適切な環境管理(エアコン使用など)
- 高齢者や子どもへの特別な配慮
- 暑熱順化の重要性
熱中症は予防可能な病気です。最新の知識を身につけ、適切な対処法を実践することで、重篤な状態を避けることができます。もし熱中症の症状でご心配な点がございましたら、お気軽にご相談ください。暑い夏を安全に乗り切るために、本ブログをぜひお役立てください。
参考
