- 2025年7月28日
夏バテに良い食べ物とは!内科医が教える効果的な栄養対策と予防法

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。夏の暑さが厳しくなると、「なんとなく疲れやすい」「食欲がない」「だるさが続く」といった症状を経験される方も多いと思います。これらは夏バテの典型的な症状です。内科医としての経験から申し上げますと、夏バテの改善と予防において「食事」の役割は非常に重要です。適切な栄養摂取により、暑さに負けない体づくりが可能になります。この記事では、夏バテのメカニズムから、具体的に摂取すべき食べ物、避けるべき食品まで、実践的な情報をお伝えします。毎日の食事を見直すことで、元気に夏を乗り切りましょう。
目次
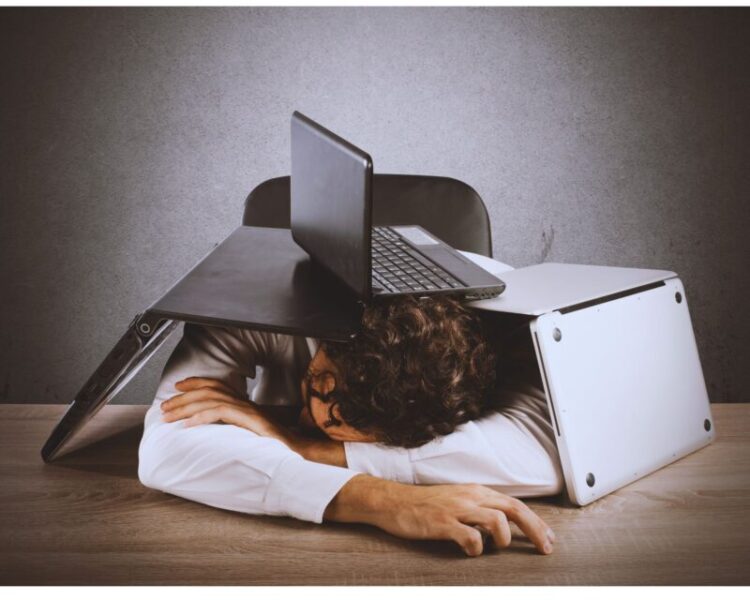
夏バテとは?基礎知識を理解しよう
夏バテとは、高温多湿な環境が続くことで起こる体の不調の総称です。医学的には「暑熱順化不全」や「熱中症の軽症」として分類されることもあります。
夏バテが起こるメカニズム
人間の体は約37度の体温を保つため、暑い環境では以下のような調節機能が働きます。
体温調節の仕組み
- 汗をかいて体温を下げる
- 血管を拡張して熱を逃がす
- 呼吸により熱を放散する
しかし、この調節機能が長期間働き続けることで、体に様々な負担がかかります。特に、大量の発汗により水分と一緒にナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの重要なミネラル(電解質)が失われることが問題となります。
自律神経への影響
冷房の効いた室内と暑い屋外の温度差が激しい現代の生活環境では、自律神経系に大きな負担がかかります。自律神経は体温調節、消化機能、血圧調整など、生命維持に重要な機能をコントロールしているため、この不調が全身の様々な症状として現れるのです。

夏バテの症状と体への影響
夏バテの症状は人によって異なりますが、以下のようなものが一般的です。
主な症状
身体的症状
- 全身の倦怠感・だるさ
- 食欲不振
- 消化不良・胃もたれ
- 頭痛・めまい
- 睡眠障害(寝つきの悪さ、浅い眠り)
- 微熱が続く
- 体重減少
精神的症状
- 集中力の低下
- イライラしやすくなる
- やる気が出ない
- 記憶力の低下
特に注意が必要な方
以下の方は夏バテになりやすく、より深刻な症状が現れる可能性があります。
- 高齢者
- 乳幼児
- 慢性疾患をお持ちの方(糖尿病、高血圧、心疾患など)
- 普段から運動不足の方
- 睡眠不足が続いている方

夏バテに効果的な栄養素と食べ物
夏バテの予防と改善には、失われた栄養素を適切に補給することが重要です。以下の栄養素を意識して摂取しましょう。
ビタミンB群
役割と効果:ビタミンB群は糖質や脂質をエネルギーに変換する際に欠かせない栄養素です。特にビタミンB1は「疲労回復のビタミン」とも呼ばれ、夏バテ対策には不可欠です。
豊富に含まれる食品
- ビタミンB1: 豚肉、うなぎ、玄米、枝豆、にんにく
- ビタミンB2: レバー、卵、乳製品、納豆、アーモンド
- ビタミンB6: まぐろ、かつお、鶏胸肉、バナナ、パプリカ
電解質(ミネラル)
ナトリウムとカリウムのバランス:汗で失われるナトリウムとカリウムを適切に補給することで、体内の水分バランスを保ち、筋肉や神経の正常な働きを維持できます。
効果的な食品
- カリウム: スイカ、メロン、バナナ、トマト、きゅうり、アボカド
- マグネシウム: アーモンド、ほうれん草、海藻類、大豆製品
- 亜鉛: 牡蠣、肉類、ナッツ類、チーズ
抗酸化物質
夏の強い紫外線や暑さによるストレスで発生する活性酸素を除去する働きがあります。
主要な抗酸化物質と食品
- ビタミンC: レモン、オレンジ、キウイ、ピーマン、ブロッコリー
- ビタミンE: アーモンド、植物油、アボカド、かぼちゃ
- β-カロテン: にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、トマト
水分補給を助ける食品
高水分含有の野菜・果物
- きゅうり(水分95%)
- トマト(水分94%)
- スイカ(水分92%)
- レタス(水分96%)
これらの食品は水分補給と同時に必要な栄養素も摂取できるため、夏バテ対策に最適です。

具体的な食事のポイントと実践法
1. 1日3食を規則正しく摂る
夏バテ時は食欲が落ちがちですが、少量でも規則正しく食事を摂ることが重要です。
朝食の重要性:朝食を抜くと、一日のエネルギー源が不足し、夏バテの症状が悪化する可能性があります。以下を参考に軽めでも栄養価の高い朝食を心がけましょう。
- バナナとヨーグルト
- トマトと卵のスープ
- 納豆ご飯
- フルーツスムージー
2. 消化に良い調理法を選ぶ
夏バテ時は消化機能も低下しているため、胃腸に負担をかけない調理法が推奨されます。
おすすめの調理法
- 蒸し料理: 野菜の蒸し物、茶わん蒸し
- 煮込み料理: 野菜スープ、お粥
- 冷製料理: 冷やし中華、冷製パスタ、ガスパチョ
3. 香辛料やハーブを活用する
食欲増進効果のある香辛料やハーブを上手に使いましょう。
効果的な香辛料・ハーブ
- しょうが: 消化促進、食欲増進
- にんにく: 疲労回復、食欲増進
- しそ: 食欲増進、抗菌作用
- みょうが: 食欲増進、さっぱり感
4. 食事のタイミングと量
小分けして食べる:一度に大量に食べるよりも、少量を複数回に分けて食べる方が消化に良く、栄養の吸収も効率的です。
5. 水分と一緒に摂る工夫
スープや汁物を活用:水分補給と栄養摂取を同時に行える料理を取り入れましょう
- 野菜たっぷりのみそ汁
- 冷製コーンスープ
- フルーツ入りの白湯
- 麦茶ベースのゼリー

夏バテ対策で避けるべき食べ物
夏バテの症状を悪化させる可能性のある食品もあります。完全に避ける必要はありませんが、摂取量を控えめにすることが推奨されます。
1. 冷たすぎる食べ物・飲み物
胃腸への負担:アイスクリーム、氷入りの飲み物、冷やしすぎた食べ物は、胃腸の温度を急激に下げ、消化機能を低下させる可能性があります。
代替案
- 常温の水や麦茶
- 自然な甘みのフルーツ
- 冷やしすぎない冷製料理
2. 脂っこい食べ物
消化に時間がかかる食品
- 揚げ物全般
- ラーメン(特に背脂系)
- ファストフード
- マヨネーズを多用した料理
これらは消化に多くのエネルギーを必要とするため、夏バテで体力が低下している時には胃腸に負担をかけます。
3. 糖分の多い飲み物
血糖値の急激な変化:清涼飲料水、スポーツドリンクの飲みすぎは血糖値を急激に上昇させ、その後の急降下により疲労感を増大させる可能性があります。(反応性低血糖と言います。)
適切な水分補給
- 水や麦茶をベースに
- スポーツドリンクは運動時や大量発汗時のみ
- 自家製の薄めた経口補水液
4. アルコール
脱水作用:夏の暑い時期に冷えたビールはおいしく感じると思いますが、アルコールには利尿作用があり、体内の水分を奪います。また、肝臓でのアルコール分解にビタミンB群が大量に消費されるため、夏バテの症状を悪化させる可能性があります。

よくある質問(Q&A)
Q1: 夏バテの時、サプリメントを飲んでも良いですか?
A: 基本的には食事からの栄養摂取が推奨されますが、食欲不振で十分な栄養が摂れない場合は、ビタミンB群や電解質のサプリメントが有効な場合があります。ただし、摂取前には医師や薬剤師にご相談いただくことをお勧めします。特に持病をお持ちの方や他の薬を服用中の方は要注意です。
Q2: 夏バテ対策の食事で、どのくらいで効果を感じられますか?
A: 個人差がありますが、適切な栄養摂取を続けることで、一般的には1-2週間程度で体調の改善を感じる方が多いです。ただし、症状が重い場合や長期間続いている場合は、食事療法と並行して医療機関での相談も検討してください。
Q3: 食欲がない時の強制的な食事は逆効果でしょうか?
A: 無理に大量に食べる必要はありません。少量でも栄養価の高い食品を選び、水分補給を重視してください。例えば、バナナ半分とヨーグルト、または野菜ジュースなど、消化に良い栄養豊富な食品から始めることが推奨されます。
Q4: 夏バテ予防のための食事は、いつから始めるべきですか?
A: 理想的には梅雨明け前の6月頃から意識的な食事管理を始めることが推奨されます。体が暑さに慣れる前から栄養状態を整えておくことで、夏バテの予防効果が高まります。
Q5: 高齢者の夏バテ対策で特に注意すべき点はありますか?
A: 高齢者は脱水症状になりやすく、またのどの渇きを感じにくい場合もあります。以下の点に特に注意してください。
- こまめな水分補給(のどの渇きを感じる前に)
- 塩分の適度な摂取
- 薬と食事の相互作用の確認
- 食事量の記録と体重の定期的なチェック

まとめ
夏バテは現代社会において多くの方が経験する身近な体調不良ですが、適切な食事管理により予防・改善が可能です。
重要なポイントを再確認しましょう
- 栄養バランスの重視: ビタミンB群、電解質、抗酸化物質を意識的に摂取
- 規則正しい食事: 少量でも3食をきちんと摂る
- 消化に良い調理法: 蒸し物、煮物、冷製料理を活用
- 水分補給と栄養摂取: スープや汁物を取り入れる
- 避けるべき食品の認識: 冷たすぎる食べ物、脂っこい料理、糖分過多の飲み物
医療機関への相談が必要な場合
以下の症状が続く場合は、単なる夏バテではなく、熱中症や他の疾患の可能性もあるため、早めに医療機関を受診してください。
- 高熱(38度以上)が続く
- 激しい頭痛や吐き気
- 意識がもうろうとする
- 体重の急激な減少
- 症状が2週間以上続く
いかがだったでしょうか?近年の夏は異常に暑いですが、適切な知識と対策で乗り切ることができます。この記事が皆様の健康維持の一助となれば幸いです。
