- 2025年8月15日
むくみの原因を徹底解説|気になる症状から予防法まで専門医が詳しく説明

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。「夕方になると靴がきつくなる」「指輪が抜けなくなった」など、むくみの症状でお悩みの方は少なくありません。むくみは単なる美容の問題ではなく、時として重要な病気のサインである可能性もあります。循環器専門医の立場から、むくみの原因や対処法について、わかりやすくご説明いたします。この記事を読むことで、ご自身のむくみの原因を理解し、適切な対処法を見つけていただければと思います。
目次

むくみとは何か?基礎知識の解説
むくみのメカニズム
むくみとは、医学的には「浮腫(ふしゅ)」と呼ばれ、体の組織に余分な水分が溜まった状態を指します。私たちの体は約60%が水分でできており、この水分は血管内、細胞内、そして細胞と細胞の間(間質)に存在しています。通常、この水分バランスは絶妙に調整されているのですが、何らかの原因でこのバランスが崩れると、間質に余分な水分が溜まってむくみが生じます。例えば、ホース(血管)の水圧が高すぎて周りに水(血液の成分)が漏れ出す状況をイメージしていただくとわかりやすいでしょう。
むくみが起こりやすい部位
むくみは重力の影響を受けやすいため、以下の部位に特によく現れます。
- 足首・足の甲:立ち仕事の方に最も多い
- すね:指で押すと凹みが残る特徴的な症状
- 顔・まぶた:朝起きた時に特に目立つ
- 手・指:指輪がきつくなる症状
- 全身:重篤な場合は全身になります
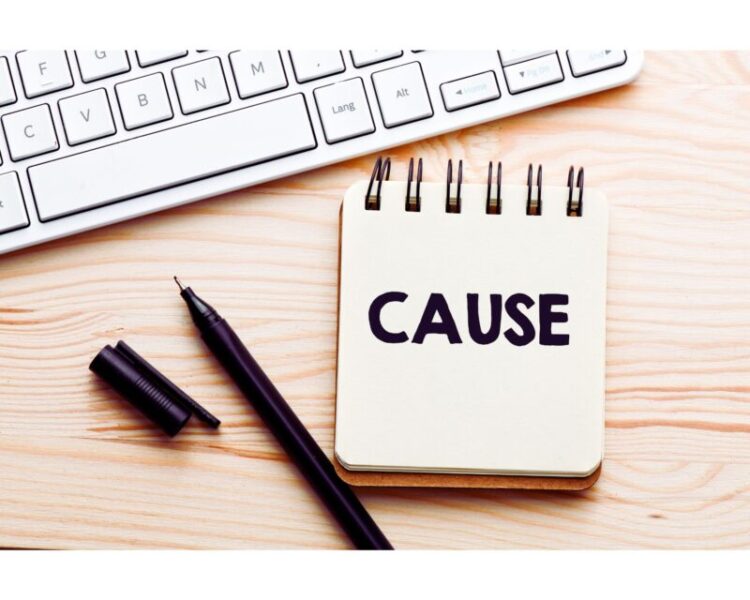
むくみの主な原因
1. 生理的なむくみ(病気ではないもの)
長時間の同じ姿勢
デスクワークや立ち仕事で長時間同じ姿勢を続けると、血液の循環が悪くなり、特に下肢にむくみが生じやすくなります。ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」と呼ばれ、血液を心臓に送り返すポンプの役割を果たしているためです。
塩分の過剰摂取
塩分を多く摂取すると、体内の塩分濃度を一定に保つために水分を体に溜め込もうとします。ラーメンやインスタント食品を食べた翌日にむくみやすいのはこのためです。
女性ホルモンの影響
月経前症候群(PMS)や妊娠中は、女性ホルモンの変動により水分を体に溜め込みやすくなります。これは生理的な現象で、多くの女性が経験していると思います。
薬剤の影響
血圧を下げる薬(カルシウム拮抗薬)、ステロイド薬、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などがむくみの原因となることがあります。
2. 病的なむくみ(病気が原因のもの)
心臓病
心不全では心臓のポンプ機能が低下し、血液の循環が悪くなります。特に足のむくみから始まり、進行すると全身に及ぶことがあります。息切れや倦怠感を伴うことが多いのが特徴です。
腎臓病
腎臓は体内の水分バランスを調整する重要な臓器です。腎機能が低下すると、余分な水分や塩分を排出できなくなり、むくみが生じます。
肝臓病
肝臓で作られるアルブミンというタンパク質が減少すると、血管内に水分を保持する力が弱くなり、むくみが生じます。お腹に水が溜まる腹水も伴うことがあります。
甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンが不足すると、全身の代謝が低下し、特に顔や手足にむくみが現れます。寒がり、体重増加、便秘なども併せて見られることが多いです。
静脈疾患
下肢静脈瘤や深部静脈血栓症では、脚の血液の戻りが悪くなり、脚にむくみが生じます。血栓ができている脚がむくむので片側のみのこともあります。

症状の特徴と注意すべきサイン
一般的なむくみの症状
- 指で押すと凹みが残る(圧痕性浮腫)
- 靴下やストッキングの跡がくっきり残る
- 夕方になると足が重く感じる
- 朝起きた時に顔がぱんぱんに腫れる
- 指輪がきつくなる
医療機関での受診が必要なサイン
以下の症状がある場合は、速やかに医療機関を受診することをお勧めします。
緊急性の高い症状
- 突然の息切れや胸痛を伴うむくみ
- 片側の脚だけの急激なむくみ
- 発熱を伴うむくみ
- 意識がもうろうとする
継続的な医療管理が必要な症状
- 1週間以上続く全身のむくみ
- 体重が短期間で2-3kg以上増加
- 尿の量が明らかに減少
- 疲れやすさや息切れを伴う
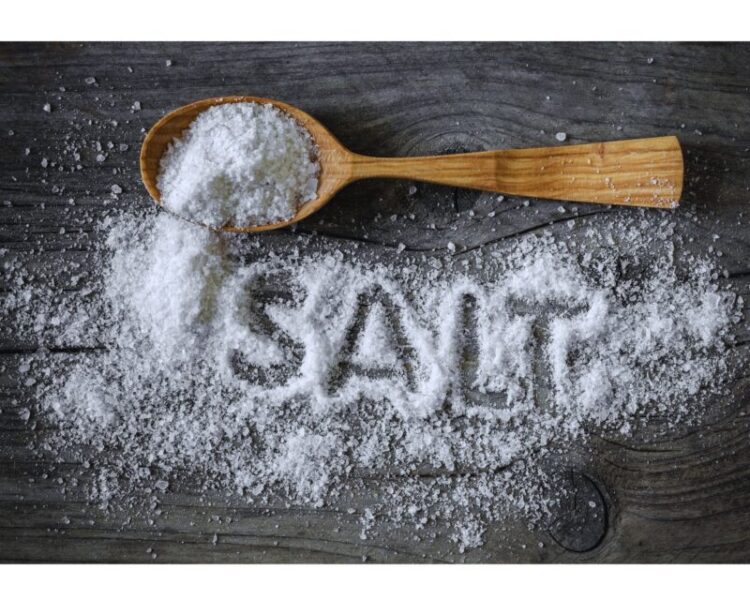
日常生活でできる予防法と対処法
1. 食生活の改善
塩分制限
1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが推奨されています。これは小さじ1杯程度の量です。以下の点にご注意ください。
- 加工食品やインスタント食品を控える
- 調味料は「かける」より「つける」
- 出汁や香辛料を活用して薄味に慣れる
- 食品の栄養成分表示をチェックする
カリウムを多く含む食品の摂取
カリウムは体内の余分な塩分を排出する働きがあります。以下の食品を積極的に摂取しましょう。ただし腎機能障害がある方は制限が必要なこともありますので、主治医と相談してください。
- バナナ、アボカド、キウイフルーツ
- ほうれん草、小松菜などの緑黄色野菜
- じゃがいも、さつまいも
- 豆類、海藻類
適切な水分摂取
水分を控えすぎると、かえって体が水分を溜め込もうとします。1日1.5〜2リットル程度の水分摂取を心がけましょう。(透析の方は除く)
2. 運動とマッサージ
ふくらはぎの筋力強化
- つま先立ち運動:1日20〜30回
- 足首の回転運動:時計回り・反時計回りそれぞれ10回
- ウォーキング:1日30分程度
マッサージ
足首から膝に向かって、優しく撫で上げるようにマッサージします。強く押しすぎないよう注意が必要です。
3. 生活習慣の改善
姿勢の工夫
- デスクワーク中は1時間に1回立ち上がる
- 座る時は足を組まない
- 寝る時は足を心臓より高い位置に上げる
着圧ソックスの活用
医療用弾性ストッキングは、適切な圧力で血液循環を改善します。ただし、動脈疾患がある方は医師に相談してから使用してください。

よくある質問(Q&A)
Q1. むくみと肥満の違いは何ですか?
A1. むくみは水分の貯留によるもので、指で押すと凹みが残るのが特徴です(中にはへこみが残らない浮腫もありますが。)。また、比較的短期間で変化します。一方、肥満は脂肪の蓄積によるもので、押しても凹みは残りません。体重の急激な変化(2-3日で2kg以上の増加)がある場合は、むくみの可能性が高いと考えられます。
Q2. 妊娠中のむくみは心配ありませんか?
A2. 妊娠中のむくみは生理的なものが多いですが、高血圧に伴っている場合は、妊娠高血圧症候群の症状である可能性もあります。急激な体重増加、高血圧、タンパク尿を伴う場合は、速やかに産婦人科を受診してください。定期的な妊婦健診を受けることが大切です。
Q3. 利尿薬を自己判断で使用しても良いですか?
A3. 利尿薬の自己判断での使用はお勧めできません。むくみの原因によっては、利尿薬が適さない場合もあり、電解質バランスの異常や脱水などの副作用のリスクもあります。必ず医師の診察を受けて、適切な治療を受けることが重要です。
Q4. どのタイミングで病院を受診すべきですか?
A4. 以下の場合は早めの受診をお勧めします。
- 1週間以上続くむくみ
- 急激な体重増加を伴うむくみ
- 息切れや胸痛を伴うむくみ
- 片側だけのむくみ
- 発熱を伴うむくみ
Q5. むくみの検査はどのようなことを行いますか?
A5. 一般的には以下の検査を行います。
- 血液検査(腎機能、肝機能、甲状腺機能など)
- 尿検査 (蛋白尿の有無)
- 心電図・心エコー検査、胸部X線検査
病歴や症状、身体所見に応じて、必要な検査を選択いたします。

まとめ
むくみは多くの方が経験する症状ですが、その原因は様々です。生理的なものから重篤な病気のサインまで幅広い可能性があるため、適切な判断が重要です。
重要なポイント
- 日常生活の改善:塩分制限、適度な運動、適切な水分摂取が基本
- 早期受診:継続するむくみや他の症状を伴う場合は医療機関へ
- 定期的な健康チェック:年1回の健康診断で早期発見を心がける
- 自己判断は避ける:薬の使用や治療法は医師と相談して決める
当院では、むくみの原因を詳しく調べ、患者様一人ひとりに最適な治療法をご提案いたします。気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。
