- 2025年8月21日
糖尿病の初期症状を見逃さないために〜早期発見で健康な生活を守る方法〜

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉優希です。「最近、のどが渇きやすい」「疲れが取れにくい」そんな症状を感じていませんか?これらの症状は、もしかすると糖尿病の初期症状かもしれません。糖尿病は初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうことが多い病気です。しかし、早期に発見し適切な治療を受けることで、健康な生活を維持することは十分可能です。この記事では、糖尿病の初期症状について詳しく解説いたします。ご自身やご家族の健康管理の参考にしていただければ幸いです。
目次
- 糖尿病とは〜基礎知識を理解しよう
- 糖尿病の初期症状〜見逃しやすいサインを知る
- 症状が現れる理由〜なぜこれらの症状が起こるのか
- 日常生活での気づきのポイント
- 糖尿病の予防と早期対策
- よくある質問(Q&A)
- まとめ

糖尿病とは〜基礎知識を理解しよう
糖尿病の基本的なメカニズム
糖尿病とは、血液中の糖分(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。通常、私たちが食事をすると血糖値が上がりますが、膵臓から分泌される「インスリン」というホルモンの働きによって、糖分が細胞に取り込まれ、血糖値は正常な範囲に戻ります。糖尿病では、このインスリンの分泌が不十分になったり、インスリンが正常に働かなくなったりすることで、血糖値が高い状態が続いてしまいます。
糖尿病の種類
糖尿病には主に以下のように分類されています。
1型糖尿病
- 自己免疫などによりインスリンを作る細胞が破壊される
- 主に若年者に発症
- 全糖尿病患者の約5%
2型糖尿病
- 生活習慣の影響が大きい
- 成人に多く見られる
- 全糖尿病患者の約95%
妊娠糖尿病
- 妊娠中に初めて見つかった糖代謝異常
この記事では、最も患者数が多い2型糖尿病の初期症状を中心に解説いたします。

糖尿病の初期症状〜見逃しやすいサインを知る
典型的な初期症状
糖尿病の初期症状は、日常生活の中で「なんとなく調子が悪い」程度に感じられることが多く、見逃してしまいがちです。以下のような症状に心当たりがある場合は、注意が必要です。
1. 異常な喉の渇き(多飲)
具体的な症状:
- 水を飲んでもすぐに喉が渇く
- 1日に2リットル以上の水分を摂取している
- 夜中に喉が渇いて目が覚める
日常生活での例: 「いつものようにコーヒーを飲んだ後、すぐにまた水が飲みたくなる」「会議中に何度も水分補給をしたくなる」といった状況が頻繁に起こります。
2. 頻繁な尿意(多尿)
具体的な症状:
- トイレに行く回数が明らかに増えた
- 夜間に2回以上トイレで目が覚める
- 尿の量が以前より多い
日常生活での例: 「映画を最後まで見ることができない」「長時間の会議や移動が不安になる」など、生活に支障をきたすレベルで尿意を感じるようになります。
3. 異常な疲労感・倦怠感
具体的な症状:
- 十分に睡眠を取っても疲れが取れない
- 階段を上るのが以前より辛い
- 仕事や家事への集中力が続かない
日常生活での例: 「朝起きた時点で既に疲れている」「いつものように家事をこなすのが億劫に感じる」といった状況が続きます。
4. 食欲の変化
具体的な症状:
- 普段より食べているのに体重が減る
- 逆に異常に食欲が増す
- 甘いものが無性に欲しくなる
日常生活での例: 「食事量は変わらないのに、1ヶ月で2-3kg体重が減った」「お菓子を食べても満足感が得られない」といった変化が見られます。
5. 皮膚や粘膜の症状
具体的な症状:
- 皮膚のかゆみや乾燥
- 傷の治りが遅い
- 歯肉炎や口内炎が治りにくい
日常生活での例: 「ちょっとした擦り傷がなかなか治らない」「歯磨きをしても歯茎の腫れが引かない」といった症状が続きます。
6. 視覚の変化
具体的な症状:
- 視界がぼやける
- 目のかすみ
- 見え方が以前と違う
日常生活での例: 「新聞の文字が読みにくくなった」「夜間の運転が不安になった」といった変化を感じることがあります。
見逃しやすい軽微な症状
以下のような軽微な症状も、実は糖尿病の初期症状である可能性があります。
- 集中力の低下
- イライラしやすくなる
- 手足のしびれやピリピリ感
- 感染症にかかりやすくなる
- 体重の変動(増減どちらも)

症状が現れる理由〜なぜこれらの症状が起こるのか
高血糖による身体への影響
多飲・多尿のメカニズム
血糖値が高くなると、腎臓は余分な糖分を尿として排出しようとします。この際、糖分と一緒に大量の水分も失われるため、脱水状態になります。身体は失われた水分を補おうとして、強い喉の渇きを感じさせ、水分摂取を促します。
これは、「砂糖水をコップに入れて放置すると水分が蒸発しやすくなる」現象と似ています。血液中の糖分が高いと、身体から水分が失われやすくなるのです。
疲労感が起こる理由
糖分は身体のエネルギー源ですが、インスリンの働きが悪くなると、糖分が細胞に取り込まれにくくなります。その結果、細胞がエネルギー不足状態になり、疲労感や倦怠感を感じるようになります。
これは、「ガソリンタンクは満タンなのに、エンジンにガソリンが届かない車」のような状態と例えることができます。
体重減少のメカニズム
糖分が細胞に取り込まれないため、身体は代替エネルギー源として筋肉や脂肪を分解し始めます。これにより、食事量が変わらないにも関わらず体重が減少することがあります。

日常生活での気づきのポイント
セルフチェックの方法
以下のチェックリストを参考に、ご自身の症状を確認してみてください。
□ 最近1ヶ月で以下の症状が3つ以上該当する
- 喉の渇きを感じる頻度が増えた
- トイレに行く回数が明らかに増えた
- 疲れやすくなった
- 体重に変化があった(増減問わず)
- 傷の治りが遅くなった
- 視界がぼやけることがある
□ 生活習慣に関するリスクファクター
- 40歳以上である
- 家族に糖尿病の人がいる
- 肥満傾向にある(BMI25以上)
- 運動不足である
- 喫煙習慣がある
- ストレスを感じることが多い
記録を取る重要性
症状に気づいたら、以下の項目を記録することをお勧めします。
- 症状の内容と頻度
- いつ、どのような症状を感じたか
- 症状の強さ(10段階評価など)
- 食事内容
- 何を食べた後に症状が強くなるか
- 食事時間と症状の関係
- 生活パターン
- 睡眠時間と質
- 運動量
- ストレスレベル
このような記録をしておくと、医師の診察時に非常に有用な情報となります。

糖尿病の予防と早期対策
生活習慣の改善
糖尿病の予防や進行抑制には、生活習慣の改善が最も重要です。
糖尿病の予防に関しての詳細は以前のブログ「糖尿病予防の鍵は生活習慣!簡単に実践できる方法」をご覧ください。
食事療法のポイント
基本的な考え方:
- 規則正しい食事時間を心がける
- バランスの良い食事内容にする
- 適切な食事量を意識する
具体的な実践方法
- 糖質の摂取方法を工夫する
- 白米を玄米や雑穀米に変える
- パンは全粒粉のものを選ぶ
- 野菜から食べ始める(ベジファースト)
- 食事の順番を意識する
- 野菜 → タンパク質 → 炭水化物の順番
- ゆっくりとよく噛んで食べる
- 1食にかける時間は20分以上
- 間食の工夫
- ナッツ類や小魚などを選ぶ
- 果物は朝食時に適量摂取
- 砂糖を多く含む菓子類は控える
運動療法の重要性
推奨される運動
- 有酸素運動
- ウォーキング:1日8,000歩以上
- 水泳やサイクリング:週3回、30分程度
- 階段の利用を心がける
- 筋力トレーニング
- 週2-3回、各部位を鍛える
- 自重トレーニング(腕立て伏せ、スクワットなど)
- 軽いダンベルを使用した運動
運動を始める際の注意点
- 急激な運動は避け、徐々に強度を上げる
- 医師と相談の上、個人に適した運動プログラムを作成する
ストレス管理
慢性的なストレスは血糖値の上昇につながるため、適切なストレス管理が重要です。
効果的なストレス解消法
- 十分な睡眠時間の確保(7-8時間)
- 趣味の時間を大切にする
- 深呼吸や瞑想などのリラクゼーション
- 家族や友人とのコミュニケーション
定期的な健康チェック
糖尿病の早期発見には、定期的な健康チェックが欠かせません。
推奨される検査
- 年1回の健康診断
- 血糖値検査(空腹時血糖、HbA1c)
- 40歳以上の方は特定健診の受診
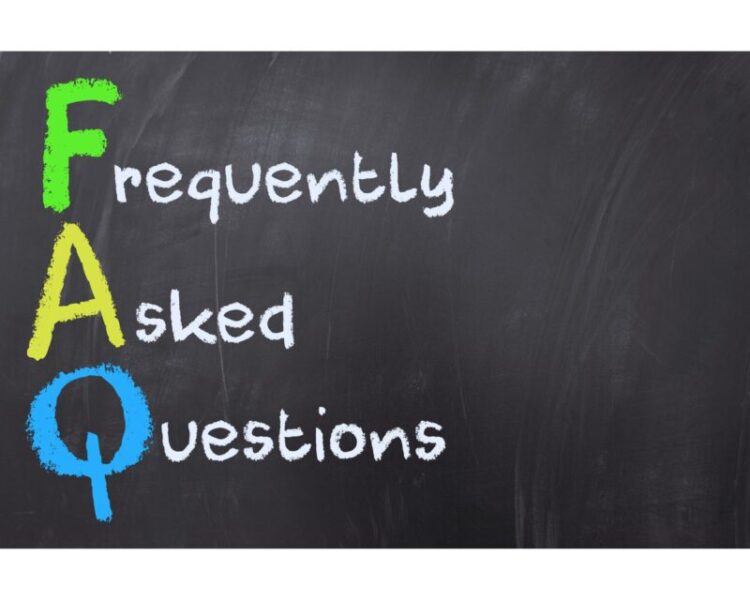
よくある質問(Q&A)
Q1. 糖尿病の初期症状はどのくらいの期間で現れますか?
A1. 2型糖尿病の場合、症状の現れ方には個人差があります。数年かけてゆっくりと進行することが多く、初期症状に気づかないまま健康診断で発見されるケースも少なくありません。一方で、急激に症状が現れる場合もあるため、気になる症状がある場合は早めに医療機関を受診することが大切です。
Q2. 家族に糖尿病患者がいる場合、必ず糖尿病になりますか?
A2. 遺伝的要因は糖尿病のリスクファクターの一つですが、家族歴があるからといって必ず糖尿病になるわけではありません。生活習慣の改善により、発症リスクを大幅に減らすことが可能です。逆に、家族歴がなくても生活習慣によっては糖尿病を発症する可能性があります。
Q3. 症状が軽い場合、治療せずに様子を見ても大丈夫ですか?
A3. 糖尿病は進行性の疾患であり、症状が軽いからといって治療を先延ばしにすることは推奨されません。早期の段階で適切な治療を開始することで、合併症の予防と生活の質の維持が可能になります。まずは専門医に相談し、適切な治療方針を決めることが重要です。
Q4. 血糖値が正常に戻れば、治療は不要になりますか?
A4. 糖尿病は慢性疾患であり、血糖値が改善しても完全に「治る」ことはないといわれます。しかし、適切な治療と生活習慣の維持により、健康な人と変わらない生活を送ることは十分可能です。治療を中断せず、長期的な管理を継続することが大切です。
Q5. 糖尿病の初期症状と他の病気の症状を見分ける方法はありますか?
A5. 糖尿病の初期症状は他の疾患の症状と似ている場合があり、症状だけで判断することは困難です。特に、多飲・多尿・体重減少・疲労感が組み合わさって現れた場合は、糖尿病の可能性が高くなります。症状が続く場合は、血液検査を含む医学的な評価を受けることが重要です。

まとめ
糖尿病の初期症状は、日常生活の中で見過ごしやすいものが多く、「年齢のせい」「疲れているだけ」と軽視してしまいがちです。しかし、これらの症状を早期に認識し、適切な対応を取ることで、糖尿病の進行を防ぎ、健康な生活を維持することができます。
重要なポイントの再確認
- 早期発見の重要性
- 症状が軽微でも、複数の症状が組み合わさった場合は要注意
- 定期的な健康チェックを欠かさない
- 気になる症状があれば、早めに医療機関を受診する
- 生活習慣の改善
- バランスの取れた食事と適度な運動
- ストレス管理と十分な睡眠
- 禁煙と適度な飲酒
- 継続的な管理
- 専門医との連携
- 定期的な検査の受診
当クリニックでは、糖尿病の予防から治療まで、患者様お一人お一人に合わせた医療を提供しております。糖尿病は適切な管理により、健常人とかわらない生活を送ることができる疾患です。気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。
また、糖尿病に関する正しい知識を身につけ、ご家族やお知り合いの方々とも情報を共有していただければと思います。地域全体で糖尿病予防に取り組むことで、より健康な社会を築いていけると信じております。
執筆者プロフィール

丹野内科・循環器・糖尿病内科 副院長 田邉 優希
- 日本糖尿病学会 糖尿病専門医
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本医師会 認定産業医
