- 2025年9月27日
- 2025年10月9日
【2025年版】インフルエンザ流行の基礎知識と対策法|松戸市の内科専門医が解説

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。毎年冬の季節になると、「インフルエンザが流行しているようだけど、どう対策すればよいのだろう」「家族がインフルエンザにかかったらどうしよう」といった不安を感じる方が多くいらっしゃいます。昨シーズンは年末年始にインフルエンザが大流行しましたが、当クリニックがある千葉県では今年は早くもインフルエンザの流行シーズン入りが発表されました。「インフルエンザの流行シーズン入りについて」
私自身多くの患者様のインフルエンザ診療に携わってきた経験から、正しい知識と適切な対策をお伝えしたいと思います。この記事では、インフルエンザ流行の基礎知識から具体的な予防法、感染時の対処法まで、皆様の日常生活に役立つ実践的な情報を分かりやすく解説いたします。是非ご覧ください。
目次

インフルエンザ流行の基礎知識
インフルエンザとは何か
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性の呼吸器感染症です。一般的な風邪と異なり、全身に強い症状が現れることが特徴です。
インフルエンザウイルスには主にA型、B型、C型の3つの型があり、特にA型とB型が毎年の流行を引き起こします。A型は症状が重く、B型は比較的軽症とされていますが、どちらも注意が必要です。
流行のメカニズム
インフルエンザが流行する理由として、以下の要因が挙げられます。
1. 季節性の要因
- 気温の低下と湿度の低下により、ウイルスが空気中で長時間生存しやすくなります
- 冬季は屋内で過ごす時間が長くなり、人同士の接触機会が増加します
2. ウイルスの特性
- インフルエンザウイルスは毎年少しずつ変異するため、過去の感染や予防接種による免疫が完全ではありません
- 感染力が強く、1人の感染者から平均1~3人に感染が広がるとされています
3. 社会的要因
- 学校や職場などの集団生活の場での感染拡大
- 交通機関や商業施設での人の移動による感染の拡散
流行の時期と規模
日本では例年、12月から3月にかけてインフルエンザの流行シーズンとなります。厚生労働省の統計によると、流行期には全国で約1,000万人がインフルエンザに感染すると推定されています。
昨シーズン(2024-2025年)にかけては、年末年始にピークを迎えましたが、例年1月から2月にかけてがピークとなることが多く、この時期は特に注意が必要です。学校などでは学級閉鎖や学年閉鎖が実施されることもあり、社会生活にも大きな影響を与えます。

インフルエンザの症状と影響
主な症状
インフルエンザの症状は、感染から1~3日の潜伏期間を経て現れます。主な症状は以下の通りです。
全身症状
- 急激な発熱(38℃以上の高熱)
- 悪寒・震え
- 全身の倦怠感
- 筋肉痛・関節痛
- 頭痛
呼吸器症状
- 乾いた咳
- 鼻水・鼻づまり
- のどの痛み
消化器症状
- 吐き気・嘔吐
- 下痢
インフルエンザで胃腸炎症状は馴染みがないかもしれませんが、インフルエンザの20%程度で消化器症状が出現するとの報告もあります。
風邪との違い
多くの患者様から「風邪とインフルエンザの違いは?」というご質問をいただきます。主な違いは以下の通りです。
| 項目 | インフルエンザ | 風邪 |
| 発症 | 急激 | 緩やか |
| 発熱 | 38℃以上の高熱 | 微熱~37℃台 |
| 症状 | 全身症状が強い | 局所症状が中心 |
| 流行性 | あり | 年間を通じて散発的 |
例えば、「朝は元気だったのに、お昼頃から急に高熱が出た」「体中が痛くて起き上がれない」といった症状がある場合は、インフルエンザの可能性が高いと考えられます。ただし、ワクチン接種している方は症状が軽くなるので、症状だけで見分けることは困難です。
合併症のリスク
インフルエンザで特に注意すべきは合併症です。以下のような方は重症化リスクが高いとされています。
- 65歳以上の高齢者
- 5歳未満の小児(特に2歳未満)
- 妊娠中の女性
- 慢性疾患(糖尿病、心疾患、腎疾患、呼吸器疾患など)をお持ちの方
- 免疫機能が低下している方
主な合併症として、肺炎、脳症、心筋炎などがあり、重篤な場合は生命に関わることもあります。
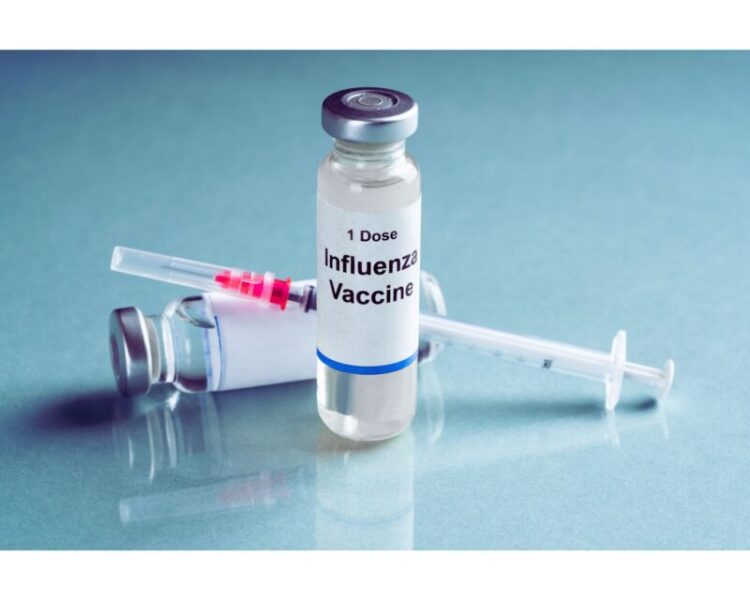
効果的な予防法と対策
予防接種(ワクチン接種)
インフルエンザ予防の最も効果的な方法は、予防接種を受けることです。
接種時期
- 10月から12月中旬までの接種が推奨されます
- 接種後約2週間で免疫が獲得されるため、流行前の早めの接種が重要です
効果
- 感染予防効果は約60~90%とされています
- 感染した場合でも重症化を防ぐ効果が期待できます
接種対象
- 生後6ヶ月以上のすべての方が対象です
- 特に高リスク群の方は積極的な接種が推奨されます
インフルエンザワクチンについての詳細は以前のブログ「インフルエンザ予防接種の効果と接種時期 | 松戸市の内科医が詳しく解説」をご覧ください。

日常生活での予防対策
1. 手洗い・手指消毒:正しい手洗いは最も基本的で重要な予防法です。
手洗いのタイミング
- 外出から帰宅した時
- 食事の前
- トイレの後
- 咳やくしゃみを手で覆った後
正しい手洗い方法
- 流水で手を濡らし、石鹸をつける
- 手のひら、手の甲、指の間、爪の先まで20秒以上かけて洗う
- 流水でよく洗い流す
- 清潔なタオルやペーパータオルで拭く
2. マスクの着用
- 人混みや公共交通機関では適切にマスクを着用しましょう
- 咳やくしゃみが出る場合は、必ずマスクを着用し、他者への感染防止に努めましょう
3. 咳エチケット
- 咳やくしゃみをする際は、ティッシュや肘の内側で口と鼻を覆いましょう
- 使用したティッシュはすぐに廃棄し、手洗いを行いましょう
4. 環境の整備
- 室内の湿度を50~60%に保ちましょう
- 定期的な換気を心がけましょう
- 十分な睡眠と栄養バランスの良い食事で免疫力を維持しましょう
生活習慣の見直し
栄養管理:免疫力を高めるため、以下の栄養素を意識して摂取しましょう。
- ビタミンC(柑橘類、野菜)
- ビタミンD(魚類、卵)
- 亜鉛(肉類、海産物)
- 発酵食品(ヨーグルト、納豆)
睡眠:成人は7~9時間の質の良い睡眠を心がけましょう。睡眠不足は免疫機能の低下につながります。
運動:適度な運動は免疫機能を向上させます。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で継続しましょう。

感染が疑われる時の対処法
早期受診の重要性
インフルエンザが疑われる症状が現れた場合は、早期の医療機関受診が重要です。
受診のタイミング
- 38℃以上の発熱と全身症状が現れた場合
- 症状出現から48時間以内(抗インフルエンザ薬の効果が期待できる期間)
受診前の準備
- 事前に医療機関に電話連絡を行い、症状を伝える (当院では発熱外来の予約をお願いします。)
- マスクを着用して受診する
自宅での療養
安静と休養
- 十分な睡眠と安静を保ちましょう
- 無理な活動は症状を悪化させる可能性があります
水分補給
- 発熱による脱水を防ぐため、こまめな水分補給を心がけましょう
- 状態に応じて経口補水液も効果的です
解熱剤の使用
- 医師の指示に従って適切に使用しましょう
- 小児にはアスピリン系の解熱剤は使用しないでください
感染拡大防止
- 発症から5日間、かつ解熱から2日間(小児は3日間)は外出を控えましょう
- 家族への感染を防ぐため、可能であれば隔離して接触を控えましょう。
医療機関での治療
診断
- 迅速診断キットによる検査
- 症状や流行状況を総合的に判断
治療法
- 抗ウイルス薬(タミフル、イナビル、ゾフルーザなど)
- 対症療法(解熱剤、咳止めなど)
入院適応:以下の場合は入院治療が必要となることがあります。
- 重篤な合併症の発症
- 脱水症状が著しい場合
- 基礎疾患の悪化
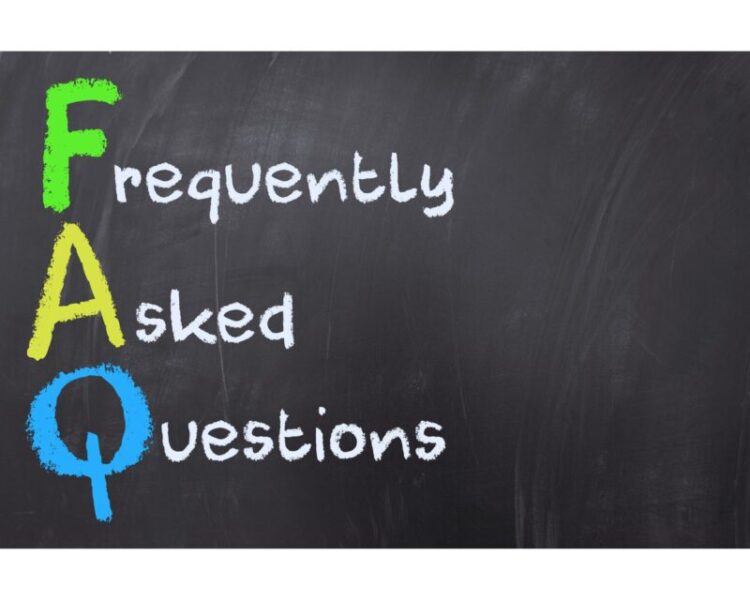
よくある質問(Q&A)
Q1: インフルエンザワクチンを接種したのに感染しました。ワクチンは効果がないのでしょうか?
A1: インフルエンザワクチンの効果は100%ではありませんが、感染リスクの軽減や重症化予防に重要な役割を果たします。ワクチンを接種していても感染する場合がありますが、症状が軽くなったり、回復が早くなったりする効果が期待できます。(65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています。)
Q2: 家族がインフルエンザになった場合、どのような対策を取ればよいでしょうか?
A2: 家族内感染を防ぐため、以下の対策を実践してください。
- 感染者は可能な限り個室で療養
- 共用部分(ドアノブ、テーブルなど)の定期的な消毒
- こまめな手洗いと換気
- 家族全員の健康状態の観察
Q3: インフルエンザにかかったら、いつから職場や学校に復帰できますか?
A3: 復帰の目安は「発症から5日経過し、かつ解熱から2日経過してから」とされています。ただし、咳などの症状が残っている場合は、マスクの着用や周囲への配慮が必要です。職場によって独自の基準がある場合もありますので、所属先の規定も確認してください。
Q4: 高齢の両親がいます。特に注意すべきことはありますか?
A4: 高齢者は重症化リスクが高いため、特に注意が必要です。
- 毎年のワクチン接種を推奨します
- 体調の変化を細かく観察し、早期の医療機関受診を心がけてください
- 基礎疾患がある場合は、かかりつけ医との連携を密にしてください
- 栄養状態と免疫機能の維持に努めてください
- 感染者との接触を避け、外出時は感染対策を徹底してください
Q5: 妊娠中ですが、ワクチン接種や治療について心配です。
A5: 妊娠中の方もインフルエンザワクチン接種が推奨されています。妊娠中は免疫機能が変化し、重症化リスクが高くなるためです。ワクチンは妊娠のどの時期でも安全に接種可能とされています。感染した場合の治療薬についても、妊娠中に使用可能な選択肢があります。必ずかかりつけの産科の主治医と相談しながら、適切な対応を取るようにしてください。

まとめ
インフルエンザの流行は毎年繰り返される身近な健康問題ですが、正しい知識と適切な対策により、感染リスクを大幅に軽減することができます。
重要なポイント
- 予防が最も重要:ワクチン接種と日常的な感染対策の実践
- 早期受診:症状が現れたら48時間以内の医療機関受診
- 適切な療養:十分な休養と感染拡大防止への配慮
- 高リスク群への特別な注意:高齢者、小児、妊婦、基礎疾患のある方
クリニック (松戸市)での診療経験から、多くの患者様がインフルエンザについて不安を抱えていることを実感しています。しかし、適切な予防と対処をすればその不安は軽減すると思います。
流行期を迎える前に、今回ご紹介した対策を日常生活に取り入れ、健康的に冬を過ごしていただければと思います。症状が気になる場合や不明な点がございましたら、遠慮なく当院にご相談ください。皆様の健康維持のため、引き続き正確な医療情報の提供に努めてまいります。
参考文献・情報源
執筆者プロフィール

田邉弦
丹野内科・循環器・糖尿病内科 院長
- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医
- 日本循環器学会 循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会 認定医
- 日本内科学会 JMECCインストラクター
- 日本救急医学会 ICLSインストラクター
- 認知症サポート医
