- 2025年10月28日
【内科医が解説】腸活とは?今日から始められる腸内環境改善の方法

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉優希です。
最近、健康雑誌やテレビ番組で「腸活」という言葉を耳にする機会が増えてきました。「腸活って何?」「本当に効果があるの?」と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。腸活とは、腸内環境を整えることで、便通の改善だけでなく、免疫力の向上や心身の健康維持を目指す取り組みのことです。実は腸内には約1,000種類、100兆個もの細菌が生息しており、私たちの健康に大きな影響を与えています。
内科専門医として、日々の診療の中で「お腹の調子が悪い」「便秘が続いている」「なんとなく体調がすぐれない」といったご相談を多くいただきます。このような症状の多くは、腸内環境の乱れが関係していることがあります。
この記事では、腸活の基礎知識から具体的な実践方法まで、医学的な根拠に基づいて分かりやすく解説いたします。
目次
- 腸活とは何か?基礎知識を理解しよう
- 腸内環境が乱れるとどうなる?具体的な症状と影響
- 腸内フローラ(腸内細菌叢)の重要性
- 今日から始められる腸活の実践方法
- 腸活に関するよくある質問(Q&A)
- まとめ:継続的な腸活で健康的な生活を
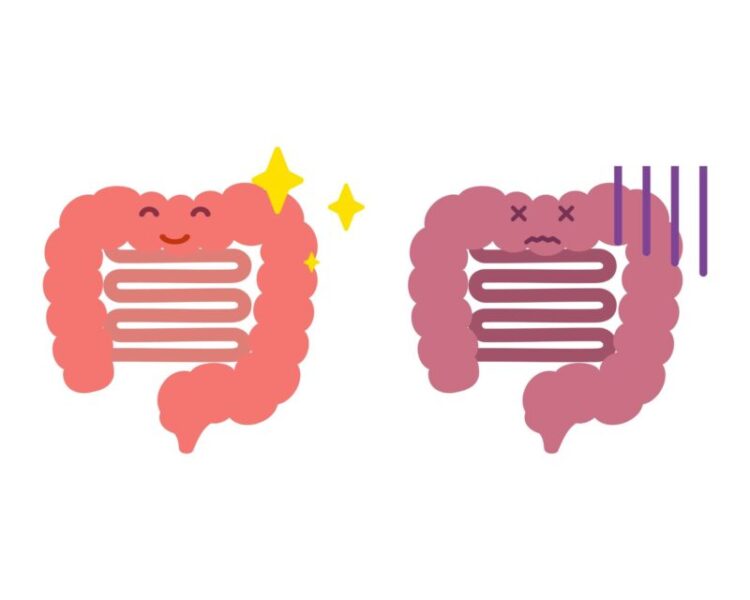
腸活とは何か?基礎知識を理解しよう
腸活の定義
腸活とは、腸内環境を整えて健康な状態を維持・改善する活動の総称です。具体的には、食生活の見直し、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理などを通じて、腸内細菌のバランスを良好に保つことを目指します。
腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、私たちの心身の健康に深く関わっています。単なる消化器官ではなく、免疫機能の約70%を担っているとも言われており、全身の健康を支える重要な器官なのです。
腸内細菌の種類と役割
腸内には、大きく分けて以下の3種類の細菌が存在しています。
善玉菌(有用菌) ビフィズス菌や乳酸菌などが代表的です。腸内環境を整え、便通を改善し、免疫力を高める働きがあります。また、ビタミンの合成や感染症の予防にも貢献しています。
悪玉菌(有害菌) ウェルシュ菌や病原性大腸菌などが該当します。これらが増えすぎると、有害物質を産生し、便秘や下痢、免疫力の低下などを引き起こす可能性があります。
日和見菌(中間菌) 腸内細菌の大部分を占める菌です。通常は特に害も益もありませんが、腸内環境の状態によって善玉菌にも悪玉菌にもなり得る特徴があります。
理想的な腸内環境は、善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7のバランスと言われています。このバランスが崩れると、様々な不調が現れることがあります。
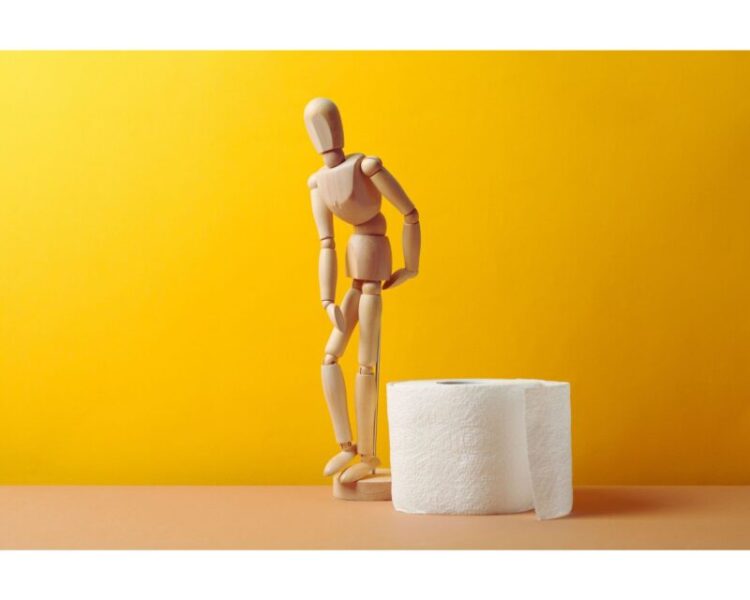
腸内環境が乱れるとどうなる?具体的な症状と影
身体的な症状
腸内環境が乱れると、以下のような症状が現れることがあります。
消化器症状
- 慢性的な便秘や下痢
- お腹の張り(腹部膨満感)
- ガスが溜まりやすい
- 食後の不快感
たとえば、「朝起きてもお腹がすっきりしない」「旅行に行くと必ずお腹の調子が悪くなる」といった経験をお持ちの方は、腸内環境の乱れが関係している可能性があります。
下痢の原因に関しては、以前のブログ「【松戸市内科医が徹底解説】下痢の原因は?症状別の見分け方と正しい対処法」をご覧ください。
全身症状
- 肌荒れやニキビの増加
- 疲れやすさ、だるさ
- 風邪を引きやすくなる
- アレルギー症状の悪化
腸内環境の乱れは、肌の状態にも影響を与えます。これは腸内で産生された有害物質が血液を通じて全身に運ばれることが一因と考えられています。
精神面への影響
近年の研究では、腸と脳が密接に関連していることが明らかになってきました。これは「腸脳相関」と呼ばれています。
腸内環境が乱れると、以下のような精神的な変化が起こることがあります。
- イライラしやすくなる
- 気分の落ち込み
- 集中力の低下
- 睡眠の質の悪化
実際に、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの約90%は腸で産生されています。そのため、腸内環境を整えることは、心の健康維持にも重要なのです。
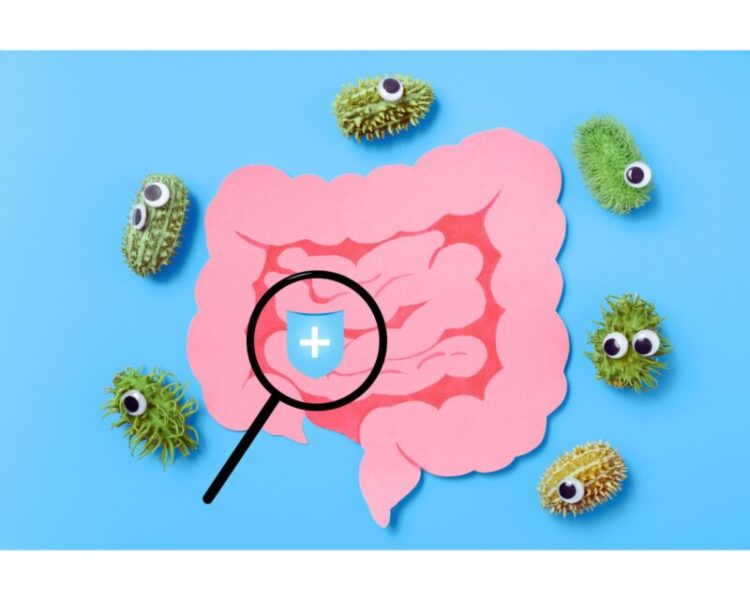
腸内フローラ(腸内細菌叢)の重要性
腸内フローラとは
腸内フローラとは、腸内に生息する細菌の集まりのことです。顕微鏡で見ると、まるでお花畑(flora)のように見えることから、この名前が付けられました。
一人ひとりの腸内フローラは、指紋のように異なっており、生活習慣や食生活、年齢、ストレスなどの影響を受けて常に変化しています。
腸内フローラと免疫力の関係
腸内フローラは、私たちの免疫システムと深く関わっています。善玉菌が優勢な腸内環境では、免疫細胞が適切に働き、病原菌やウイルスから体を守る力が高まります。
実際の研究データでは、腸内環境が良好な人は、そうでない人と比べて感染症にかかりにくい傾向があることが報告されています。特に冬場の風邪やインフルエンザの予防には、日頃からの腸活が効果的と考えられます。

今日から始められる腸活の実践方法
食生活の改善
発酵食品を積極的に取り入れる
善玉菌を増やすためには、発酵食品を日常的に摂取することが推奨されます。
- ヨーグルト:朝食に100〜200g程度
- 納豆:1日1パック
- 味噌:味噌汁として1日1杯
- キムチ、ぬか漬け:小鉢1皿程度
これらの食品には生きた善玉菌(プロバイオティクス)が含まれており、腸内環境の改善に役立ちます。ただし、一度に大量に摂取するのではなく、毎日少しずつ続けることが大切です。
食物繊維を意識的に摂る
食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える重要な栄養素です。
水溶性食物繊維(海藻類、果物、大麦など)と不溶性食物繊維(野菜、きのこ、豆類など)をバランスよく摂取することが理想的です。
具体的には、以下のような食材を選ぶのがおすすめです。
- 朝食:オートミール、バナナ、リンゴ
- 昼食・夕食:海藻サラダ、きのこ類、根菜類
- 間食:ドライフルーツ、ナッツ類
目安として、1日に20〜25g程度の食物繊維摂取が推奨されていますが、現代人の平均摂取量は15g程度と不足しがちです。

オリゴ糖を活用する
オリゴ糖は善玉菌のエサとなる成分(プレバイオティクス)です。バナナ、玉ねぎ、ごぼう、大豆などに含まれています。これらの食材を意識的に食事に取り入れることで、腸内の善玉菌を効果的に増やすことができます。
生活習慣の改善
適度な運動を心がける
運動は腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。激しい運動である必要はありません。
- ウォーキング:1日20〜30分程度
- ストレッチ:起床時と就寝前に各5〜10分
- 腹筋運動:軽い腹筋運動を1日10〜15回
特に朝の軽い運動は、その日の腸の動きを活発にする効果が期待できます。
規則正しい生活リズムを保つ
腸の働きは体内時計の影響を受けています。毎日同じ時間に食事をとり、十分な睡眠を確保することで、腸のリズムも整ってきます。
- 朝食を必ず食べる(腸の蠕動運動のスイッチに)
- 睡眠時間を7〜8時間確保する
- 就寝2〜3時間前までに夕食を済ませる
ストレス管理
ストレスは腸の働きに直接影響を与えます。「試験前にお腹が痛くなる」「緊張すると下痢をする」といった経験は、ストレスと腸の関係を示す典型的な例です。
リラックスできる時間を持つことが大切です。深呼吸、瞑想、趣味の時間など、自分なりのストレス解消法を見つけることをおすすめします。
水分補給の重要性
適切な水分摂取は、便の硬さを調整し、スムーズな排便を促します。1日に1.5〜2リットル程度の水分を、こまめに摂取することが推奨されます。
朝起きた時にコップ1杯の水を飲むことで、腸が刺激され、排便のリズムを整えやすくなります。
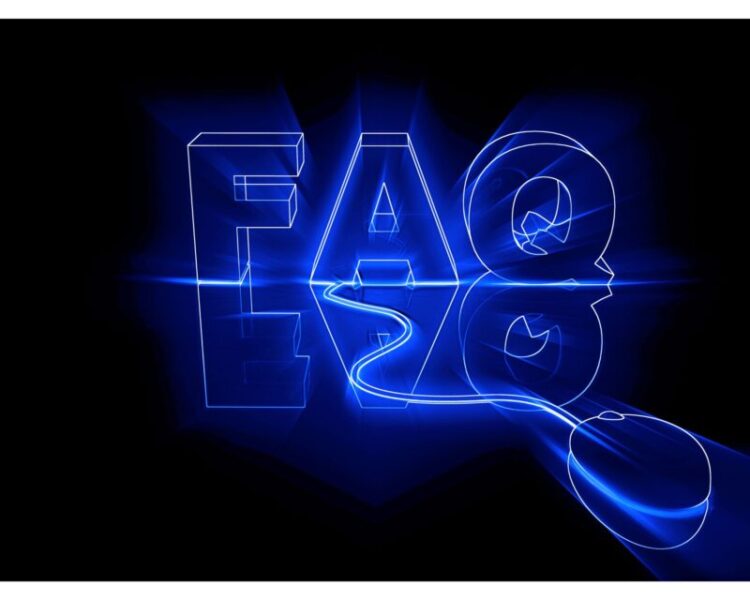
よくある質問(Q&A)
Q1: 腸活の効果はいつ頃から実感できますか?
A: 個人差がありますが、食生活の改善を始めてから2週間〜1ヶ月程度で、便通の変化を感じられる方が多いです。腸内環境の改善には時間がかかることもあるため、少なくとも3ヶ月程度は継続することをおすすめします。「すぐに効果が出ない」と諦めずに、長期的な視点で取り組んでいただくことが大切です。
Q2: ヨーグルトはどのタイミングで食べるのが効果的ですか?
A: 胃酸の影響を受けにくい食後に摂取するのが一般的に推奨されています。特に朝食後は、その日の腸の活動を活発にする効果が期待できます。ただし、タイミングよりも毎日継続して摂取することの方が重要です。
Q3: サプリメントだけで腸活はできますか?
A: サプリメントは腸活をサポートする補助的な役割と考えてください。基本は、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠といった生活習慣の改善が重要です。サプリメントの使用を検討される場合は、医師や薬剤師にご相談いただくことをおすすめします。
Q4: 便秘薬を飲んでいますが、腸活と併用しても大丈夫ですか?
A: 現在治療中の方や薬を服用されている方は、必ず主治医にご相談ください。腸活自体は基本的に安全な取り組みですが、症状や使用している薬によっては注意が必要な場合があります。自己判断で薬の使用を中止することは避けてください。
Q5: 腸活を始めて逆にお腹が張るようになりました。続けて良いですか?
A: 食物繊維の摂取を急に増やすと、一時的にお腹が張ることがあります。その場合は、摂取量を減らして徐々に増やしていく方法をお試しください。症状が続く場合や悪化する場合は、医療機関を受診されることをおすすめします。
Q6: 子どもや高齢者でも腸活はできますか?
A: はい、年齢を問わず腸活は有効です。ただし、子どもの場合は発酵食品や食物繊維の量を調整し、高齢者の場合は食べやすさや消化の良さも考慮することが大切です。ご家族の状況に応じて、無理なく取り組んでいただければと思います。

まとめ:継続的な腸活で健康的な生活を
腸活は、特別な器具や高額な費用を必要とせず、日常生活の中で誰でも始められる健康法です。以下のポイントを押さえて、無理なく続けていきましょう。
腸活の基本ポイント
- 発酵食品と食物繊維を毎日の食事に取り入れる
- 適度な運動習慣を持つ
- 規則正しい生活リズムを心がける
- 十分な水分補給を行う
- ストレスを上手に管理する
継続のコツ:完璧を目指す必要はありません。できることから少しずつ始め、習慣化していくことが大切です。たとえば、「朝食にヨーグルトを加える」「通勤時に一駅分歩く」といった小さな変化から始めてみてはいかがでしょうか。
医療機関の受診が必要なサイン:以下のような症状がある場合は、自己判断せず医療機関を受診してください。
- 突然の激しい腹痛
- 血便が出る
- 体重が急激に減少する
- 発熱を伴う腹痛
- 1週間以上続く下痢や便秘
腸の健康は、全身の健康につながります。今日から、ご自身のペースで腸活を始めてみませんか?
執筆者プロフィール

丹野内科・循環器・糖尿病内科 副院長 田邉 優希
- 日本糖尿病学会 糖尿病専門医
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本医師会 認定産業医
