- 2025年8月4日
足がつる原因を内科医が詳しく解説|予防法から対処法まで
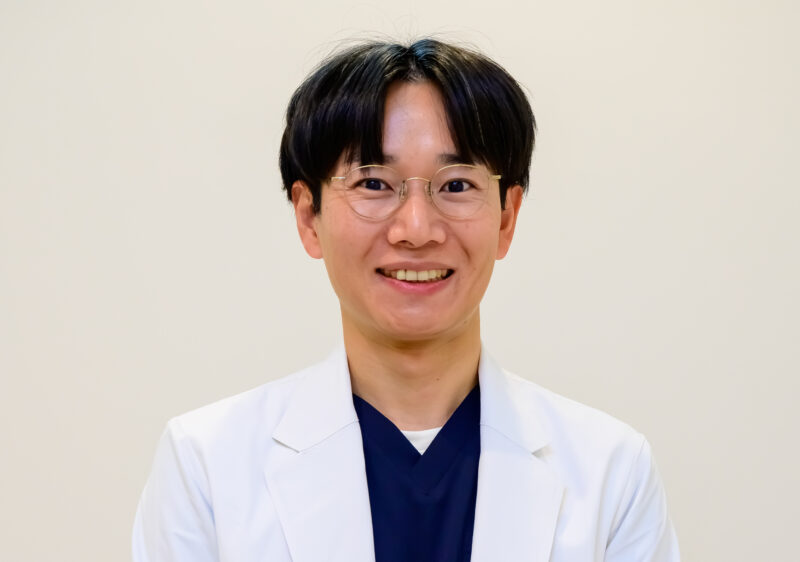
こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。「夜中に突然足がつって目が覚めた」「運動中に急に足がつって動けなくなった」このような経験をお持ちの方は少なくないでしょう。足がつる症状は多くの方が経験される身近な症状ですが、その原因や適切な対処法について正しく理解されている方は多くありません。本記事では、足がつる原因から予防法、対処法まで、医学的根拠に基づいて詳しくご説明いたします。是非ご覧ください。
目次

足がつるとは?基礎知識の解説
足がつるという症状は、医学的には「筋痙攣(きんけいれん)」または「こむら返り」と呼ばれています。これは筋肉が自分の意思とは関係なく、突然強く収縮してしまう状態のことです。
筋痙攣のメカニズム
最新の医学研究により、足がつる原因として神経系の制御異常が主要な要因であることが明らかになっています。
神経学的メカニズム
- 脊髄反射活動の異常:正常な筋肉の収縮・弛緩を調節する脊髄レベルでの反射機能に異常が生じる
- 運動ニューロンの過度な興奮:筋肉を収縮させる神経細胞が異常に興奮状態となる
- 筋紡錘とゴルジ腱器官のバランス異常:筋肉の長さや張力を感知するセンサーの働きが乱れる
従来よく言われていた「脱水や電解質不足が主原因」という説は、近年の研究で限定的な役割であることが判明しており、神経系の異常が主要な原因と考えられています。
足がつる症状は特に夜間に起こりやすく、ふくらはぎ(腓腹筋)に最も頻繁に発生します。また、足の裏や太ももの筋肉にも起こることがあります。

足がつる主な原因
足がつる原因は多岐にわたりますが、主要な原因について詳しくご説明いたします。
神経系の機能異常
最も重要な原因として、神経系の制御機能の乱れがあげられます。
具体的な要因
- 筋疲労による神経筋制御の変化
- 加齢による神経機能の低下
- 睡眠中の神経活動の変化
- ストレスや緊張による自律神経の乱れ
筋肉の疲労
激しい運動や普段使わない筋肉を使った際に起こる筋肉疲労も、足がつる大きな要因です。筋肉が疲労すると、正常な収縮・弛緩のリズムが乱れやすくなります。
血行不良
長時間同じ姿勢を続けることで血液循環が悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が供給されず、筋痙攣を起こしやすくなります。
血行不良を招く要因
- デスクワークでの長時間座位
- 冷房による冷え
- 動脈硬化
- 運動不足
水分・電解質バランスの異常
脱水や電解質異常は、神経筋機能に影響を与える要因の一つです。以下のような状況で影響することがあります。
具体的な状況例
- 大量の汗をかいた後
- 下痢や嘔吐による脱水
- 利尿剤の服用
- 過度なダイエットによる栄養不足
熱中症の症状としてに足がつることも多いと思いますが、それは水分や電解質のバランスの異常によるところが大きいと考えられます。熱中症に関しての詳細は以前のブログ「【内科医が解説】熱中症の症状を見逃さないために知っておきたい基礎知識と対処法」をご覧ください。
疾患に伴うもの
以下のような疾患が原因で足がつることもあります
- 糖尿病:高血糖により神経や血管にダメージが生じる
- 腎臓病:電解質バランスの調節機能が低下する
- 肝臓病:アルブミンの低下や電解質のバランスの調節機能が低下する
- 甲状腺疾患:代謝異常により筋肉機能に影響する
- 静脈瘤:下肢の血液循環が悪化する
薬剤の副作用
一部の薬剤が原因となることもあります
- 利尿剤
- 降圧剤(β遮断薬やカルシウム拮抗薬の一部)
- コレステロール低下薬
- 気管支拡張剤
妊娠
妊娠中、特に妊娠後期に足がつりやすくなることが知られています。これは体重増加による血管圧迫や、胎児の成長に伴うカルシウムやマグネシウムの需要増加が関係していると考えられています。
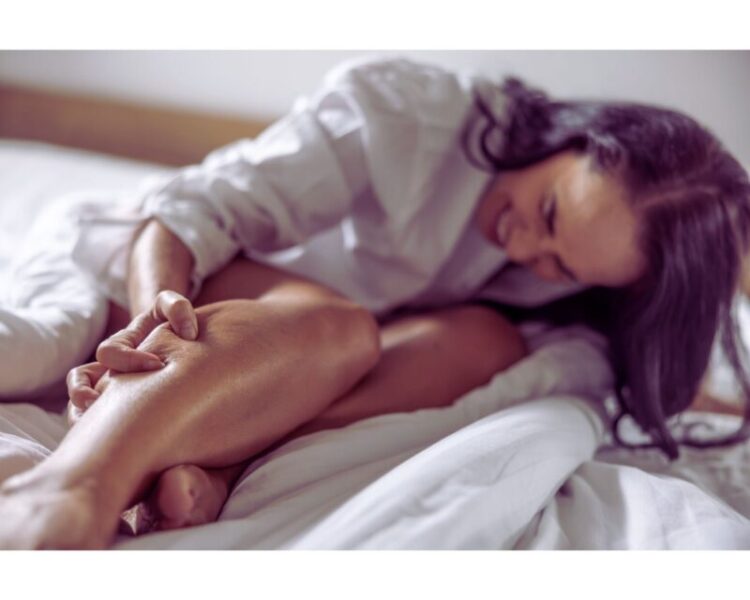
症状の特徴と身体への影響
典型的な症状
足がつる時の典型的な症状をご紹介します
痛みの特徴
- 突然起こる激しい痛み
- 筋肉が硬く盛り上がる
- 自分の意思では筋肉を動かせない
- 数秒から数分間持続する
好発時間
- 夜間から早朝にかけて
- 運動中や運動直後
- 入浴後
身体への影響
足がつること自体は一時的な症状ですが、繰り返し起こることで以下のような影響が生じる可能性があります:
- 睡眠の質の低下:夜間の筋痙攣により睡眠が断続的になる
- 日常生活への支障:痛みや不安により活動が制限される
- 転倒リスクの増加:突然の筋痙攣により転倒する危険性がある

予防法と日常生活での対策
足がつる症状を予防するために、日常生活で実践できる対策をご紹介します。
水分・電解質の適切な補給
推奨される水分摂取量
- 一般成人で1日約1.5-2リットル
- 運動時や暑い日はさらに追加
- アルコールやカフェインの過剰摂取は避ける
電解質バランスを整える食品
- カリウム:バナナ、ほうれん草、アボカド
- カルシウム:乳製品、小魚、緑黄色野菜
- マグネシウム:ナッツ類、海藻、豆類
ただし腎臓が悪い方は注意が必要ですので、かかりつけ医に相談してください。
適度な運動とストレッチ
効果的なストレッチ方法
- ふくらはぎのストレッチ
- 壁に手をついて立つ
- 片足を後ろに引き、かかとを床につけたまま前に体重をかける
- 30秒間キープし、反対側も同様に行う
- 足首の運動
- 座った状態で足首をゆっくり回す
- 朝起きた時と就寝前に各10回ずつ
生活習慣の改善
血行促進のための工夫
- 入浴時は湯船にしっかり浸かる
- 足湯の活用
- 適度なマッサージ
- 弾性ストッキングの使用(特に下肢静脈瘤や立ち仕事が多くむくみのある方に有用です)
睡眠環境の整備
- 寝室の温度を適切に保つ
- 足を少し高くして就寝する
- 寝具は足を圧迫しないものを選ぶ
栄養バランスの改善
足がつる予防に効果的とされる栄養素を意識的に摂取することが大切です
1日の推奨摂取量の目安
- カリウム:2,000-3,000mg
- カルシウム:600-800mg
- マグネシウム:300-400mg

足がつった時の対処法
足がつってしまった際の適切な対処法をステップごとにご説明します。
急性期の対処法
Step 1: 冷静になる
- 慌てずに安全な場所で対処する
- 無理に動かさず、まずは安静にする
Step 2: ストレッチを行う
- つった筋肉をゆっくりと伸ばす
- ふくらはぎの場合:つま先を手前に引く
- 痛みが和らぐまで20-30秒キープ
Step 3: マッサージ
- 筋肉を優しく揉みほぐす
- 血行を促進するよう心がける
Step 4: 温める
- 症状が落ち着いたら温タオルなどで温める
- 血行促進により回復を促す
やってはいけない対処法
以下の行為は症状を悪化させる可能性があるため避けてください
- 無理に力を入れて動かす
- 冷たいものを当てる
- 強すぎるマッサージ
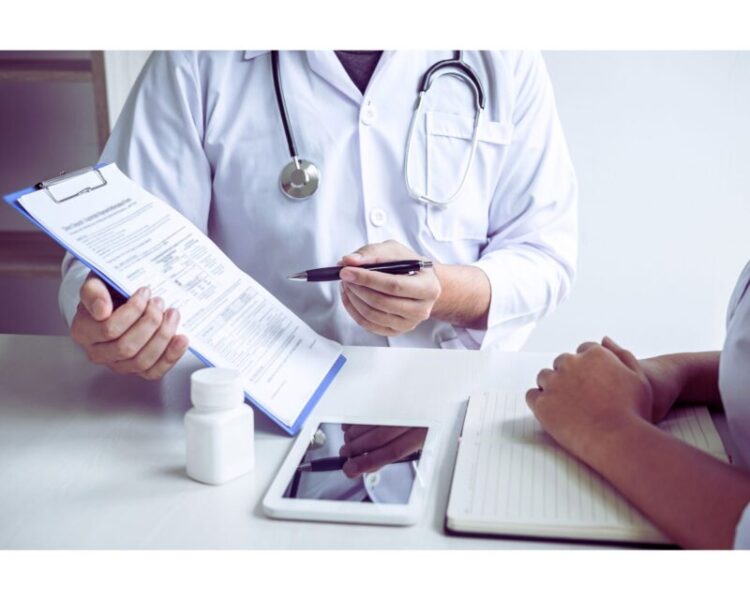
医療機関を受診すべきタイミング
以下のような場合は、速やかに医療機関での診察を受けることをお勧めします。
緊急性の高い症状
- 激しい痛みが持続する
- 足の色が変わる、冷たくなる
- しびれや麻痺を伴う
- 呼吸困難や胸痛を伴う
継続的な医療管理が必要な場合
- 週に3回以上足がつる
- 日常生活に支障をきたす
- 他の症状(むくみ、息切れ、倦怠感など)を伴う
- 既存の疾患(糖尿病、腎臓病など)がある
- 服用中の薬剤と関連が疑われる
検査について
医療機関では以下のような検査を行う場合があります
- 血液検査(電解質、血糖値、腎機能など)
- 心電図検査
- 血管エコー検査 など
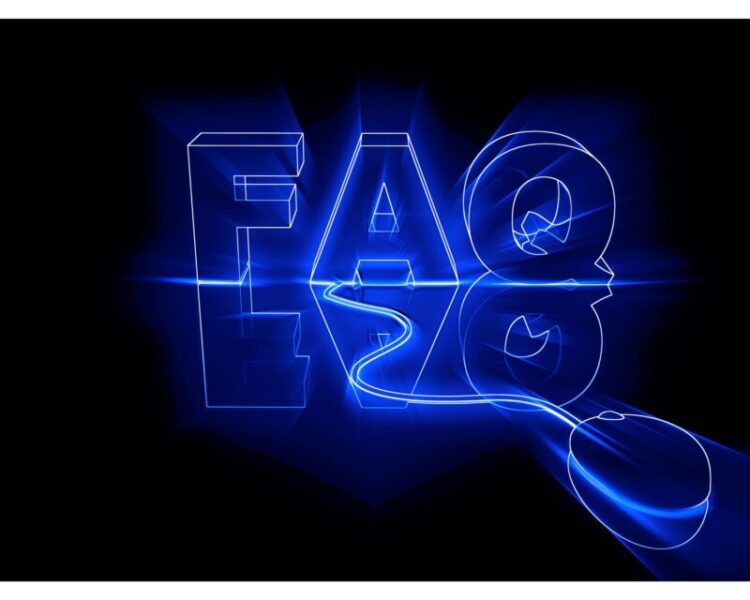
よくあるご質問(Q&A)
Q1: 足がつるのは年齢と関係がありますか?
A: はい、年齢とともに足がつりやすくなる傾向があります。これは筋肉量の減少、血行不良、慢性疾患の増加などが関係しています。ただし、適切な対策により改善は可能です。
Q2: 運動をしている人の方が足がつりやすいのでしょうか?
A: 激しい運動や普段行わない運動をした際には足がつりやすくなります。しかし、適度な運動は血行促進や筋力維持に効果的で、予防につながります。運動前後のストレッチと適切な水分補給が重要です。
Q3: サプリメントは効果がありますか?
A: マグネシウムやカルシウムなどのサプリメントが有効な場合もあると思いますが、まずは食事からの摂取を心がけることが大切です。サプリメントを検討される場合は、医師にご相談ください。
Q4: 妊娠中の足のつりは胎児に影響しますか?
A: 妊娠中の足のつり自体が胎児に直接的な害を与えることはありません。ただし、頻繁に起こる場合は母体の負担となりますので、産婦人科の医師にご相談することをお勧めします。
Q5: 薬で治療することはできますか?
A: 頻繁に足がつる場合、医師の判断により漢方薬などが処方されることがあります。ただし、まずは生活習慣の改善から始めることが基本となります。
Q6: 予防のためのマッサージはどのくらいの頻度で行えばよいですか?
A: 予防的なマッサージは毎日行っても問題ありません。特に入浴後や就寝前に軽くマッサージすることで、血行促進効果が期待できます。
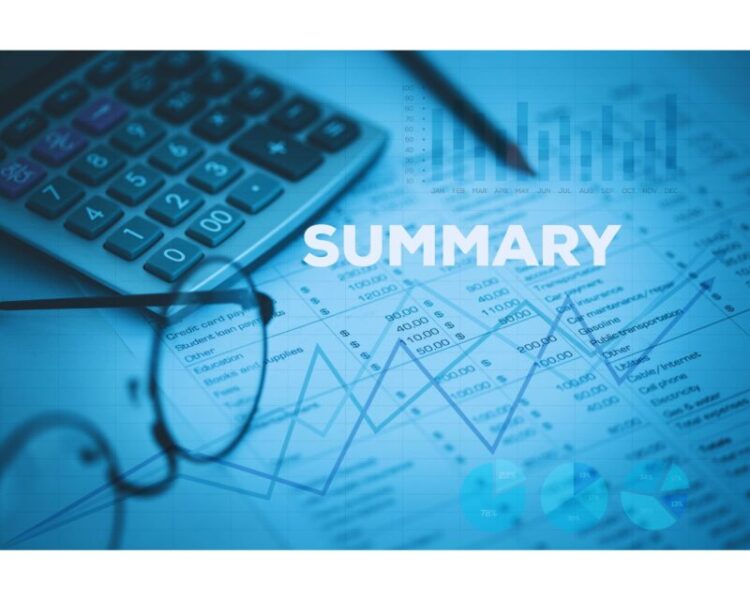
まとめ
足がつる症状は多くの方が経験される身近な症状ですが、その主要な原因は神経系の制御異常であることが最新の研究で明らかになっています。その他補助的な要因として水分・電解質バランスの異常、血行不良、筋肉疲労などがあげられます。自身に当てはまる原因に基づいた適切な対策を行うことが重要です。
重要なポイント
- 神経系の健康維持:適度な運動、ストレッチ、十分な睡眠
- 生活習慣の改善:血行促進、適切な栄養バランス
- 急性期の適切な対処:冷静にストレッチとマッサージを行う
- 医療相談の重要性:頻繁に起こる場合や他の症状を伴う場合
日常生活での予防策を実践していただき、症状が改善しない場合や心配な症状がある場合は、お気軽に医療機関にご相談ください。適切な知識と対策により、足がつる症状による日常生活への影響を最小限に抑え、より快適な生活を送っていただけることを願っております。
